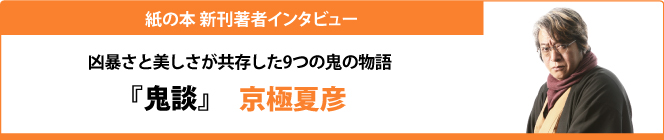凶暴さと美しさが共存した9つの鬼の物語 【京極夏彦インタビュー】
公開日:2015/4/6
鬼という言葉を聞いてわたしたちが思い浮かべるのは、頭から角を生やし、虎皮のパンツを穿いた、絵本やアニメでお馴染みのあの姿だろう。あるいは能楽の「般若」の面、秋田県のなまはげを思い浮かべる人もいるかもしれない。しかし、一般に流布しているこうしたイメージは、鬼本来の姿とはほとんど関係がない。『鬼談』を刊行した京極夏彦さんはそう語る。
きょうごく・なつひこ●1963年、北海道生まれ。94年『姑獲鳥の夏』でデビュー。96年『魍魎の匣』で日本推理作家協会賞(長編部門)、2004年『後巷説百物語』で直木賞、11年『西巷説百物語』で柴田錬三郎賞を受賞。他にも受賞多数。作品に『死ねばいいのに』『数えずの井戸』『眩談』『書楼弔堂 破曉』『いるの いないの』などがある。
「もともと昔の鬼には角が生えていないんです。鬼の記述がある『出雲国風土記』などを見ても、角が生えているなんてどこにも書かれていない。能面の般若だって鬼ではないんですよ。額から角が生えているのは、これは人間じゃありませんよ、という記号的な表現。なまはげにしても、節分にかぶるお面にしても、厳密には鬼ではありません。角が生えているものをひとまとめに鬼だと言うのは、あまりに乱暴な話。それでは鬼が気の毒です(笑)」
収録作は「鬼交」「鬼想」「鬼縁」「鬼情」「鬼慕」……と鬼づくしの全9編。しかしその中には、角を生やした赤鬼や青鬼のたぐいは一切登場しない。では、この作品で描かれている鬼とはどんなものなのだろう? 京極さんによれば、鬼とはそもそも中国において、死んでいる人、すでに亡くなった祖先を意味する言葉だったという。
「儒教では祖先を敬うことを大切にしますが、祖先はもう死んでしまってこの世にいないわけですね。それを、幽霊のようにわかりやすく記号化するのではなく、いないものはないものとして敬う。本来の意味での鬼は非存在で、だから見えない。日本では、それに様々な概念が習合します。『人でないもの』に加え、『甚だしい』という属性なんかが加えられる。結果凶暴にもなる。儒教的死生観がベースにはあるものの、日本の鬼はやや分かりにくいですね」
そうした古来の鬼観をベースにして生まれた収録作は、たしかにどれも甚だしく、凶暴だ。
「 」談シリーズの既刊3冊である『幽談』『冥談』『眩談』が、ぼんやりした不安や恐怖、ノスタルジックな回想を好んで描いていたのに対し、今回の『鬼談』には読んでいて思わずドキリとするような衝撃作が並んでいる。ラスト1行で読者を混乱の渦にたたき落とすような、ショッキングな幕切れも印象的だ。
「幕切れの1行はよく指摘されるんですが、図らずもこうなったという感じです。鬼はないものということを読者に明示すると、自ずと突き放したような結末になる。『幽談』から『眩談』まではタイトルと中身の結びつきも、自然にそうなってしまったという感じだったのですが、今回は「鬼」なので、わりとダイレクトでした。結果として甚だしい、尖った感じになってしまったかも。これまでの3冊はややダウナー系ですが、今回はややアッパーというか、全体に激しいかもしれません」
鬼とは存在しないこと 説明したら鬼ではなくなる
収録作を幾つか紹介しよう。
「鬼縁」は現代と江戸時代を舞台に、2つの異なるエピソードが交互に語られてゆくという作品だ。現代のパートの主人公は、弟が生まれたばかりの少女。彼女が両親や赤ん坊に対して抱く気持ちがこまやかに綴られていく。江戸時代のパートは、幼い頃に右腕を失った若侍・桐生作之進が主人公。武芸の家に生まれ育った彼は、何不自由のない生活を送っている。一見つながりのなさそうな2つのエピソードは、少女の父親が赤ん坊の右腕を掴んで「これだよなあ」と呟いた瞬間、不気味に重なりあいはじめる──。
「こういう話を読むと、我々は2つのエピソードに因果関係を求めてしまう。子孫じゃないかとか、生まれ変わりじゃないかとか。でも、そんなものは一切ないんです。鬼とは存在しないもの、ないもの。『鬼縁』なら縁がないということです。因果関係がない2つの事件をシンクロさせるのは、読むほうの勝手な思い込みですね」
という著者の言葉どおり、2つのエピソードは奇妙な符合を見せながら、最終的に繋がらないまま終わる。この得体の知れない奇妙な読後感、一体どう表現したらいいのだろう。
「鬼気」という作品では、帰宅途中の主人公が「顔を半分隠した女」に後をつけられることになる。これだけでも十分恐ろしいのだが、結末において主人公の母親(認知症を患っている)が発する台詞がまた恐ろしいのだ。主人公と母、顔を隠した女の関係について、とめどない想像が広がってしまう一言だ。
「あれは言われたらイヤでしょうね。この台詞にしても、野暮な説明をしようと思えばできないことはない。でも、そうすると鬼の要素が消えてしまう。説明不足で破綻しているじゃないか、と思われるかもしれませんが、報告書じゃなく小説ですからね。僕は普段から周辺情報はくどくど書くんですが、肝心な部分の説明は一切しない傾向があるもので(笑)。今回はそれがより顕著に出たのかも」
巻頭に置かれた「鬼交」は官能ホラー競作集『エロティシズム12幻想』のために執筆されたもの。寝床で金縛り状態になった女性が、周囲に漂う異様な変化や、心身の敏感な反応を一人称で語ってゆくというこの作品は、これといった事件が起きるわけではないのに、非常にエロティックな印象を受ける。存在しないもの(=鬼)を文章で描きだす、というコンセプトがもっとも端的に表れた作品かもしれない。
「書いた当時、官能小説といえば男性目線オンリーで、そういう理解はどうなんだと思っていたんですね。官能は別におやじの専売特許じゃないです。そもそも官能という言葉に性的意味はないわけだし。とりあえず男目線のエロはやめて、官能の原義にも忠実に、それでいてエロティックな感じになる小説は書けないだろうかと思ったんですね。そうなら恋愛小説じゃないから対象はいらないし、性的行為もいらないだろうと。ずっと前に書いて忘れていたんですが、そういえばこれも『鬼談』だなと思って収録しました」