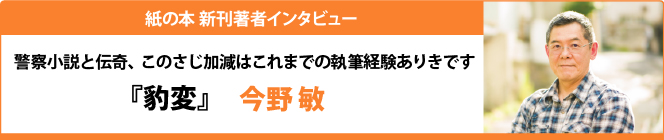警察小説と伝奇、このさじ加減はこれまでの執筆経験ありきです【今野敏インタビュー】
更新日:2015/7/6
現在執筆中の連載は何と7本。常にそうしたペースで今野敏は疾走するように書き続けている。ジャンルについても多種多様。これまでの作品群から警察小説に限って挙げてみても、小さな所轄署のチームワークが魅力の「安積班」、特殊能力を持つ科学捜査員たちの強烈な個性が光る「ST 警視庁科学特捜班」をはじめとする数多の人気シリーズ、さらに特殊部隊・SATに所属する一警察官の成長を描いた『精鋭』、これまでにない弱気な刑事が主人公の『マル暴甘糟』など、新たな切り口の作品も続々と生み出している。
今野 敏
こんの・びん●1955年、北海道生まれ。78年デビュー。「潜入捜査」「ST 警視庁科学特捜班」ほか、数多の人気シリーズを持ち、警察、伝奇、武道、SFと幅広いジャンルを執筆。2006年、『隠蔽捜査』で吉川英治文学新人賞、08年『果断 隠蔽捜査2』で山本周五郎賞、日本推理作家協会賞をW受賞。
「自分でもわけがわからなくなっちゃう時があるけど(笑)、連載に関して言えば、前回執筆したものを読み直し、その続きを書いていく。それだけなんです」
事もなげにそう言って、カラッと笑う。数多くの作品を同時に執筆するそのチャンネルはいったいどうなっているのだろう。
「何作書いていたとしても、取り掛かった途端、その主人公の佇まいが浮かんでくるんです。顔のイメージはないんだけど、何を着ているのかというところまで、ふっと見えてくる」
『野性時代』で“新しい警察小説を”という連載のオファーがあった時、見えてきたのは前髪の長い長身の青年。黒いシャツに黒いスーツと、全身黒ずくめのその人は『陰陽祓い』『憑物祓い』の主人公・祓師の鬼龍光一だったという。
「このところ、わりに地味な警察小説を書いてきていたので、ちょっと冒険したいなと思っていたんです。そこに浮かんできたのが彼。“なんだ、鬼龍いるじゃん”って(笑)、ほのかに伝奇的な匂いのするストーリーが生まれてきました」
奈良に本宮をいただく鬼道衆の末裔として、秘密裏に依頼される“亡者祓い”を請け負う鬼龍が登場したのは1994年刊行の『鬼龍』。同作を原点として生まれたシリーズは警察小説と伝奇小説が合体したエンターテインメントの傑作として、多くのファンの心を掴んできた。
「彼が最後に登場した『パラレル』の刊行は10年前のこと。懐かしいなぁと思いながら書き始めました。鬼龍と対をなす、白ずくめの恰好をした奥州勢祓師・安倍孝景など、古くから馴染みのキャラクターたちとの再会は楽しかったですね」
だが今回、ストーリーの中心に立つのは、彼らと協力関係を結ぶ、警視庁生活安全部・少年事件課の富野輝彦。『豹変』は、彼の視点を軸とした警察小説として進んでいく。
センシティブな世代に社会の歪みは表れる
東京の中学校で、生徒が同級生を刃物で刺し、現行犯逮捕された。妙にぎらぎらした眼をした3年生の佐田秀人は、富野が向かった取り調べ室で言い放つ。“邪魔をしたから懲らしめた。それだけのことだ。わしは、やるべきことをやった”。老人のように嗄れた声、妙な口調。“邪魔をいたすな。怪我をするぞ”──華奢な体躯の少年が起こした驚愕の行動。それはまるで狐につままれたような出来事。14歳の放った圧倒的な不気味さからストーリーは動き出していく。
「最近の中学生って、スマホを渡すとすぐに使えますよね。トリセツも見ずにゲームを始めてしまう。あんなこと、自分たちの世代には到底できない。生まれた時からネットもメールもある世代の理解しづらさ、会話が成立するのかなぁという不安感を、私は彼らに対して少し持っている。実際に喋ってみると、心配するほどのことでもないんですけどね」
狐憑き──姿を消した佐田を追う富野の前に、忽然と現れた祓師・鬼龍の口から出た言葉に、自身が抱いた強烈な違和感が合致する富野。どこからともなくやって来た安倍孝景も加わり、狐憑きを祓うために佐田の行方を追っていくのだが……。“これで終わるとは思えません”。鬼龍の予言通り、狐憑きの14歳は次々と出現していく。
「社会がおかしくなる時って、センシティブな年齢である14~15歳の子に、まずその兆候が表れる気がして。大国主の末裔で出雲神族の直系、自身も潜在能力のある富野は『祓師』で登場してきたのですが、彼を少年事件課の警官にしたのも、そうした意識が自分にあったからではないかと思えるんです」
“検事や判事にはどう言ったらいいんだ?”──目の前で起きたことを受け入れられず、何とか常識的な線で片付けようとする周囲の警察官たち。警察組織の中で進行するストーリーに“心霊現象”という飛び道具は通用しない。富野と周りの刑事たちとのやりとり、そして狐憑き事件の解明に至る過程には、今野さんのそんな気概が満ちている。警察小説と伝奇小説、真っ向から対立するその2つを、矛盾なく融合させたところが本作の醍醐味だ。
「どんなさじ加減で書けば、読者の方が興味を持続させてくれるのか、そしてあきれられないか。いくら伝奇の匂いを入れたといっても、あまりバカバカしいことを書くと興醒めしてしまうでしょう? その塩梅がわかるのは、やっぱり若い頃に伝奇小説をいっぱい書き、そのあとに警察小説を書いてきたという私の経験。本作ではそれが物を言ったと思います」