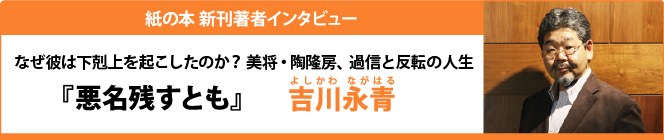なぜ彼は下剋上を起こしたのか? 美将・陶隆房、過信と反転の人生
公開日:2016/1/7
戦国三大奇襲のひとつとして高名な“厳島の戦い”。2万もの軍勢を擁する周防の大国・大内軍を見動きのできぬ平地僅かな島へとおびき寄せ、山側から奇襲、水軍で海を封鎖、5千にも満たぬ毛利軍が圧勝を収めた頭脳戦ともいえる合戦である。その戦で西国覇者への大きな一歩を踏み出した毛利元就、片や敗将として厳島を生涯の地としたのは大内軍勢を率いた陶晴賢。入道前の名を陶隆房──。
よしかわ・ながはる●1968年、東京都生まれ。2010年「我が糸は誰を操る」で第5回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞。改題した『戯史三國志 我が糸は誰を操る』で翌年デビュー。著作に、吉川英治文学新人賞候補作『誉れの赤』『時限の幻』『義仲これにあり』『義経いづこにありや』『天下、なんぼや。』など多数。
「“負けた側からの戦国史を書いてみませんか?”というお話をいただきまして。節目、節目で決戦レベルのものがある、戦国が通史で読めるようなものを。すると初期段階の群雄割拠、下剋上の時代というものは絶対に外せない。そこで下剋上を体現した人って何人いるのかなと改めて数えてみたんですね。すると実に数人しかいなかった。北条早雲、斎藤道三……」
それらの人物たちに思いを巡らせていた時、色鮮やかな花のごとく浮かびあがってきたのは、20歳の若さで大内家の家老筆頭となり、初陣のすぐ後から1万の軍勢を指揮、それらをまるで手足のように動かす稀有な才覚を持っていたと語り継がれる陶隆房だったという。
「主君の大内義隆を討ち、下剋上を成し遂げておきながら、安芸の一国衆であった毛利元就の下剋上によって転げ落ちていく。隆房は下剋上をした人々のなかでも際立ってドラマチックな人生を送った人物なんですね。そしてその人生を思うにつけ、以前から常々感じていたところがありまして。“人間の可能性というものを絶対視し過ぎではないのか?”と。現代にも通じるそのことに対し、何か物申せるのではないかという思いが、執筆の契機となりました」
知勇兼備──隆房に対する自身の先入観を検証するために膨大な資料を読むなかでわかったのは、彼への評価がなぜかあまりないこと。残されているのは行動の記録のみ。下剋上という“悪名残す”人物像はそこから組み立てていったという。
「大内家転落の契機は、尼子軍に大敗を喫した月山富田城の戦いなのですが、その際、隆房がどんな行動をとったかという記録から人物の土台となるエッセンスは抽出されてきました。戦は1年3カ月にも及び、兵は疲弊、将たちも戦意喪失、その局面にきても“ここまで来た以上、最後まで戦わねば”と隆房は撤退に、ひとり断固反対したと。そこまでやってきたことを無にしてはならぬという考え方はある意味正しいのですが、まぁ、愚直なまでに一本気な人だったんだろうなぁと」
さらに隆房のプロフィールを彩るのが戦場で視線を集めるほどの美しさ。そして主君・大内義隆の寵童あがりという過去。
「現代から見れば異色ですが、戦国時代において大将が配下の男を抱くのは、それによって揺るぎない信頼関係を示してやることでした。その美しさから寵童として愛され、後に才を買われて家老筆頭にまでなり、と、そこまで目を掛けてくれた義隆に対し、一本気な隆房は家臣の鑑ともいえる忠誠心を抱いていたと思うのですが……」
史実は“義隆を討ってしまった”ことを示すのみだ。陶隆房はなぜ下剋上を起こしたのか?物語はこまやかにその過程と“反転”の瞬間を追っていく。
照射したいのは“人間の物語”
「私たちはこの物語よりもずっと後世に生きる人間ですから、何が起きたということはすべてわかっている。ただ登場人物は現在進行形ですから、自分の判断や選択が正しいかどうかは絶対にわからない。だから私も隆房たちとそこにいるつもりで書いていました。隣に座って会話をしつつ、物事を一緒に考えて」
“何をすることが最善なのか”。日々、それを考えて生きること──それは昔も今も変わらぬ人の営み。時代小説から現代へと照射したいのは“人間の物語”であると吉川さんは言う。本作でのその大きな軸は“戦友”として信頼関係を育みつつも、後にそれが“反転”してしまう隆房と元就にも通っている。ストーリーは尼子軍に攻め込まれた毛利の居城・吉田郡山城に隆房が援軍として駆けつける場面から始まっていく。
「元就との戦いで隆房が生涯を閉じるということを考えると、この物語はふたりの絡みなしには語れないんですよね。そんな彼らが初めて出会ったのが吉田郡山の戦い。“あ、ここからだな”と思いました。本作は隆房の物語であると同時に、元就との交流の物語でもあるんです」
隆房21歳、元就45歳。立場こそ隆房が上だが、彼を見つめる元就の視線にはまるで我が子に対するような情も垣間見える。そしてそれは、どこか吉川さんの視線のようにも感じられる。
「隆房を見つめていく元就は、私が書いていきたいと思ったことを代弁してくれる人でもありました。ふたりは西国の行く末や領国の統治について、どちらも一家言あった人。いずれ劣らぬ才の両者を捉えた時、あ・うんの呼吸で相手が何をしようとしているのかがわかってしまうような関係性が自然に出てきました。それは後に起こる“反転”からの対立にも影響を及ぼしていくのですけれども」
その一方で隆房が対峙していくのが大内家内部の問題である。月山富田城の戦いでの敗走により、文治派の相良武任が台頭、そしてその戦いで跡継ぎをなくした大内義隆の心は戦から離れ、武断派の隆房は追いつめられていく。貴族の如く文化に傾倒し、莫大な浪費を重ねる主君・義隆。繰り返される臨時徴税に苦しむ領民。そんな大内家を建て直そうと苦心する家臣たち。そこで誰が主導権を握るか? 家中には対立の軸が幾重にも増えていく。
「義隆は大内家が没落する原因になった人。ただ、武士といっても人間だし、心が折れてしまうところは現代人と変わりなく、むしろ私たちと近しいところがあるような気がして。書いている最中も“何やっているんだよ”と思いつつ、不思議と責める気にはなれませんでした」
そんな義隆に対する隆房の心の動きを物語は繊細な描写で掬っていく。そこには主従としてだけではない、かつて寵を得ていた複雑な感情も絡んでくる。
「武士という人たちの心には、非常にウエットな部分も重きを占めていた気がするんですよね。情けを受けていたわけだから、“命を掛けて義隆を守る”と、隆房の行動の形は男のやり方だけれど、ベースにあったのは、慕情、恋愛に極めて近かったのではないかと」
その義隆をなぜ殺してしまったのか──そこに吉川さんならではの人間を捉えた“目”がある。その後、大内家を掌握してからの隆房の強引なやり方にも。
「その姿に本作で私の書きたかったことが表れている。人間には無限の可能性があるとよく言いますよね。たしかにその通りかもしれない。でもそれ、言いっぱなしだとすごく無責任だと思うんです。みんなが人間の力を過信し過ぎることになってしまうんじゃないかって」
そしてみずからの過信を隆房が知る時がやってくる。吉川さんが「どれだけ熱く書けるか」ということを念頭に置き、執筆したという厳島の戦いだ。