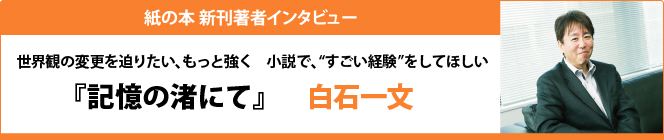世界観の変更を迫りたい、もっと強く 小説で、“すごい経験”をしてほしい
公開日:2016/7/6
もう理屈は必要ない 人間は人間のままあるべき
「世界観について少し強い変更を読者に迫っていきたいと思っているんです。この小説はその第一歩ですね。何となくぞわぞわするというか、それが全部頭のなかにある、というような」
物語が長い旅を終え、記憶とは食い違う遺稿の真実が明かされるとき、同時に提示されること──そこに白石さんがこの小説で最も言いたかったことが込められている。10年の歳月をかけて熟考し、辿り着いた考え。それは不確かで、曖昧な世を生きていくための、地に足の着いた力ともなる。
「人間は人間のまま、あらねばならない。たとえば神のような存在に自分たちの問題をゆだねることなく、人間として解決しなければいけないと思うんです。たとえば人を殺さないとか、差別しないとか、人間として当たり前のことに理屈をつける必要なんてないですよね。理屈をつければつけるほど、そうした当然のことを守らなくて済む理由がどんどん増えてくるだけですから」
本作を読み、自分のなかにブレや揺らぎを感じたなら、そのなかに“自分だけの自由がある”と白石さんは言う。
「自分だけの価値を獲得してほしいんです。何かをまとめていく力とか、ダイナミズムに呑み込まれないために」
取材・文=河村道子 写真=下林彩子
『記憶の渚にて』
白石一文 KADOKAWA 1700円(税別)
世界的なベストセラー作家だった兄が謎の死を遂げた。彼の遺品のなかから発見された随筆。我が家の歴史を綴ったはずのそれは自分の記憶とは大きく食い違う、偽装されたものだった。そこにある意味とは? 兄の死の真相とは? 150年の時を超え、海を跨ぎ、すべての謎がひとつの像を結ぶとき、物語は問う。“あなたの記憶は、あなただけのものですか?”