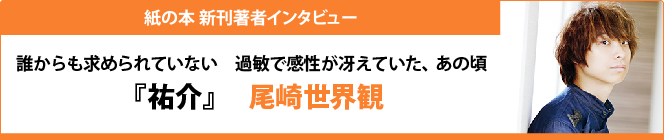誰からも求められていない 過敏で感性が冴えていた、あの頃
公開日:2016/8/6
ロックバンドのボーカリストが小説を書く。それ自体は珍しくない。町田康や辻仁成は芥川賞作家だし、コラムやエッセイで思いの丈を綴る音楽家も多い。
男と女のドキッとする瞬間や、出口のない毎日へのいらだちなど、尾崎世界観の歌詞は行間からいろいろ妄想させられる。言葉への愛が深いからこそ、小説への挑戦は納得だ。
「昔から本を読むのは好きだったし、音楽誌などでコラムも書かせて貰っていて、いつか小説を書きたいと思っていました。実際に話が進んだのは、1年半くらい前に文藝春秋の編集さんと出会ってから。僕のなかでは文藝春秋といえば、“小説の出版社”というイメージがあったので、そこでやれるなら絶対にやりたいと思いました」
とはいえ小説は、歌詞やコラムとは違う。同じ文章でも随分、苦労したそうだ。
「編集さんからは、『とりあえず最後まで書いてみてください。絶対に出るとは限りませんけど』と言われました(笑)。そのときは『4カ月で書きますよ!』と返したんですけど、結局、書き始めるまでに2カ月かかって、完成までに1年3カ月かかりました……」
『祐介』は、尾崎さんの10代から20代なかばに体験したことを土台に描かれた半自伝的な内容となっている。
「どんな小説にしようか随分迷ったんですけど、やっぱりバンドがうまくいかなかった時代に体験したことを書いておきたかったんです。腹立つことや嫌な奴に囲まれながら生きていて、思い返してもムカつきますけど、あのときの感覚って、今は持てない視点なんです。自分は誰からも求められていないって気持ちを抱えてて、凄く過敏で感性が冴えていた。未だにあの頃に作った曲も歌っていますからね。今回、小説を書く機会を貰ったときに、あのときの気持ちをしっかり作品で残そうと思ったんです」
音楽で表現するのと、小説では表現の仕方は違う?
「音楽の場合は、伝える方法がたくさんあるけど、小説は文字しかない。言葉で表現できないことは伝えようがない。だからこそゴールになる言葉を見つけたときは嬉しいんですけど、最初から最後までずっとそれを続けなければ相手に伝わらないという作業には苦労しました。砂漠にいてオアシスを探している状態がずっと続いていた感じです」
それは、音楽を作ることが日常になっているミュージシャンならではの感覚かもしれない。言葉以外の表現方法を持っているからこそ、文字だけで表現することが難しかったのかもしれない。
「音楽の場合は、歌詞で表現できなければメロディとか演奏で代用できるんです。気持ちを伝えるところだったら音を止めてみようとか、逆にうるさくしようとか、いろいろなことができる。言いたいことの根本的な部分は一緒なんだけど、小説は言葉だけで伝えないといけないから、そこで悩みました」
嫌な奴は今も覚えてる 僕にとっては大事な存在
主人公は、売れないバンドマン祐介。ライブとスタジオ練習に明け暮れ、深夜スーパーでバイトをして日銭を稼ぐ。かつて尾崎さん自身が辿った道だ。
「半自伝的小説と銘打ってますけど実話じゃないです。たまに『凄い人生だったんだな』なんて言われたりするけど、そんなわけないです。とはいえ、入り口は全部経験してます。土台を過剰に膨らませて、嫌な人は誇張してもっと嫌な感じで書きました。僕にとって嫌な人って大事な存在だったし、今も嫌なことをされた奴こそ忘れずに覚えてるんです」
『祐介』には、個性的な人物が多数登場するが、なかでも深夜スーパーで働く多賀さんは印象深い。
「多賀さんのモデルは深夜スーパーでバイトしてたときに同僚だったタカクラさんという人です。顔を合わせたらケンカばっかりしてるのに、なぜか一緒に帰ったりしてて。僕が社員の人と揉めて辞めることになったとき、ぼそっと『メジャーになってね』って言われて。しかもそのときの発音が測る方のメジャーで、『発音が違うんだよ、じじい!』って思いつつも、なぜか嬉しくて。あのときの気持ちを書けたのはよかったです」
深夜に働き、帰るのは朝方。完全に世間と逆行する暮らしを続ける祐介の生活の軸はバンド。だが、不思議なのは祐介は決してバンドでの成功を夢見ているわけではないこと。
「自分の話になりますけど、当時はライブハウスのノルマを稼ぐために働いてたし、バンドを続けていくだけで精一杯だった。バンドマンでいることに必死だったんです。お金がないから弦が買えなくて、思いっきりギターを弾くこともできない。こんなバンド、売れるわけねーよ! って、思ってました」
祐介は幼少期から同じ夢を見ているというくだりがある。まさにそれは悪夢で、グロい暴力描写が続く。ミュージシャン・尾崎世界観と、小説家・尾崎世界観の違いがもっとも出ている部分ではないだろうか?
「もともとあの悪夢のくだりは、2カ月間構想を練っていたときに一番最初に作った設定なんです。僕のなかにある、性とか暴力を書きたい衝動を詰め込んだ部分です。ああいった表現は音楽でやるとメロディやリズムが邪魔になってギャグになってしまうんですけど、小説として吐き出せたのは一番やってよかったなと思ったところです」
登場する女性たちは、一夜を共にするファンの子もいれば、風俗嬢もいる。描き方も極端だ。
「基本的に祐介は、女の人には興味が無いというか、人と繋がろうという気がない男なんです。僕はセックスと恋愛って別だと考えているので、そのコントラストは大事にしたいなと思って、ひとりだけ本当に好きな人がいるという部分を入れました。ちなみに余談ですけど、作品に登場するエロビデオのタイトルはものスゴく悩んで何度も書き直しています(笑)」
尾崎さん自身の女性観は?
「僕は女の人を尊敬しているので、男は女性に勝てないなと思っています。自分より上に見ています。その一方で冷たい態度もとってしまう。それは、せめてもの反抗心というか、甘えというか……」
立て続けに起きる不運のなか、祐介は、誘われるままひとりで京都へライブをしに行く。尾崎がもっとも力を込めて書いたというクライマックスだ。
「最後の章を書いているときが一番楽しかったです。あの部分だけ、僕のなかでメロディを感じて書いたところです。僕のなかで歌のような感じですね。音楽と一番近いところにある部分です。実際、京都でうまくライブができずに、町を彷徨ったことがあったんです。真夜中に鴨川を見てたら吸い込まれそうになって、漫画喫茶に行ったら、同世代の店員に冷たくされたりして。ムカついて、悔しくて、その感情が元になっています」