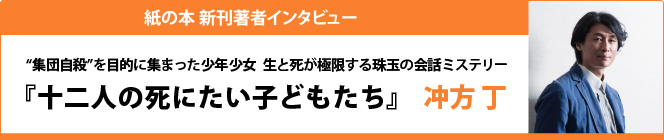「自殺サイト」で出会った12人の少年少女の生と死が極限する! 冲方丁が書きたかった“密室劇”とは?
公開日:2016/10/6
時が来た。SF小説や時代モノなど、ジャンルの枠を超えて活躍する作家・冲方丁の最新作『十二人の死にたい子どもたち』は、いまこの時代だからこそ世に放つことができた渾身の一作だ。登場するのは、「自殺サイト」を介して出会った、12人の少年少女たち。
冲方 丁
うぶかた・とう●1977年、岐阜県生まれ。4歳から14歳までを海外で過ごす。96年に『黒い季節』でデビュー。以降、ジャンルの枠を超え活躍し、09年に発表した『天地明察』にて、第31回吉川英治文学新人賞、第7回本屋大賞を受賞。近著に、『マルドゥック・アノニマス』『冲方丁のこち留(とめ)』などがある。
「執筆のお話をいただいた当時は『電車男』(2005年に映画公開)がブームになっていた頃だったんですが、掲示板で知り合うというのはまだまだ限定されたシチュエーションだったんです。でも、今回の作品はバリエーション豊かな子どもたちが揃わないと面白くならないと思っていて。そこで機会を窺っていたんですが、それから12年が経って、SNSに代表されるようにネットを使う若者たちが一般化されてきた。そこでようやく、世間の常識と僕が書きたいものが一致したんです」
12人の子どもたちは、タイトルが示す通り「自殺志願者」だ。それぞれに動機を抱え、自らの人生に終止符を打つため、一人、また一人と廃病院に集まる。そして彼らは、金庫に収められた1〜12の12個の数字から一つを選んで手にし、集合場所である地下室へと向かう。元々院内にあった時計の文字盤を飾っていたそれらの数字は、その“集い”への参加資格証明なのだ。
「時計の文字盤のように、登場するキャラクターたちは全員が対を成す存在になっています。“アイドル”と“追っかけ”、“不治の病の子”と“簡単に治る病気の子”みたいに。だから、ある子が死にたいと思えば思うほど、他の誰かの死の動機を全否定するような構造になっているんです。それに加え、時計の針が動いていくように、物語が進むにつれて対を成すキャラクターたちが刻々と変わっていくことを意識しました」
1:サトシ、2:ケンイチ、3:ミツエ、4:リョウコ、5:シンジロウ、6:メイコ、7:アンリ、8:タカヒロ、9:ノブオ、10:セイゴ、11:マイ、12:ユキ。数字を手に集まる彼らは、意気揚々としていたり、哀しみを湛えていたりとさまざま。そんな彼らの前に現れるのが、招かれざる客とも言える、13番目の参加者─通称“ゼロ番”だ。静かにベッドに横たわる彼は、どうやら死んでいるよう。果たして、彼の正体は……? そこから物語は、ミステリーとしての表情を見せ始める。正体不明の参加者を残したまま死ぬことはできない。このままみんなで死んでしまえば、自分たちは“ゼロ番”を殺害して集団自殺をした、“物言わぬ被疑者”になってしまうかもしれないから。
本作では、「警察は必ずしも真実を究明してくれるわけではない」という国家権力に対する不信感についても言及されている。執筆当時の15年、世間を騒がせたのが、作家・冲方丁の逮捕劇だ。冲方は、謂れなき容疑で留置場へ閉じ込められる事態へと陥ってしまう。
「元々、警察というものが現代において怪しい装置として批判されているということはわかっていたことだったんですが、僕自身が不当に逮捕され、ありえない経験をしたことで、本作でも記述している警察への不信というテーマが深まりました」
彼らが集団自殺という目的を達成するためには、警察も含めた外部の人間を頼ることなんてできない。だからこそ12人は、自分たちの手で真実を明らかにしようと動き出す。廃病院という密室のなかで、断片的な情報を元に真実へと迫っていく様子は、さながら戯曲のようでもある。
「本作を書くにあたっては、『十二人の怒れる男』や『二十日鼠と人間』のような手法を取り入れようと考えていたんです。SFや時代モノだと、世界そのものを描写しないと理解してもらえないんですが、現代モノは会話や素振り、その人の在り方だけで世界が描ける。そして、だからこそ通用する、“密室劇”にチャレンジしたかったんです」
現代の世相が反映された12人の自殺志願者たち
多種多様な人物によるミステリー劇に必要不可欠な“探偵役”を務めるのが、5番のシンジロウだ。そして、対を成すのは11番のマイ。知的ゲームを楽しむように状況を整理するシンジロウと、後先を考えずに発言するマイは、非常に対照的だ。
「彼らは“賢者と愚者”の関係性にあるんです。賢者はもちろんシンジロウ。それに対して、マイは愚者的に場を引っ掻き回していく。けれど、マイからはどこか本質を突くような発言が飛び出すので、書いていてとても痛快なキャラクターでした。そして、物語の後半でシンジロウと対を成すのがメイコです。彼女は、真実を解明しようとするシンジロウの邪魔をして、自分の都合だけで場を仕切っていこうとする。でも、やること成すこと墓穴を掘ってしまう。彼女も書いていてすごく面白かった」
シンジロウと同様に明晰な頭脳を見せながら物語を引っ張っていくのが7番のアンリだ。彼女が抱えている死への動機は、ほかの面々よりもはるかに“大きな”もの。だからこそ彼女は、この計画を達成することに躍起になる。自らの信念を、愚直に貫こうとするのだ。その切迫した姿は、ここ最近話題を集めた、学生デモに参加する若者たちと重なるところがある。
「いまって、特に若い世代がいろんな問題を抱えつつ、それを表明する武器を手に入れていると思うんです。そこで自分たちの力を試行錯誤しているというか。アンリも一緒で、何とかして自分の感情の出口を必死で探している。その結果、彼女は作中で表現しているような、非常に極端な答えへと辿り着いてしまうんです」
冲方自身が「極端」と称するアンリの主張。しかし作中では、それすらも否定されない。根底にあるのは、作中のキーワードとなる“自由意志の尊重”だ。
「個人の自由意志を尊重した時、各々のバックボーンによって浮き彫りになる違いを描きたかったんです。僕は幼少期に海外に住んでいたことがあるんですが、そこではクラスメイト全員の宗教が異なるなんて日常茶飯事で。すると、物事の考え方も見事に違う。たとえば、日本人なら『他人に迷惑をかけてはいけません』と教えられますけど、インドの人たちは『生きている限り誰かに迷惑をかけるんだから、その代わり親切にしましょう』っていう教えなんです。彼らからすると、日本人の教えは傲慢そのもの。『じゃあ、お前はこれまで誰にも迷惑をかけずに生きてきたのか!』って怒られちゃう(笑)。そういう違いをひもといていくなかで、自然と結束や信頼が生まれていくという経験があったので、それが本作に滲んでいるんだと思います」