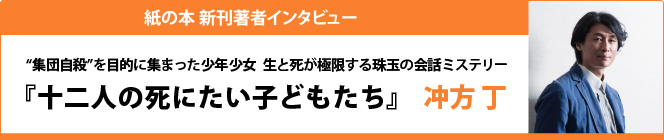「自殺サイト」で出会った12人の少年少女の生と死が極限する! 冲方丁が書きたかった“密室劇”とは?
公開日:2016/10/6
「自殺」という選択肢は常に我々のなかに存在する
他人の考えを尊重し、対話によって折衷案を模索する。それは非常に難しい反面、多様な主張が交錯する現代において、唯一の希望とも言える。だからこそ本作では、自殺そのものも決して否定はしない。
「死というものは、人間の選択肢として常に存在しているものなので、自殺する人を悪く描くような小説にはしたくなかったんです。それはそれで葛藤や決断があったことに違いはないですし。それに、リョウコのような“自己獲得”のための死もあって当然なんじゃないかと。歴史を振り返ってみれば、侍の切腹や殉教といった選択肢が実際にあったわけですから。だから、12人のなかには共感され得る死の動機を持つ子もいるんです。殺される前に死ぬとか、人を殺した償いのために死ぬとか、あるいは病気によって人間性が根こそぎ奪われてしまう前に死んでやろうとか。その反面、他人からすればどうでもいいような動機で死のうとする子もいて、それらを読者に提示することで、考えてもらいたいなと思っていたんです」
本作のタイトルは、一見すると不穏さが漂うが、読後感はとても爽やか。冲方自身も「執筆当初から、希望に満ちた終わり方にしたいなと思っていた」と話す通り、一筋の光が差しこむようなラストシーンは、読んでいて温かい涙が流れた。
このたび、現代を舞台にした密室劇にチャレンジし、見事な長編ミステリーを完成させた冲方。実は、すでに次回作の構想があるという。
「本作の大人版とも言える作品を書いてみようかと思っています。舞台設定をもう少し広げつつも、どこかに閉じ込められてしまう密室劇にしようかな、と。現代モノって、舞台が広がれば広がるほど、ドラマが散漫になってしまうんです。海外ドラマでも、アメリカ、オーストラリア、イギリスに渡る物語になってしまうと、“いま、どこにいるんだっけ?”となってしまう。それよりも、『LOST』のように、とある島に閉じ込められてしまったような状況を描く方が、人間の本質や現代性が浮き彫りになりやすい。今回はミステリーテイストの作品にしましたが、次はスティーヴン・キングみたいなホラーテイストの作品にするのが理想ですね」
取材・文=五十嵐 大 写真=三浦希衣子
『十二人の死にたい子どもたち』
冲方 丁 文藝春秋 1550円(税別)
「自殺サイト」を経由し、繋がりあった12人の少年少女。絶望からの逃避、過去への懺悔、自己承認……、彼らはそれぞれの理由から死を選ぼうとする。ところが、そこに現れたのが、13番目の参加者。彼はいったい誰なのか──。廃病院の密室を舞台に、戯曲を思わせる巧みな構成で読み手を引っ張る、渾身の長編ミステリー。