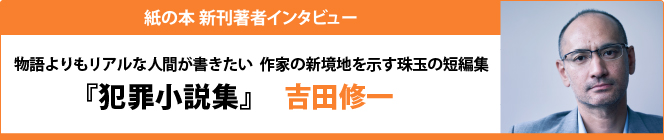人はなぜ罪を犯すのか?『怒り』『悪人』で知られる芥川賞作家・吉田修一が『犯罪小説集』で“加害者の歪んだ心”を描く!
公開日:2016/11/14
『さよなら渓谷』、『悪人』、『怒り』。芥川賞作家・吉田修一はこれまで、犯罪事件によって広がった波紋を描く長編を継続して発表してきた。最新作『犯罪小説集』は5編からなる作品集であり、それら事件小説の系譜に連なるものである。だが、なぜ今回は短編集なのか。
よしだ・しゅういち●1968年、長崎県生まれ。法政大学卒業後、97年に「最後の息子」で第84回文學界新人賞を獲得しデビュー。『パレード』で第15回山本周五郎賞、『パーク・ライフ』で第127回芥川賞、『悪人』で第61回毎日出版文化賞と第34回大佛次郎賞、『横道世之介』で第23回柴田錬三郎賞など、受賞歴多数。
「もちろん『怒り』などの流れに含まれる1冊なんですけど根本的には少し違っていて、流れの先に出てきたものというよりは原点に戻った小説なんです。何かの事件を題材にして長編を書くと、どうしても物語が必要になる。その物語を広げていくのではなく、加害者のほう、もっと人間そのものに寄っていけないかということをずっと考えていました。そこで思いついたのが短編集だったのです。人間を純粋に描くことを目的として短編を書いても、それをいくつか並べれば、おのずと物語の形になるだろうと。それで編集者に、『短編を書きたいというよりも短編集を作りたいんです』という申し入れをしました」
長編の中で誰かの人生を書こうとすれば、どうしても小説の柄に合わせた肉付けが必要になる。フィクションの占める比率も多くなるだろう。それを省くということなのだろうか。
「人間と人間が出会えばそこには物語ができます。自分はそれを描くというやり方でずっとやってきたのだと思っています。今回も、もちろん出会いはあるのですが、『その人から広がっていく話』ではなくて『その人に向かっていく話』を重視しました。物語はその人に集約されていく。そうした形でやりたいことの原点に戻ることで、リアルな人間を描けるのではないかという狙いです」
収録作の1つ「曼珠姫午睡」では、ゆう子という女性が引き起こした事件の顛末と、彼女の級友である英里子の日常とが並行して綴られていく。2本の物語の線は平行で、両者が交わることによって関係性が大きく変化するということはない。まるで私たちの実人生を見ているようでもある。人生を変えるようなドラマチックな出会いというのは、そうそうあるものではないからだ。そうした意味では『犯罪小説集』において物語は「動かない」。
「もし『曼珠姫午睡』を長編にするのであれば『二人の出会いから話を』ということになるでしょうが、そこには関心がありませんでした。そうではなくて『英里子という女性に自分がどれだけ近寄っていけるか』ということが大切だったのです」
各編にはそれぞれ着想の元になった実際の事件が存在する。『犯罪小説集』を書くにあたって吉田は、まずその事件についての資料を読むことから開始した。事件のどういうような要素が作家を刺激したのか、ということにはとても興味が湧く。
「事件の当事者が発した言葉ですね。触発されてその言葉を作中に使っているものもありますし、そうせずにエピソードの形で取り入れたものもあります。実際の事件を題材にするということでいえば、最初は元になるものがあれば小説は書きやすいだろうと思っていたのですが、まったく逆でした。書くべき相手が私の肩口あたりにいて、見下ろしているような感じがあって。事件を起こした当人が見ているという(笑)。長編の場合も同じように関係者が出てくるんですけど、彼らとチームを作って一緒に作っていく感じがある。今回は違いましたね。初めてです、こんな経験。彼らになりきって書こうと頑張っていても、なぜか「違う」と言われてしまう。あっちは正解を知っているけど、こっちはそれを考えなくちゃいけないから……いや、もちろん私が全部やってるんですけど(笑)」
事実を元にしているといっても、小説は当然自由に事実から離れることができるし、結末を変えることもできる。何が吉田の手を止めさせたのか。
「正解というと誤解を与えかねませんね。『実際の事件はこうやって起きた』という正解ではなくて、『この小説はどう書かれるべきか』というフィクションとしての正解です。私は事件の関係者を自分なりに書こうとしていたのですが、その書きようにはやはり正解・不正解があったようには思います。普段は書こうとする相手にある程度勝てるんですよ、こっちは作者だから。でも、今回は負けっぱなしでした。あっちがものすごく強いんですよね。初めての体験ですが、本当にぼっこぼこにされました(笑)」
仏師は木の中にあるべき仏の姿を見出し、それに向けてノミを振るうという。吉田の言う小説の正解とはそれに似たニュアンスなのではないだろうか。その感覚は、フィクションである小説の中でリアルな人間を描きたいという目的意識につながっているはずだ。収録作5編はそれぞれに独立した短編で相貌も異なる。どの作品がいちばん難産だっただろうか。
「全部苦戦してるんですけど(笑)、内容を制御しにくかったのは巻頭の『青田Y字路』です。登場人物たちの感情に飲み込まれた、ということでは『白球白蛇伝』の人々を書くのが骨でした。苦労したといえば、ちゃんとした短編を書いたのはたぶん10年ぶりくらいなので、そこも大変でした。これぐらいの長さの小説がいちばん大変なのはよくわかっていたんですけど、久しぶりにチャレンジしてみようかなと。いや、本当に大変でしたね。こんなに疲れたのは初めてというぐらいに、毎回ぐったりするんですよ、陸上でいうと、800メートルとかの中距離の感じでした。疲れましたね」
それほどに苦労した5作だったのだ。個々の作品を見ると、それぞれに印象に残る情景があり、それが小説の顔を決定づけていることにも気づかされる。「青田Y字路」では日本のどこにもありそうな郊外の風景、「万屋善次郎」ではそれが冬の限界集落に代わる。巻末の「白球白蛇伝」では幕切れで覗く青空が強く心に残るのだ。それぞれの作品の完成度を物語るものだが、実は吉田は各編を書くにあたり、過去にない試みをしていた。
「最初に書いたのが『青田Y字路』で、続いて『百家楽餓鬼』『白球白蛇伝』『曼珠姫午睡』『万屋善次郎』という順で『野性時代』に掲載いただきました。ところが担当編集者や、読んだ人がみんな言うんですよ、『本当に気持ち悪い』って(笑)。私自身も気持ち悪いんじゃないかと思います。実は今回、いっぺん違う視点で書いたものを別の視点で書き直すという実験をしています。小説の全部をそうやって書いたわけではなかったんですが、それでもかなりの分量を書いて、文章のリズムがとれてから書き直すということをやりました。おそらく、気持ち悪いという感覚は、その手法が影響しているんだと思います。たとえば『青田Y字路』は、はじめ木の視点で書いていました。Y字路に1本の杉の木があるのですが、それが見ているという形です。なので、ところどころ木の視点がなんとなく残ってるんでしょうね。『万屋善次郎』は、最初犬の視点でした。それを人間視点に直したのですが、元の視線が低い位置からのものだし、生理的な違和感が生じるんです。この分量だからこそできた試みで、同じことを『怒り』でやれ、と言われても絶対無理です(笑)」
『怒り』に3人の主要な視点人物が存在し、多くの声が響き合う群像小説であったことを思い出す読者も多いだろう。『犯罪小説集』は、こうした文体上の冒険も含まれた意欲作なのである。気になるのは、これが独立した試みであるのか、それとも似たような作品集がこれからも続いていくのか、ということだ。
「これはもともと、『50歳になったらやってみたい』と思っていた作品だったんです。構想としては、今回の『犯罪小説集』の他にあと2冊ぐらい同じような形で短編集をやって、それがひとかたまりの作品になるようにしたい。今回は愛蔵版ということで函入りの立派な本まで作ってもらえたので、ぜひ3冊並べたいですね。最初に言ったように、そうすると1つの物語、いや、1つの世界ができるような気がします。それがこういう短編集のおもしろさではないかなと思うんです。50歳まではもうちょっと時間があるので、覚悟を決めてやらねば(笑)。そういう意味でいうと、三部構成の一部が終わったぐらいの気持ちで、まだ全然やりきった感じがないですね。それは個々の短編を書いているときも同じでした。書き終えた瞬間に重いものがドーンと来る。宅配便がまとまって到着するときみたいで、『まだ前の箱を開けてないんですけど』って言っているのにどんどん来る。あんな感じです。作家は身を削って書くって言いますが、今回は逆に増えました。濡れた洋服をずっと着せられているようで、重たかったですね」
世界が続き、さらには増殖していく小説。読者は物語の中に浸り、その世界が現実のものであればいいと夢想する。『犯罪小説集』という作品の魅力はそうした点にもあるのではないか。
「なんというか、生ものなんですよ。だから、召し上がりはお早めに(笑)。生肉と同じで鮮度が大事ですから、そういう感じで味わってもらえれば」
取材・文=杉江松恋 写真=江森康之
『犯罪小説集』
吉田修一 KADOKAWA 1500円(税別)
はじまりは少女が行方不明になったことだった。夏の日の午後、小学生の愛華は通学路の途中にあるY字路で友達と別れ、そして消息を絶った。変質者が出没しているとの噂が隣町にはあったが……。「青田Y字路」をはじめ、実際の事件から着想を得た5短編。作者にとっては7年ぶりの短編集であり、函入りの豪華愛蔵本も同時発売される。