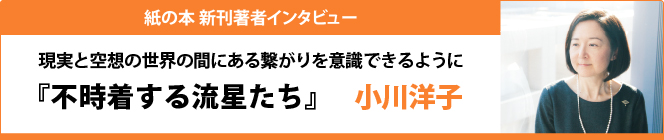芥川賞、本屋大賞受賞作家! 『博士の愛した数式』で知られる小川洋子さんの新刊の内容は?【インタビュー】
更新日:2017/2/6
一つの短編を読み終わると、次のページに記された、実在の人物や歴史的事実にまつわる短い文章にハッとさせられる。小川洋子さんの最新短編集『不時着する流星たち』はそんな不思議な読後感を味わわせてくれる。
「実在の有名人や誰もが知っているエピソードという、現実に根ざしたものから出発して、どこまでフィクションの世界に行けるか、だけどたどり着いたその世界は、現実の地平と同じ場所に作られているんだという現実と物語の世界の「繋がり」を意識してもらえるような短編集にしたいとイメージが最初にありました」
おがわ・ようこ●1962年岡山県生まれ。「揚羽蝶が壊れる時」でデビュー。『妊娠カレンダー』で芥川賞、『博士の愛した数式』で読売文学賞&本屋大賞、『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞、『ことり』で芸術選奨文部科学大臣賞など著書、受賞多数。現在、芥川賞などの選考委員も務める。
ヘンリー・ダーガー、パトリシア・ハイスミス、エリザベス・テイラー、バルセロナ・オリンピック……登場する人物や出来事は、いろいろな資料を読み込みつつ決めていったという。時代もジャンルも多彩だ。
「資料を読んでいくうちに、どこに心惹かれるのかというポイントがそれぞれ違うので、取り上げ方も自然と変わってきました。基準は私がその人物を好きかどうかではなく、小説的かどうか、そこに物語を見出せるかということです。10編書いていくうちに、私にとって「物語的な現実」というのがあるとわかってきましたね。短編だからというわけではないですが、広い視野で全体を見回すよりも、焦点を絞って小さな一点をじっと見ていた方が、扉を開けて奥に隠れている世界に行ける感じがしました」
出発点とも言えるのは、本書に第一話として収録されている「誘拐の女王」という短編のモチーフになっているヘンリー・ダーガーだという。
「実はこの作品の前に『ことり』(朝日新聞出版)、『琥珀のまたたき』(講談社)という長編を続けて書いていた時期がありまして、直接的なテーマというわけではないんですけど、アール・ブリュット(生の芸術、芸術教育を受けず名声も求めず自然に創作されたもの)についてずっと調べていたんですね。ヘンリー・ダーガーはその象徴的な人物の一人で、彼の人生や人物像をそのまま書けば小説になるだろうし、その小説を私が書いたんだったらどんなにいいだろうと思わせるような人でした。もしかしたらこの短編の語り手の「妹」はヘンリー・ダーガーの存在にすら生涯気づかないかもしれないんですけど、ヘンリー・ダーガーが生きた証が、彼自身も知らないところで物語の欠片になっているわけです。繋がろうとしていないし繋がる必要もないのに、なぜか繋がってしまっている、その「繋がり」こそがこの短編集で書こうとしたものだったのではないかと思っています」
閉じ込められた場所から想像を飛ばす
小川洋子作品に共通するのは、きらめく欠片を集めた博物館のようなイメージだ。この短編集もいろいろな人物や歴史的事実を、趣向を凝らして並べた小さな博物館のように見える。登場人物たちは、物を集めたり、数えたり、名前をつけたりという「コレクション」的な行為を繰り返す。
「私の作品はずっと偏愛的にそういった繰り返しの行為を描いていますね。やってもほとんど意味のないように思われることが、その人にとってはその人自身の存在を証明する重要な試みなんです。ヘンリー・ダーガーが誰に見せることもなく巻物のような絵を描くのも、「測量」(第五話)のおじいさんが歩いてあちこちを測量するのも、いわゆる役に立たないこと、意味のないこと、お金にならないことをやっている人がどんなに魅力的かということを書いているんですよね。何にもならないことにのめり込んでいく姿が実は最も人間らしいのかな、と思っています」
そもそも博物館的なるものへの偏愛はどこから来ているのだろうか。
「何かを閉じ込めるということに執着しているんでしょうか。私にとって『アンネの日記』が文学との最初の出会いであったことから決定づけられているように思います。アンネは隠れ家に閉じこもって生活していて、体は閉じ込められているけれども、精神はどこまでも遠くへ行ける、それを可能にするのが文学なんだというところから始まっているんでしょうね」
閉じ込めるための仕掛けもまた、小説の重要な鍵になっている。
「想像力でより遠くへ旅するためには、むしろ何か制限がかかっている方がジャンプ力が出るのではないでしょうか。絶対逃げられない壁に閉じ込められている感じから物語を始めていくんです。この短編集でも「誘拐の女王」でお姉さんが持っている裁縫箱とか、「若草クラブ」の百葉箱とか「さあ、いい子だ、おいで」の文鳥のカゴとか、何かを閉じ込める輪郭を必要していますよね。私の場合、どこまでも自由に行きなさいと言われると、かえってどうしたらいいかわからなくなってしまうかもしれません」
この魅惑的な博物館の名前に当たる本のタイトルは『不時着する流星たち』。10編の中に宇宙や星が登場する話はないのに、なぜかしっくりくる。描かれているのがみんなエイリアン的な行動をとっている人物だからだろうか。
「実はKADOKAWAから前回出した短編集が『夜明けの縁をさ迷う人々』というタイトルなんですけど、さ迷っていた人たちがようやく着地したのに不時着だった、というような、前作とイメージを連ねる意味でこのタイトルにしました。宇宙人みたいに違和感を抱かせるような人ばかりなんだけど、自分を泰然として受け止めているんです。狭い世界に生きているけれど人間的には深みがある人たちだなと思いますし、私はどうしてもそういう人に興味がわくんでしょうね」