『AB!』『Charlotte』を経て、3作目のオリジナルアニメで立ち返った原点とは――『神様になった日』麻枝 准2万字インタビュー①
更新日:2020/10/20

毎週土曜24:00~放送中
(C)VISUAL ARTS / Key /「神様になった日」Project
「『Angel Beats!』『Charlotte』を経て――、麻枝 准は原点回帰する。」――この言葉を掲げて、10月10日放送開始のTVアニメ『神様になった日』は始動した。『AB!』から『Charlotte』まで5年。そして、『Charlotte』から本作に至るまで、5年の歳月が経過した。PCゲームとしてリリース、のちにアニメ化されたKeyブランドの傑作たち=『Kanon』『AIR』『CLANNAD』『リトルバスターズ!』で、数多くのユーザーの心を揺さぶりまくった麻枝 准が、みたび原作・脚本・音楽を担当する、オリジナルアニメーション。そして宣言された「原点回帰」。麻枝作品で笑い、涙を流してきた者にとっては、最新作で披露される彼の「原点」とは何であるのか、どう心を動かしてくれるのか、楽しみで仕方がない。そんな『神様になった日』の真実と背景に、メインキャラクターを担当するふたりのキャストの言葉、そして麻枝 准自身へのロング・インタビューで迫っていきたい。
第3話放送の直後にお届けするのは、原案・脚本・音楽を手掛ける、麻枝 准のロング・インタビュー第1弾だ。今回、2時間みっちりと話を聞かせてもらった。合計2万字強のインタビューで、『神様になった日』に至る背景と、そこに込められたモチベーション、そしてクリエイター・麻枝 准の現在と今後を明らかにしていきたい。まずは、5年ぶりのオリジナルアニメーション制作のキーワードとなった「原点回帰」についてと、『AB!』『Charlotte』の総括をするべく、話を聞いた。




『神様になった日』に関しては、「リベンジしてやろう!」という気持ちはない。純粋に、感動作を作ろう、という気持ち
──まず、再び麻枝さんのオリジナルのアニメーションが拝見できるのを、すごく嬉しく思っているんですけれども。5年ぶりに新作アニメを制作することになった経緯と、麻枝さん自身が『神様になった日』について、これを作りたいと思った背景・動機について、お話を伺わせていただきたいです。
麻枝:まずはP.A.WORKSさんから「また麻枝さんとやりたい」とアニプレックスの鳥羽(洋典)プロデューサーに言ってくれたようで、そこから話を持ちかけられた形です。そのときの自分は退院明けで、特に大きな仕事も入ってなかったので、三度目のチャンスをいただけるのであれば全力で取り組んでみようと思って、快諾した次第です。そこから、どんな話を作ろうか、というところから考え始めたんですけど、鳥羽プロデューサーから最初にもらったキーワードが「原点回帰」だったので、それを自分なりに「Keyで最初の頃に作ってたような、シンプルに泣けるお話なんだろうな」と解釈して、そういう作品を考え始めた感じです。
──これまでクリエイションを重ねてきた中で、いろいろな作品が生まれてきたわけですけども、麻枝さんにとって原点とはどういうものとして存在していたんでしょう。
麻枝:自分の中で明確にあったのは、『Kanon』の真琴シナリオです。皆さんが生きてる日常プラス、ひとつのファンタジーで泣かせるっていう。そんなに突飛な舞台を用意するのではなく、ファンタジーでもありつつ現代的なものを大前提にして、そこに新たにギミックやクライマックスを考えました。
──『Kanon』の真琴シナリオが原点だとすると、麻枝さん自身がシナリオを執筆してから長い年月が経過しているわけですけど、2020年の今、その原点を見つめることにどんな意義があったのか、そして原点と向き合ったことで、見えてきたものとは何だったのか、という点を知りたいです。
麻枝:アニメの脚本を手掛けるようになってから、いろんなこと、やりたいことを詰め込みすぎていたところを感じていて、そこが逆に、もちろん結果盛り上がった部分もあって、そっちが正解になっていたりするのかもしれないですけど、そういうものを削ぎ落としていって、クライマックスで泣けることに研ぎ澄まされた作品に今回はなった、と思っていて。そういう意味では、昔ひとりでこつこつ作っていた頃の泣きゲーに、一番近い形になってますね。逆に、『Kanon』は20年以上前の作品ですけど、それが今、2020年というこのタイミングだと、受け手にとっても新鮮になるというか、「こんなに泣けるアニメがあるんだ」とか、1周回って新しいものとして受け入れてもらえる価値も生まれてくるんじゃないかな、ということを期待しています。
──なるほど。実際に、今アニメは制作が進行中だと思うんですけども、シナリオや物語全体は完成しているわけですよね。麻枝さんの中にも、手応えがあるんでしょうか。
麻枝:今のところは、まだなくて。今はダビングの最中で、おそらく最終話のダビングをしたときに、演技プラス自分の書いた音楽――『Kanon』もそうだったんですけど、自分が書いたシナリオに自分の曲をつけたときに、マックスで泣けるシーンが生まれる、と思っていて。もちろん、演技の素晴らしさがあって、これに音楽が乗ればすごいことになるかもしれない、という予感だけはあるんですけど、ダビングを終えてみないことには、手応えは得られないですね。
──わかりました。ちょっと話が戻っちゃうんですけど、「原点回帰」というワードが出てきたときに、麻枝さんはどう思いましたか?
麻枝:うーん、なんだろう? 必然とも感じられましたね。こう、自分がやりたいことをやり放題やらせてもらってきたから、逆に「さあ、やりたいことをやってください」って言われても、正直自分からは何も出てこない状態でもあったので。ここからさらにお客さんが置いてきぼりになるようなことをやっても、それは自分も戸惑うところだったので、3作目にして「原点回帰」というお題でうまいこと導いてもらったかな、と思います。
──5月に、麻枝さんも出演されていたニコ生の番組を観たんですけど、最大で4万人以上の人が観ていたじゃないですか。その視聴者数を見て、麻枝 准の新作というだけで無条件で期待して、観る人というのはたくさんいるんだなあ、と改めて感じたわけですけど――。
麻枝:自分は、そうは思ってないですよ?(笑)。
──(笑)でも実際、4万人が観てましたからね。さっき話してくれたように、置いてきぼりにしてしまった側面もあるという自覚があったとしても――いち視聴者としては置いてかれた感じはしてないですけど――自分の作品を待っていてくれる人がいることについて、どのように感じてますか?
麻枝:それは、待ってくれている人が、アニメファンなのか、自分のファンなのかによって、大きく変わるんですよね。
──では、まずは麻枝さんのクリエイティブを待っているファン、という意味でお聞きしましょうか。
麻枝:自分のファンに関しては、「麻枝はアニメに向いていない」という答えが導き出されちゃっているので。
──そうなんですか?
麻枝:そうだったんですよ。だから、「今度こそはうまくやってみせる」っていう気持ちでいるんですよね。自分のファンでいてくれる知り合いに話を聞いても、「原案だけにとどめて、脚本はプロに任せたほうがいいんじゃないか」みたいなことを言ってくれる人もいて、それはまったくその通りだと思うんです。自分はアニメの脚本の下積みがあったわけでもなく、特にそういう勉強をしてきたわけでもないし、それをいきなり『Angel Beats!』で任されて、そのときのままなので。だけど、「いや、でも、ちょっと待って。今回こそはうまくやってみせるから」っていう気持ちです。「だから、ちょっと見ていてね」っていう感じです。ほんとにそこは、自分のファンでいてくれてる方からすると、三度目の正直なのか、二度あることは三度あるなのか、冷や冷やしながら見守られている、と思ってるんですよね。
──では、広い意味でのアニメファン、という意味ではどうですか?
麻枝:そういう人たちには、たとえば『Angel Beats!』に関しては大きく受け入れられた作品なので、胸を張って、「あの『Angel Beats!』の原案・脚本の新作だよ」っていうところで、期待してもらえるかな、とは思います。ただ、4万人の視聴者の方には、いろんなきっかけがあって、P.A.さんの新作だから、とか、アニプレックスさんだから、あるいはそれと麻枝 准の3つが並んでいるから期待してくれてるのかわからないですけど、純粋に思うのは、昔泣きゲーというジャンルがあって、その第一線で活躍していたライターが書くアニメってどんなもんなんだろう、と興味を持って観てほしいなっていう気持ちでいます。
──「今度こそうまくやってみせるよ」っていう気持ちもあるし、ご自身がアニメの脚本を書かれるエキスパートであるとは思っていないけれども、それでも自分がやることに意味がある、それをもう一度世に問いたい、ということですかね。
麻枝:やっぱり、PCゲーム、我々が作ってるノベルゲームが、以前と比べると売れなくなってしまったので、そこで突破口を作って切り拓くきっかけとして、世間にKeyというブランドであったり、自分自身もそうですけど、アニメという舞台でもう1本、Keyの代名詞になるような作品を作り上げたいと思ったのも、「もう一度挑戦してみよう」と思った大きな動機ですね。
──Keyというブランドの存在を改めて示す目的や志も、『神様になった日』には含まれている。
麻枝:そうです。
──その言葉を聞けただけで、鍵っ子は歓喜ですけどね(笑)。麻枝さんが、そんな熱い気持ちで取り組んでいるんだな、と伝わってくるので。
麻枝:そのメッセージは、『神様になった日』の所信表明でも公開してるんです。どんなに高評価なものを作っても、PCのノベルゲームの業界では、そこから普段ノベルゲームをプレイしないような新しいファンを獲得していく間口の広さがもうなくて。プラットフォームを変えないと、これから先は戦っていけないと思ったので、自分の会社の中でも先頭切って切り拓いていこうと、今は頑張っているところです。
──『Charlotte』のBlu-ray BOXも出たので、以前制作されたアニメ2作品について少し振り返りたいんですが、先ほど話に出た『Angel Beats!』は、もう10年前の作品になるんですよね。CDセールスも含めて商業的な成功を収めた作品だったし、今でも『AB!』が好きな人はたくさんいて、愛されている作品だと思うんです。麻枝さん自身はその『AB!』をどう総括していて、この作品を作った経験が自身に何をもたらしたと感じているんでしょうか。
麻枝:まあ、いっぱい叩かれもしたんですけど、結果的に今でもたまにトレンドに入ったりするくらい、強力なタイトルではあって。たとえば今、うちの社員が外の会社と新しく取引をするお願いするときに、ビジュアルアーツの会社を紹介するとして、「『Angel Beats!』『CLANNAD』の」と頭につけるんですよね。それだけ、一番の代名詞になってるんですね、『Angel Beats!』と『CLANNAD』は。それを言うと、向こうもすぐ「ああ」ってわかる。そういうタイトルにできたことは、会社にとってもすごく大きいし、自分個人にとってもすごく大きい作品だったなって思います。
──なるほど。ビジュアルアーツの代名詞であるとともに、最初におっしゃったように、「叩かれた」側面もある、と。実際に面白かったし、音楽も素晴らしかったと思うんですけど、それこそPCゲームと違って、アニメーションの場合は同時にユーザーからガッと反応が来るじゃないですか。それらのリアクションは、作り手としての麻枝さんにどんな影響を与えたんでしょうか。
麻枝:なんだろう? やっぱり、ゲームっていうのは、フルプライスでいったら8,800円払って、買ってプレイするので、まず感想を言うまでのハードルが高いんですよね。8,800円払わなくちゃいけないという時点で。
──そうですね。
麻枝:でもアニメは無料で観られるから、感想を言えるハードルがめっちゃくちゃ低いんですよ。だから、1話の時点で「なんだ、このクソ脚本!」みたいなことも簡単に言える媒体であって、そういうのも全部拾うと、ものすごくメンタルが揺さぶられますよね。だから、『AB!』の放送中は、人生でも体験したことがないくらい、壮絶な思いをしました。エロゲー業界から鳴り物入りで、しかも祭り上げられるような感じで入ってきたので、そういうのが気に入らないと思う人たちもたくさんいたでしょうし。それまでも、自分のゲームがアニメになることはありましたけど、最初から自分が原案・脚本のアニメは初めてだったので、アニメファンを全員敵に回してしまったんじゃないか、と思うような恐ろしさも味わいました。
──その恐ろしさは、麻枝さんの創作に何らか影響を与えましたか。
麻枝:『Angel Beats!』に関しては……「インスタント成仏」みたいに揶揄されたところです。最後に過去も未来もよくわからないキャラたちもどんどん消えていくって言われたので、「だったらゲームでリベンジしてやろう」と思って、ゲームの制作を発表したんですけど、グダグダと続きを作れないままここまで来ちゃってますね。ただ、放送直後にはちょっとリベンジ精神が燃えたので、そういう意味では影響はありました。
──『Charlotte』の放送当時にも、麻枝さんははっきりと「今度はいいものを見せてやろうというリベンジ、それだけです」とおっしゃってました。今の話もそうですけど、麻枝さんはわりと反動の力のようなものを創作のエネルギーにされている方なんだな、と。
麻枝:はい。自分は、負のエネルギーで作品を作るタイプのクリエイターなので、それはありますね。『Angel Beats!』で叩かれることがたくさんあったので、「もっといい作品を作ってやろう!」と思ってました。『Charlotte』で完全にリベンジできた、とは思ってないですけど。
──自分の作品に対する反動というか、「いいものを見せなければならない」という気持ちに、どんどんなっていく。そういう意味では、『Charlotte』から5年間、リベンジの機会はなかったわけで、それは麻枝さん自身の体調のこともあったと思うんですけど、この5年はどういう時間でしたか?
麻枝:その時間は……何をやってたんでしょうね(笑)。そうなんですよ、『Charlotte』の前後は、一番精神的にも病んでたし、怠惰な時間だったような気がしていて。正直に言うと、才能が枯れた状態になってたんですよね。その後に大病を患って、実際に自分は一回命を落としてきて、リセットして取り戻して、もう1回、強くてニューゲーム的に人生をやり直してる感覚です。そういう意味では、『Charlotte』を作っているときは、音楽面でもスランプでしたね。自分からは新しいお話も曲も全然浮かんでこなくて、けっこういっぱいいっぱいだったし、もう体が限界を迎えて一回終わったのかなあ、という感覚でいます。
──自身の才能がすり減ってしまっているような感じだった、と。
麻枝:はい。もうなんか、才能が枯渇しちゃったなっていう感覚でした。
──だとすれば、生まれ変わって、強くてニューゲームの状態でもう一度クリエイティブをスタートできている今ならば、リベンジできるんじゃないか、という想いにもつながりますよね。
麻枝:はい。まあ、『神様になった日』に関しては、「リベンジしてやろう!」という気持ちではないですよ。もっと純粋に、感動作を作ろう、という気持ちだけですね。

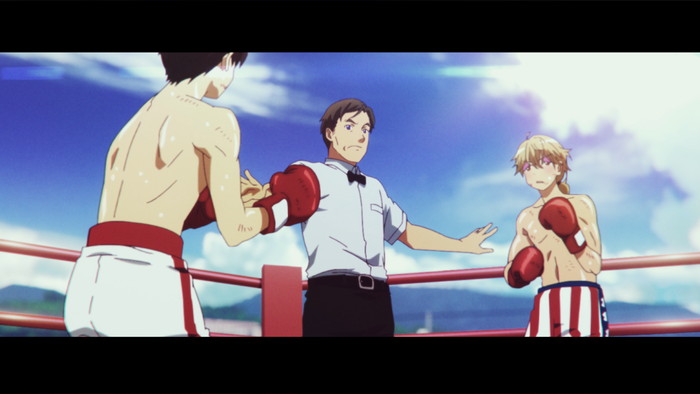


昔やっていた、泣けることに特化した作品に立ち返って、それを洗練させている
──『AB!』も『Charlotte』もいろんな要素を詰め込んだ作品だったし、それは麻枝さんも自覚されているところだと思うんですけど、逆にやり残したことがあるという感覚がそれぞれの作品を終えたあとにあったのかということと、もしあったとすれば、『神様になった日』を作りながらその感覚は満たせているんでしょうか。
麻枝:やり残した感というか……うーん、結局のところ、原案・脚本をやってるということは、最近『神様になった日』のクレジットを見て、「シリーズ構成も自分がやってることになってるのか」って気づいたんですよ。それがね、下手だったな、と。『AB!』でも『Charlotte』でも、よく尺足らずって言われていて、それはもう、完全にシリーズ構成の部分なんですよね。で、今回の『神様になった日』は、そうならないために12話で企画を作って、もし最後に駆け足になるんだったら、13話目を作れるようにしておきました。これでまた駆け足って言われたら、ほんとにシリーズ構成が下手だなって思いますけど。それで今回うまくいってるかどうかも、お客さんのもとに届いたときにしかわからないですね。
──課題は明確で、打てる手は打った、ということですね?
麻枝:一応打てるように、12話にしておきましたね。それで大丈夫なのかは、まだわかんないです(笑)。あとはもう、1年半くらいホン読みをしてくれた浅井監督や鳥羽プロデューサーたちのアドバイスや意見を信じるしかないですね。
──映像は6話まで観させていただいて、シナリオは全話読みました。正直、今麻枝さんがおっしゃったから言わせてもらうと、『Charlotte』は確かに最終話がものすごく駆け足でしたよね。点描がたくさん入っていたし。『AB!』にも、近しい印象は正直ありました。でも、今回はまったくそういう印象がなかったですよ。
麻枝:だとしたら、シリーズ構成はうまくいってるのかもしれません。
──シリーズ構成をどうするか、というのはいわゆるテクニカルな部分だと思うんですけど、クリエイティブ面に関して、この作品に臨むにあたって、自分自身に求めた成長や進化、あるいは課題は何だったんでしょうか。
麻枝:いや、むしろアニメをやるようになってから損なわれてしまったものを、純粋にそこに特化して、泣きゲー的なものをもう一回見せよう、ということですよね。アニメになって、自分がやりたいことを詰め込むんでいたのはやめようと。だから進化させたというより、昔やっていた、泣けることに特化した作品に立ち返って、それを洗練させてます。
──なるほど。ただ、原点に立ち返りつつ、泣ける物語を作る上で、さらに以前やっていたことをより進化させてものである必要はありますよね。まったく同じことをトレースするよりも、過去に泣けるゲームを作っていたわけで、同じ「泣ける」でも、よりいろんな人の心に響く泣けるものを作る、という点では進化になるのかな、と。
麻枝:でもまあ、20年前にやってたことを今やったら、案外今の若いアニメファンの人たちには新しく映るかもしれない、と思ってるんですよね。だから、自分に関してはアップデートする必要もないと思っていて、自然に新しく映るんじゃないかな、と思ってます。
『神様になった日』麻枝 准インタビュー②は、10月24日配信予定です
取材・文=清水大輔






















