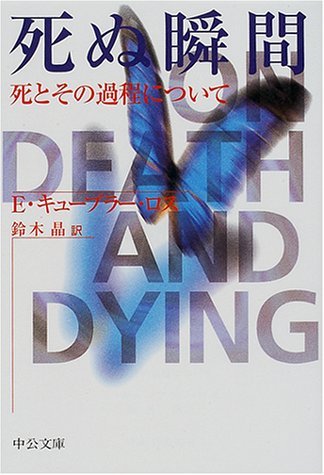人はいつから「死」を受け入れられるのか? 末期がん患者200人の声
公開日:2014/5/4
がんの宣告を受けた人が、診断から1年以内に自殺するリスクは、がんにかかっていない人の約20倍に上ることが、国立がん研究センターなどの調査で判明した(4月23日読売新聞)。2年目以降はこうした差がほぼなくなっていることから、その背景として、がんによる心理的ストレスは、診断後の数か月が最も強いことが指摘されている。
人は誰しも死に向かって生きており、死を徐々に理解し、老いや病を引き受けていく。しかし、予期せず不治の病であることを宣告された人間の心の負担は、いかなるものか。人が恐れてやまない「死への恐怖」や、「死」を受け入れる心のメカニズムについて解き明かした本がある。
14年前に書かれた『死ぬ瞬間 死とその過程について』(エリザベスキューブラー・ロス:鈴木 晶 :訳/中央公論新社)は、スイスの心理学者が200人の末期がん患者に直接面談し、彼らが死にいたるまでの心の動きをつぶさに研究した不朽の良書だ。
著者のキューブラーは、末期がん患者に「患者ではなくひとりの人間として、人生の最終段階とそれにともなう不安や恐怖、希望について学ぶための教師になってほしい」と真摯に頼み、彼らを会話へといざなった。そしてインタビューに応じた患者自身も、自分の胸の内をさらけだす貴重な機会ととらえ、協力を申し出る者も多く現れたという。3年に渡る膨大な対面取材調査や、試行錯誤の結果、“死に至る”人の心の働きについて、多くを明かすことが実現したのだ。
末期がん患者たちの心の動きは、次の5つの過程に示される。
【第1段階:否認と孤立】
自分が不治の病であることを知ったとき、多くの患者は、不安と恐怖からそれを否認するという。これは一時的な自己防衛であり、本能的に自分の心を守ろうとする、人にとって必要な反応だ。患者によってはその後、部分的受容へ移行する場合や、孤立に向かう場合もあるとのこと。
【第2段階:怒り】
絶望的な告知を一度は拒否したものの、やがて「ああそうだ。決して間違いなんかじゃない」と新たな反応が生じてくる。そして次に「なぜそれが自分なのか」という疑問とともに、怒りや妬み、憤慨が表出する。怒りはあらゆる方向に向けられ、周囲の対応は困難になる。しかしそんな状態にあっても理解され、大切にしてもらえる患者は、自分が愛されていることを知って、怒りがおさまるという。
【第3段階:取り引き】
当初は現実を直視できなかった患者が、自分以外の人間や神に怒りを覚え、やがて「避けられない現実」を先延ばしできないものかと交渉を試みる。善行の報酬として願いを叶えてもらおうと、神と取り引きするのだそうだ。患者と個別面談をした際に「教会に奉仕する」「延命してくれるなら自分の体を科学に提供する」と約束した患者が大勢現れ、キューブラーを驚かせたという。
【第4段階:抑鬱】
手術や再入院など、もはや自分の病気を否定できない状況になってくると、苦悩や怒りは、大きな喪失感にとって代わる。さらに治療による経済的負担や職を失うことなどが、抑鬱状態を招く原因となる。その一方で、死期が近いほど、この世との別れのために心の準備をしなくてはならない苦悩にもさいなまれる。この時期周囲の人間は、励ますよりも、黙ってそばにいることが望まれる。
【第5段階:受容】
これまでの段階において、周囲から何らかの助言が得られれば、患者はやがて諦めの境地に至り、自分の運命を受け入れられるように変化する。そしてある程度の期待をもって、最後の時が近づいてくるのを静観するようになるという。疲れきり、衰弱がひどくなり、新生児の眠りにも似た長時間の静かな眠りを好み、周囲に対する関心もまた、薄れてゆく。最終的には、恐怖も絶望もない存在となって旅立ってゆき、人生というひとつの環が完結するのだそうだ。
人が死ぬことを恐れるのは、それにともなう絶望感や無力感、孤独感に対してである。「死」は、死にいたる過程が終了する瞬間にすぎないのだ。この研究に携ったスタッフたちはみな、末期患者たちが示す洞察と知覚、忍び寄る死を直視しようとする勇気に、感銘を受けたという。
「死への準備教育」を日本に広めた上智大学のアルフォンス・デーケン教授は、「死への教育は、積極的に生きるための教育でもある」と語る。私たちはどうしても「死」を恐れ、「死」から目をそらしてしまいがちだ。しかし「死」を意識することで、生きることの意味や尊さを理解し、よりよく生きることができるのではないだろうか。
文=タニハタマユミ