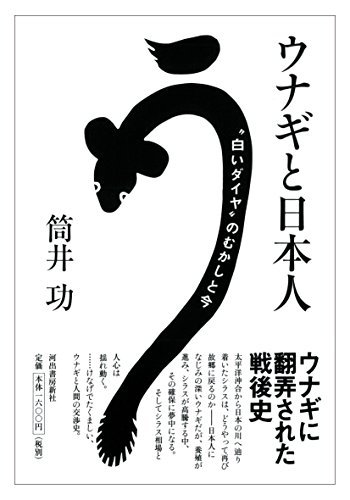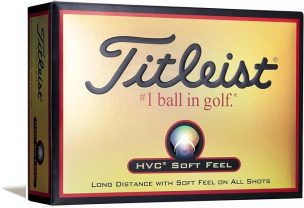【7月29日は土用の丑の日】漁獲量激減! 絶滅危惧種となった「ニホンウナギ」の現状
公開日:2014/7/26
まもなく夏の風物詩ともいえる「土用の丑の日」である。じつは、土用というのは四季それぞれにあるが、2014年の夏は、7月29日の1日のみとなっている。一説によれば、平賀源内により打たれたキャッチコピーが発祥とされているが、日本人にとって「夏の暑い盛りにウナギを食べる」というのは馴染み深い慣習だろう。
しかし、ここ数年はニホンウナギの危機がうたわれる機会も多い。世界的にも消費量が多いとされる日本だが、天然ウナギの生態に何が起きたのかは無視できない話題だ。そこで、ウナギの歴史や生態を綴った書籍『ウナギと日本人』(筒井功/河出書房新社)をたよりに、天然ウナギに何が起きているのかを整理していこう。
■生まれてから5000キロもの長旅を経て、日本へ辿り着くニホンウナギ
ニホンウナギの生態については、じつはまだすべてが明らかになっていないそうだ。しかし、平成21年5月、学術研究船「白鳳丸」が世界で初めてとなる受精卵の採集に成功している。場所は、グアム島のほぼ西方400キロの辺りだが、現在も進められる調査の中で、ニホンウナギの産卵がこの周辺だと推測されている。
東京から南方へ、直線距離で2500キロの位置で産み落とされた卵は、稚魚であるシラスとなったのちに北赤道海流に乗って西へ向かう。フィリピン東方沖で黒潮に乗り、北東へ流されると共に日本へ到達する。
道のりでいえば生まれてから5000キロもの長旅をするニホンウナギは、海から川へと向かい、やがて、鯉のように「滝登り」をしながら川を遡上していく。同書によれば、「垂直かそれに近い水流をさかのぼる」ほどの遡上能力があるといわれており、山間や平地などを問わず、生息域は日本各地にわたっているという。
■自然開発が原因で徐々に姿を消していったニホンウナギ
同書では、ニホンウナギを自然の中で捕獲していたという高知県香美市物部町安丸の男性を取材している。昭和6年生まれの男性は、小学4年生頃の記憶を辿る中で「(川の)幅が一メートルもあれば、ウナギは必ずいましたよ」と振り返っている。当時は「ツケバリ」と呼ばれる仕掛けを夕方遅くに30本ほど設置して、早朝に引き上げていたそうだ。「掛かるのは、だいたい五、六匹でしたがね」と語る男性だが、多いときは20匹以上も捕れたようである。
掛かったウナギはだいたい30センチ前後で、胸が黄色く「ノボリコ」と呼ばれていた。捕ったウナギは腹から裂き、焼いたあとに砂糖醤油をかける。砂糖がなければ焼く前に塩をかけて食べていた。何も付けずに丸焼きしたこともあったが、まずくて食べられなかったそうだ。
しかし、当たり前のように捕れていたはずのウナギはどこへ消えたのか。その背景では、人々が進めていった自然環境の開発が関係していた。男性の住む安丸には、物部川の支流である上韮生川が流れている。しかし、昭和中期に安丸と物部川河口とのあいだに永瀬ダムと杉田ダムができた。つまり、物部川河口から上韮生川の源流までに遡上を妨げる人工物ができたのである。
■人間による「捕りすぎ」と「海洋環境の変化」も姿を消した理由に
農林水産省発表の天然ウナギの漁獲量統計によれば、明治時代中期から昭和17年頃までは、おおむね2000トン台から3000トン台で推移していた。昭和18年からの5年間は戦時中のため記録がないものの、その後も同様の数値で推移し、昭和30年には統計上最高となる5932トンを記録したという。しかし、昭和53年から昭和54年にかけて、一気に1000トン台まで減少。さらに、平成5年以降は減少を続け、直近では平成24年に169トンと過去最低を記録している。
自然環境の開発により、遡上できなくなったことが一因として上げられるが、じつは、他にも原因があるようだ。同書では、乱獲と海洋環境の変化が上げられている。
密猟などを捕捉しづらい以上、統計自体の数値が必ずしも信頼できるわけではないという前提のもとだが、同書では「捕りすぎ」の原因を、稚魚であるシラスの関連業者が膨大であることに結びつけている。それは、ウナギを捕獲することで生計を立てる人たちだけではなく、ウナギを提供する飲食店や、スーパーなどの小売店も含めたものだ。その中にはおそらく、少しでも利ざやを稼ごうとするために闇のルートから仕入れる人間も考えられる。
また、河川のダム開発などだけではなく、地球温暖化による海の変化も指摘されている。近年では、台風の多発や大規模化がみられるが、これにより海流の向きや渦の発生頻度が変化しているという研究結果がある。グアム周辺の海域から西へ向かい、やがて黒潮に乗って日本へやってくるはずだったシラスだが、近年では、エルニーニョ現象により産卵場そのものが南下していたり、海上の渦に巻き込まれて黒潮に乗れず、結果として、そのまま死滅してしまうシラスが増加しているという見方もある。
■半世紀のあいだで数十分の一まで落ち込んだ稚魚の漁獲量
平成24年から平成25年にかけて、ウナギの稚魚であるシラスウナギの不漁が報道されたのは記憶に新しい。将来的に「食べられなくなるのではないか」とも危惧されているが、ウナギを取り巻く現状はどうなっているのだろうか。
独立行政法人「水産総合研究センター」の統計によれば、シラスウナギの国内捕獲量は、昭和45年まで、おおむね年間100トンから200トンの間を維持していた。昭和38年のピーク時には、年間232トンだったという。しかし、平成元年から平成20年にかけては年間10トンから20トンの範囲にまで落ち込み、平成22年から平成23年には、続けて10トンを下回っていた。直近では、平成25年に5トン前後だったと報道されており、半世紀のあいだに数十分の一まで落ち込んだことになる。
そして、平成25年、環境省はニホンウナギを絶滅の恐れがある野生動物たちが記録されている「レッドリスト」へ登録した。時機ごとの生息数などにより見直されるものの、現在は、近い将来に絶滅の危険性が高いとされる「絶滅危惧IB類」に指定されている。同リストの9段階に分けられたカテゴリーのうち、5段階目にあたる。
また、環境省とは別に、世界的な組織である「国際自然保護連合(IUCN)」も、2014年6月に同組織の「レッドリスト」へニホンウナギを登録した。現在は、3段階中で2番目にあたる「近い将来で野生での絶滅の危険性が高い種」に指定されている。
環境省やIUCNの「レッドリスト」は、いずれも漁獲や取引を制限するといった法的拘束力はない。しかし、絶滅の恐れがある動植物の国際取引を規制する「ワシントン条約」を適用される可能性が指摘されており、実際、ウナギの消費量が世界的にもきわめて高い日本へ保護対策を求められているという報道もある。
最後に、保護対策の一貫として「完全養殖」の研究は進められているものの、市場の需要に耐えうるほどの体制は今のところ確立されていないようだ。ただ、独立行政法人水産総合研究センターが人口稚魚の量産に取り組むなど、産卵から稚魚、成魚となり、次の世代を生み続けるというサイクルを実現して、ふたたびニホンウナギがたくさん見られるような環境を作り出すための研究が進められている。近い将来、日本のあらゆる河川へニホンウナギが戻ってくることを、日本人としてやはり祈りたい。
文=カネコシュウヘイ