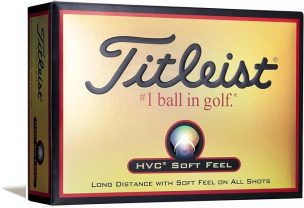夏目漱石や志賀直哉もハマっていた!? 近代日本のアイドル史に迫る
公開日:2014/8/27
明治、大正、昭和、平成と、時代は続きながらも移り変わっている。しかし、いつの時代にも人びとを熱くさせるものが存在する。その一つが、アイドルというカテゴリだ。今や幾多のユニットが乱立する時代となったが、じつは現在、盛り上がりをみせるアイドルというひとつの文化は、かつての日本で生まれた「大衆芸能」にまでさかのぼるという。
その視点から独自の考察を展開している1冊が、『幻の近代アイドル史 明治・大正・昭和の大衆芸能盛衰記』(笹山敬輔/彩流社)である。文豪・夏目漱石や詩人・谷崎潤一郎など、いまだ語り継がれる文化人たちも、こぞってハマっていたというアイドルたち。時代ごとの大衆芸能から様々な見解の並ぶ同書だが、その中から、文化人たちがハマったという「娘義太夫」についてのエピソードを紹介していきたい。
娘義太夫とは、明治時代に栄えた大衆芸能のひとつである。浄瑠璃の一流派である「義太夫節」を歌う女性グループの総称だ。とはいえ、現代のように歌詞にメロディを付けるというものではなく、三味線の音色に合わせて物語を語って聞かせる内容だったという。
古くは江戸時代からの歴史を持つが、幕府の「風紀を乱す」という理由からの命令により一時は中止に。しかし、明治時代からはふたたび寄席で一世を風靡したそうだ。
当時は若い男性を中心に人気を博したそうだが、同書によれば、その理由は「歌」によるのはもちろん、メンバーひとりひとりの「顔を見に行く」という背景もあったという。いうなれば、当時の人びとにとっての「会いに行けるアイドル」、そして、「今会えるアイドル」だったといっても過言ではないだろう。
また、明治から大正にかけてのファンたちは「ドースル連」と呼ばれていた。名前の由来は、曲の終わりかけに「ドースル、ドースル」といっせいに掛け声をかけることから来たそうだが、さながら、コールで埋め尽くされる、現代のアイドルのライブシーンとも重なる部分がある。
そして、かの文豪である夏目漱石や俳人の高浜虚子、小説家の志賀直哉なども、娘義太夫へハマっていたようだ。なかでも、高浜虚子は友人に「吾は明らかに小土佐(当時、娘義太夫のメンバーであった竹本小土佐)に恋せり」と伝えたのが記録として残っており、また、自身の作品『俳諧師』でも、娘義太夫のひとりに恋する主人公を描いている。
芸能という大きなくくりの中では、いつの世もアイドルと彼女たちに憧れる人たちがいるという図式は、何ら変わらないように思える。おそらく現代のアイドルシーンも、数百年後には同様に、語り継がれているのかもしれない。そのためにも現代のアイドルたちを目に焼き付けながら、彼女たちを改めて応援してみたくなった。また、当時の文豪たちが現代に生きていたら、それぞれどのユニットやメンバーを推していたのかも、ひじょうに気になるところだ。
文=カネコシュウヘイ