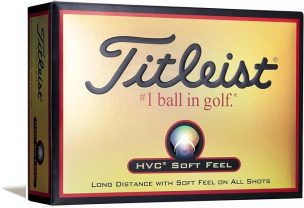知略と情熱で毛利を救った男の「戦わない」ドラマに酔う
更新日:2017/11/21
毛利両川と言われた吉川家と小早川家。吉川家には元就次男の元春が、小早川家には三男の隆景が入り、毛利本家を支えたが、彼らの印象のせいか、吉川は「武」、小早川は「知」のイメージが強い。また、後の関ヶ原の合戦では、クライマックスは小早川秀秋(隆景の養子)の裏切りであり、吉川広家(元春三男)と言えば同じ寝返るにしても、「討って出よ」との西軍の催促に「これから弁当食べるから」などというスットコな理由でごまかすなど、どうも小早川裏切りの前座のような扱いで語られることが多いのである。
しかし、なかなかどうして吉川広家という男はすごいぞ──と蒙を啓かせてくれたのが中路啓太『うつけの采配』(中央公論新社)だ。幼い頃よりうつけと言われていた広家は、三男という立場もあって吉川家を継ぐことなど考えてもいなかった。しかし父と兄の死により吉川家の当主となって以降、叔父の小早川隆景に反発したり敬服したりしながら、自分なりに毛利を支えようとする。
物語は秀吉の第一次朝鮮出兵──文禄の役から始まり、関ヶ原の仕置きまでが描かれているが、最初の読みどころは、広家が自分の「うつけ」と向き合うくだりだ。自分はとても叔父・隆景のような名将の器ではない。けれど毛利本家の照元は頼りにならないし、安国寺恵瓊は自らを毛利の軍師と過信し、己の野心を果たそうとしている。隆景から「毛利が天下をとろうなどと思うな」「恵瓊は信用するな」という遺言を受け、後を託されたものの、広家はその重責から逃げようとする。そんな彼を変えたものは何だったのか、まずはそこが山場だ。
そして後半は、知将としての広家の策略と毛利のお家存続を賭けた活躍に注目。広家の本当の敵は家康でもなければ石田三成でもなく、毛利本家を潰しかねない暗君と安国寺恵瓊なのである。家康と戦って勝てるはずがない、けれど毛利は戦う気でいる。毛利の家を残すために広家がとったギリギリの綱渡りは、思わず息を飲むほどのスリルに満ちている。しかも広家の選んだ方法は「戦わない」ことだ。戦国時代の小説において、「戦わない」ことをここまでエキサイティングに読ませるとは。さらに、広家の策略を実現するために奔走する腹心・伊知介との涙を誘う交流も読みどころのひとつだ。巧い。
小早川や吉川は関ヶ原で家康と内通し味方したのに、なぜその後は不遇をかこったのか。毛利は敗軍の総大将であり、本来であれば取り潰しが当然のところをなぜ長門・周防の二カ国を安堵されたのか。それを不思議に思うなら、ぜひ本書をお読み戴きたい。毛利と吉川と小早川の三位一体で戦国時代を生き抜き、西の大国となった毛利を、広家は最大の努力と知略と誠意で守ったのである。うつけどころか、彼がいなかったら毛利の名は消えていた。後に幕末で志士を多く生み出した長州藩は生まれなかっただろう。決死の思いで毛利を守った「うつけ」の情熱を、存分に堪能できる1冊だ。
文=大矢博子