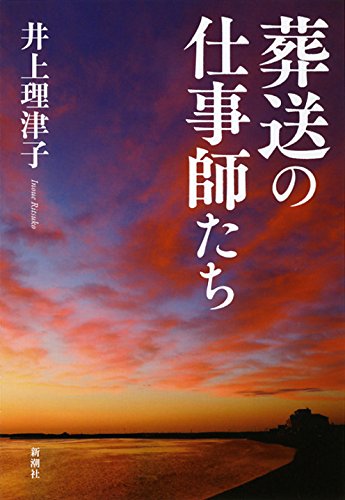湯灌師、納棺師、エンバーマー… 遺体に寄り添う仕事人たちの物語を読む
公開日:2015/6/17
先日祖父が亡くなった。病院で息を引き取ってから自宅に戻ってくると、早速葬儀社の社員がこれからの流れについて打ち合わせにやってきた。次にお坊さんがお経をあげにきて、それから親戚が弔問のためにぞくぞくと集まってくる…。息をつく暇もない。そんな中、今度は黒っぽいスーツを着た2人の女性が現れた。お悔やみを述べるとしずしずと祖父の遺体の横に座った。そして、服を脱がせて体を丁寧に拭きはじめる。着替えさせてから化粧を施すと、もう一度お悔やみの言葉を述べて静かに帰っていった。無駄のない流れるような動作はなんとなく神秘的な雰囲気で、思わずじ~っと見入ってしまった。
あの2人の女性はいったい何者だったのだろうか? あまり身近で人が亡くなったことがない私は、『葬送の仕事師たち』(井上理津子/新潮社)を読んで初めて知った。葬儀に先だって遺体を洗浄、もしくは清拭し、身だしなみを整える「湯灌師」「納棺師」という人たちだった。
本書は葬送の仕事に携わるあらゆる人々を取材し、生の声をまとめた重厚な一冊である。この中で、湯灌・納棺の仕事を始めて約6年経つ女性は、遺体を洗浄する「湯灌」をどんな風にやるのか、葬儀会館の控室で形だけ披露する。著者はそのなめらかな動きを、まるで歌舞伎や浄瑠璃の黒衣(くろご)ようだと表現する。重いものを重く見えないように、軽いものも軽くは見えないようにしたり、指先をまっすぐ伸ばしたり、所作の美しさを常に考えているとか。遺族の視線を意識した儀式的とも言える所作が、非日常の空間を作り出していたわけだ。
ここでひとつ気になることがある。相手にしているのは人でもモノでもなく、見ず知らずの遺体。知人ならばともかく、不気味に感じることはないのだろうか? 著者は思い切ってこの点に切りこんでいるが、これに対し女性は「あり得ない」ときっぱり答える。遺族も一緒にいる場でそんな感覚はまったくないという。ただ、その場で泣くことはないが、故人を想って感情移入してしまうことはあるそうだ。
身だしなみを整えるだけで済む場合はいい。中には、事故や自死などで遺体が損傷していることもある。そんなときには復元技術を持った納棺師たちが活躍する。さらに最近、最高の納棺術と評されるアメリカ発祥の技術「エンバーミング」が日本でも広がりつつあるそうだ。薬液を使って遺体を生前の姿に近づける科学的な防腐技術で、鎖骨の下の部分にメスを入れて2cmほど切開し、動脈に調合液を注入する。その圧力で静脈から血液が押し出され調合液が全身に回ると、顔色がグッとよくなるという。
しかし、火葬が主流の日本でエンバーミングは必要なのかと疑問に思ってしまうが…。2005年に資格を取得した、日本人エンバーマーの草分け的存在である男性は、中学高校時代に親友を亡くしたことから、テレビで知ったエンバーマーになることを誓ったという。バイク事故で突然亡くなって通夜に駆けつけたものの、親友は崖から落ちて顔が割れていたため、会わせてもらえなかったそうだ。エンバーミングであれば骨片から組み立てて土台を作り、よりその人らしい姿に戻すことができる。
さらに今、医学が進んだことから闘病生活が長くなり、薬の投与が多いことから腐敗の速度が早くなっているとか。顔を見ることができないまま、骨壺に収まっているのはあまりにも辛い。生きていた頃の姿と骨壺に収まった姿。その間がつながらないと、頭ではわかっていても心の底から納得することはできなくて、いつまでも引きずってしまう。悔いなくお別れをするためにも、エンバーミングは大切な技術なのかもしれない。
葬送は故人とのお別れの場。よりきれいな姿を見せてほしいのは、何も親族や友人など周囲ばかりでないだろう。最後だからこそ、きっと本人だって望んでいるはずなのだから。
文=林らいみ