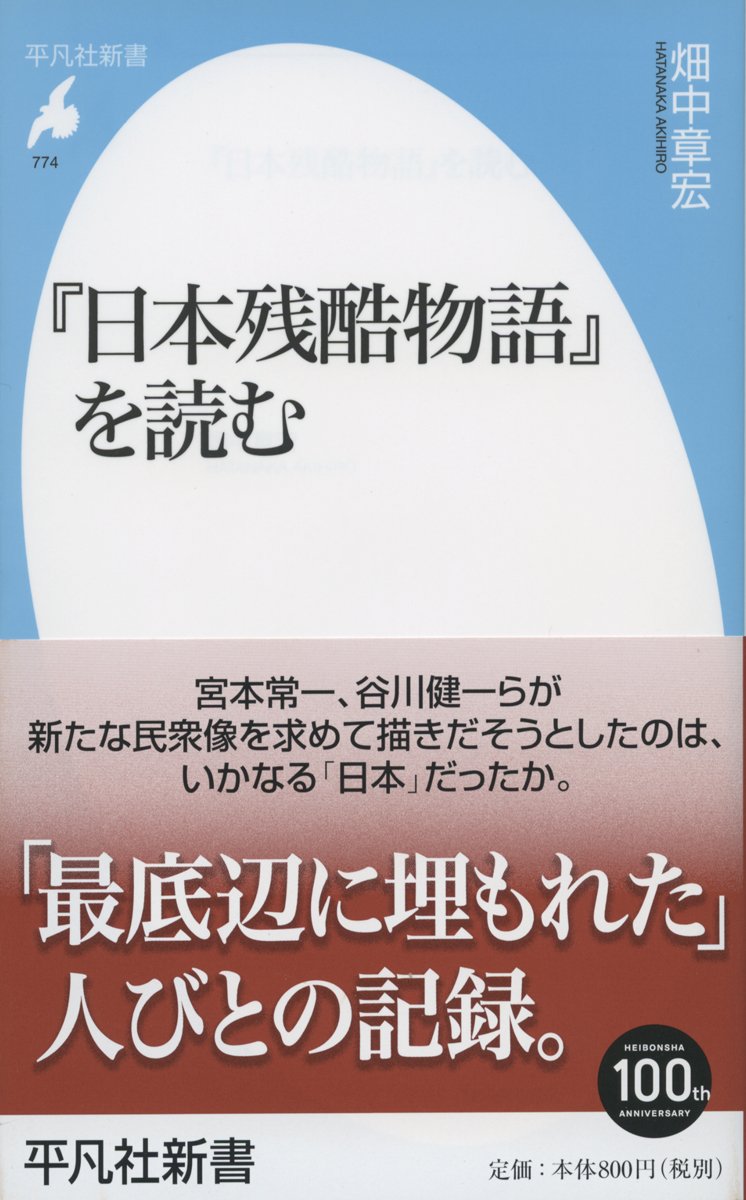戸籍に名前も載らない人たち…明治から昭和初期を生きた少年たちの残酷な青春
公開日:2015/6/27
若者の貧困問題をニュースで見る度に、人ごとではない不安を感じる人は多いだろう。この問題は、現代に限った話ではないという。昭和34~36年(1959~1961)にかけて刊行された『日本残酷物語』には、教科書には載っていない貧しい庶民の歴史がまとめられている。これを編集したのは、後に雑誌『太陽』の編集長となる谷川健一と、『忘れられた日本人』などの著書で有名な民俗学者の宮本常一だ。
「『日本残酷物語』を読む」(畑中章宏/平凡社)は、出版された当時の社会状況や、編集作業の舞台裏などを解説しつつ『日本残酷物語』を読み解いた1冊だ。そのなかから、明治から昭和の初め頃、実際に生きられた“残酷な青春”を紹介しよう。
●「戸籍に名も残らない」――雇われ先もなく結婚もできない者の末路
佐渡島の明治5年(1872)の戸籍に「伯父」「伯母」とだけ記された、名もなき者たちがいる。東北地方では「おんじ」「おじ坊主」と呼ばれる者たちだ。彼らは、村の余り者として扱われ、一人前の人間としての発言権や人格は認められることはなかった。そして、名さえ記録に残されないまま、単なる家の労働力として一生を終えた。
かつて、農家の相続は長男が行うのが一般的であり、次男以下は奉公に出るか、婿養子に入るしか、生きていく術はなかった。そのため、婿や嫁として他家に入るあてがなく、奉公先も決まらない者たちは、成人しても一生生家で暮らさざるを得ない。近代産業が発達すると、徐々に都市へ出稼ぎに行くようになるが、個人の意思で一人暮らしなどできない時代のこと。彼らは長男やその子供たちとまともに口を聞くこともはばかられ、家畜同然の扱いを受けることもあったという。
●「誰にも気に留められない自殺」――帰るところはないも同然の少年
昭和一桁代、大阪付近の農村部に生きた少年の人生も紹介しよう。農村地帯とはいえ、この地域では近代の幕開けから、多くの子供が家内工場で作った製品を卸先に届ける役割を担っていた。そのため、義務教育が施行されたにもかかわらず、病気でもないのに学校を欠席する子どもが多かったという。
北田という少年は、12、13歳になると、家のかまどで出た灰を肥料として売り歩き、日銭を稼いでいた。家族は、北田の稼ぎをあてにする母1人のみ。母は相手を見つけては体を売っていたようだが、子を養っていくという感覚は既に擦り切れていたようだ。北田少年は稼ぎがないと家に入れてもらえず、お宮の拝殿で寝る日もあった。昭和10年(1935)を過ぎた頃からは、化学肥料の普及で灰の需要が減ったため、工場に手伝いに。そして、20歳に届かないある日のこと、突然、野井戸に飛び込んで死んでしまった。
このような境遇は、北田少年が特別だったわけではない。彼と同じような若者たちは、同地域では珍しくなかったそうだ。前途への希望のなさ、生活への疲れ、早くから親の性行為を知ってしまう痛みなどと、自死の理由を推し量ることはできるが、手記が残っているわけではないのではっきりとはわからない。
●「残ったのは1人だけ」――地方から都会へ出てきた秀才たちの行く末
次は、瀬戸内海の島で生まれた少年の青春だ。大正12年(1923)、地元の小学校を卒業した1人の少年が、大阪の逓信講習所(郵便や通信を扱う逓信省の職員養成機関)に入学した。成績優秀にもかかわらず、家が貧しいため中学校へ進学できない少年をなんとか進学させたいと、小学校の先生が勧めた進路先だった。少年は、もし成績がふるわなかったら退学させられてしまうという恐怖で一時神経衰弱になるも、なんとか卒業し、大阪市内の二等局に配属された。
数年後、一緒に卒業した仲間のほとんどは、職場から消えていた。日給の安さと雑務の多さに耐え切れずに局の金を使い込んで警察へ引かれた者、血を吐いて郷里へ戻って死んだ者。またある者は、左翼運動で捕まったきり戻ってこなかった。少年は1人、働きながら師範学校の受験に合格し、局の外に出ることができた。しかし、彼にもまた重い病気が待っていた――。
実は、この少年とは宮本常一自身のこと。全七巻にわたる『日本残酷物語』の編集に際して、宮本は自身の残酷な青春もここにそっと収めたというわけだ。
畑中氏によると、『日本残酷物語』の刊行時期は、日米関係、沖縄、核など、現代に続く社会問題が表面化してきた時期に当たる。一般的には高度経済成長期といわれる頃だが、華やかな出来事の裏には残酷さも存在したのだ。経済成長の恩恵から取り残された人々や、新たに出現した社会問題に飲み込まれてしまった人々の辛さとシンクロしたのか、『日本残酷物語』は、刊行されるや否や、半年で20回以上増刷されるほどの売れ行きだったという。
『日本残酷物語』に綴られた人生は、今の私たちにとっても身近なものとして共感できる。今も昔も、日本は一度貧困に陥ってしまうと、這い上がるのが難しい社会だからだ。そんな残酷な世界を必死に生きなければならないのに、なぜ過去の記録研究を知る必要があるのか。それはきっと、今の苦しい環境を俯瞰するのに役立つからではないだろうか。特に、苦況の原因をすべて自分一人のせいにして、身動きが取れなくなっている人の、肩の荷がふと軽くなることを願う。
文=奥みんす