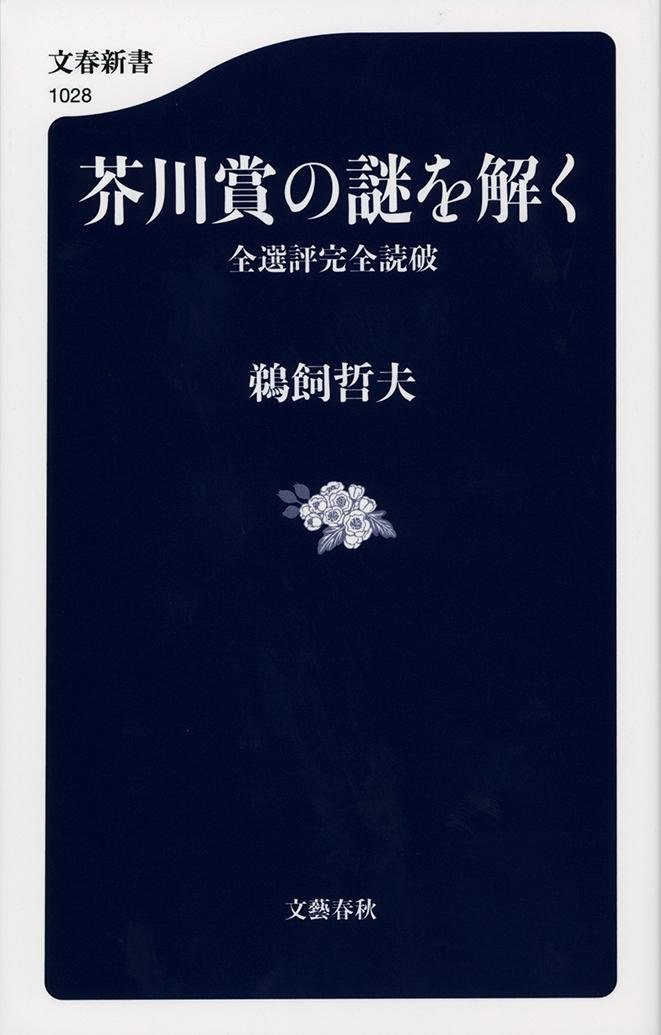太宰治が川端康成に逆ギレの真実は? 芥川賞の歴史を解く
更新日:2017/11/19
又吉直樹『火花』受賞で盛り上がる芥川賞。
この調子で純文学界が盛り上がることを期待したいところだが、そもそも芥川賞について詳しく知っている人はどれくらいいるのだろう。筆者の周りでも、「芥川賞はどこに応募するの?」と公募だと思っていた人や、「芥川賞と直木賞はどちらの権威が上?」と、芥川賞と直木賞の違いをわかっていない人がいた。
これまでの芥川賞の選評を全て読破した著者が書いた『芥川賞の謎を解く全選評完全読破』(鵜飼哲夫/文藝春秋)から、芥川賞の歴史を紐解いてみよう。
太宰治の落選ではじまった芥川賞
正式名称は芥川龍之介賞という芥川賞は、純文学の無名もしくは新進作家の創作に与えられる新人賞だ。芥川と学生時代からの友人であった作家の菊池寛が、芥川が亡くなり、彼の名前で新進の作家を発掘し、雑誌『文藝春秋』の賑やかしをはかろうとしたことがきっかけで作られた。
このできたばかりの芥川賞に固執したのは太宰治だ。太宰は第1回の候補に選ばれると友人に芥川賞を受賞する気満々の手紙を送っている。しかし、第1回芥川賞は『蒼氓』の石川達三が受賞。落選となった太宰だが、彼の芥川賞に対する執着はなかなか収まるもではない。「作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾みあった」という川端康成の選評に太宰が怒りをしめしたのである。
「“作者目下の生活に厭な雲ありて、云々。”事実、私は憤怒に燃えた。(中略)刺す。そうも思った。大悪党だと思った」とその年の『文藝通信』10月号に反論文を掲載した。
実際に、太宰の私生活は決して良いとはいえなかった。『人間失格』に書かれているように、女性との心中騒動や鎮痛剤として使用したパビナール中毒など厭な雲はあった。図星だったからこその逆ギレともいえる。刺すとまで言ってしまうのだから芥川賞への熱量は相当のものだったようだ。
その後の太宰は選考委員であり、太宰を支持した佐藤春夫の家に通い親しくなるとともに、芥川賞懇願の手紙を送っている。しかし、第2回は候補になることもなく、第3回には大悪党とまで罵った川端康成に宛てて、長さ4メートルに及ぶ芥川賞懇願の書簡を送りつけ芥川賞を切望するが、とうとう受賞できず願いが叶うことはなかった。
芥川賞だけが新人賞ではない
芥川賞をとらなかったからと言って、作家としての成功を断たれたわけではない。事実、太宰は知らない人がいないほどの文豪と言えるし、村上春樹、吉本ばなな、高橋源一郎、島田雅彦など、素晴らしい純文学の作家たちも芥川賞を逃している。
芥川賞と同じくらいの実力者を輩出する野間文学新人賞や、三島由紀夫賞など純文学の新人賞もあり、才能ある作家は評価される場所がきちんと設けられているため、現代では芥川賞だけに固執する必要もないともいえる。また、芥川賞を逃しても後に直木賞を受賞するパターンもある。やはり芥川賞は新人賞であるため、同時期にデビューした人や、時代によって評価が変わるなど運もあるといえよう。
石原慎太郎の『太陽の季節』が受賞し社会現象になったり、金原ひとみ『蛇にピアス』と綿矢りさ『蹴りたい背中』のダブル受賞で一気に芥川賞の最年少記録が塗り替えられ、話題になったりと、さまざまな出来事があった芥川賞。『火花』が第153回で受賞になるまでには長い歴史があった。
しかし、太宰治が起こしたその後も語り継がれる「芥川賞事件」があったからこそ、芥川賞の価値は高まり、今なお芥川賞は高く評価されると言っても過言ではない。
長い歴史のある芥川賞。ぜひこの機会に振り返ってみてはいかがだろうか。新しい純文学の世界が広がるかもしれない。
文=舟崎泉美