「悪い奴からは嫌われなければ、善人とは言えない」今こそ読み直したい革新の書『論語』
更新日:2017/11/16
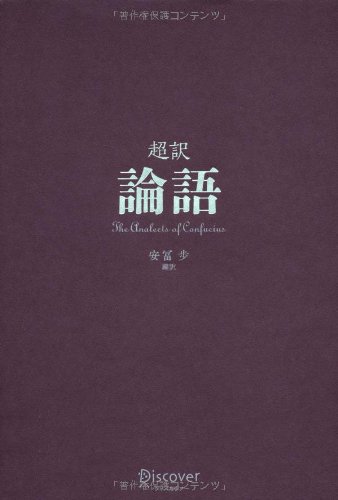
『論語』というと、古臭いイメージがあるかもしれない。学校の教科書などで習ったイメージだと「封建時代」「男尊女卑」「聖人君子」などの単語が連想されるだろうか。しかし、『論語』とは今もなお色褪せない、革新的な教えを説いている書である。
それは政治家が世の中を治めるための「制度」や「体系」としての思想ではなく、一個人の心の持ち方を説いている(その個人的な心の持ちようから、制度や政治の話に敷衍していくことはある)。
最初からお堅い話になってしまったが、『論語』は難しいことだけをつらつらと述べている書ではないことを分かっていただきたい。現代における自己啓発書のようなものだと考えても、あながち間違いではないかもしれない。
だが、原典をあたるのは、色々な壁があり、難しい。漢文の読み方により、様々な解釈が生まれるからだ。更に、数多く出版されている『論語』の解説本でさえ、初心者にはとっつきづらい部分がある。
そこで、現代人にも分かりやすいように訳されたのが『超訳 論語』(安冨歩編訳/ディスカヴァー・トゥエンティワン)である。
超訳とは、どういうことか。作者は述べる。
本書は、徹底して客観的たらんとしつつ、同時に、徹頭徹尾、主観的な書物である
作者は、作者なりの解釈を持ち、論語の原文に関して、その文章から与えられる「響き」を得た。その「響き」を本書にまとめてくれているのだ。裏を返せば、その「響き」は誰しも同じように感じるわけではないということ。筆者はその点に留意している。
論語について何かを誰かに言いたい、と考えたなら、必ず原文に当たり、本当に私が聞き取った響きが聞こえるかどうか、読者自ら確認してほしい。
著者の「響き」から導き出されたものを、「超訳」と称している。だが、そのように、誰かの思考を介した『論語』の方が、入門編としては案外読みやすいものだ。
よって、本書はとても分かりやすい『論語』の入門書といえる。
最初に、『論語』とはどんな思想なのか? という点を、まとめてくれているのもありがたい。『論語』とは「学習という概念を人間社会の秩序の基礎とする思想である」と著者は述べる。人には何かを学びたいという好奇心があり、外部から知識を得る。しかし「知っている」だけでは、取り入れた知識に振り回されていることに等しい。修練を重ねると、その知識が「自分のものになる」瞬間がある。主体性を得て知識を己の中に習得できた時、初めて「学習した」といえるのだ。
この、知識を得て我が物にする「学習」が、大切だと述べている。
その学習回路が開いている(ただ知識や情報を得て満足しているだけではない)状態が「仁」であり、それができる人が「君子」である。「君子」とは、「なんでもできる完璧な人」という意味ではない。
そう考えると、昨今のインターネットやSNSによる情報過多の状況は、安易に知識を得られるだけに、「学ぶ」ことまでできていない「知っている」だけの状態である。これは最も「君子」から遠のいているのではないだろうか……。
話を元に戻す。『論語』では「こだわること」を嫌うという。一つのことに固執して、意固地になっている状態は君子とはほど遠い。「学習回路が開いた君子は、状況に応じて自分を新しくしていくことができる。固定した機械などではない」そうだ。
本書は、その9割方が論語の名言集のようになっているので、自分のその時の気持ちに則したお気に入りの言葉を見つけることもできる。
「他人が自分を知(わか)ってくれない」なんてどうでもいいことだ。
「自分で自分を知(わか)ろうとしない」ことが問題なのだ。
世間の目ばかり気にしてしまう人にとって、心に響く言葉ではないだろうか。
その場の誰からも善人とされるような人こそは、徳を破壊する賊だ。誰からも善人とされるということは、何かを誤魔化しているからだ。悪い奴からは嫌われなければ、善人とは言えない。
これはなるほど、と感じた。「誰からも愛される人」というのは、自分を誤魔化している人なのだ。人から嫌われることを恐れている人にとって、どこかハッとするものがあるのではないだろうか。
上記はあくまで、個人的に「響いた」言葉だ。この響きも、年齢や気分、生活環境が異なれば違ってくるだろう。ゆえに、いつでも、何度でも開きたくなる、そんな本である。
文=雨野裾






















