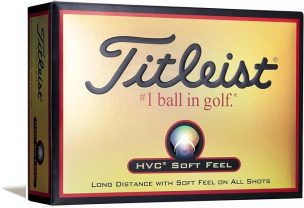マット・デイモン主演『オデッセイ』の原作を読む 火星にひとり取り残された男のサバイバル日誌
公開日:2016/2/13

『火星の人』(アンディ・ウィアー/早川書房)は、アメリカの作家アンディ・ウィアー氏の手によるSF小説だ。作家といっても、この作品を書いていた当時、彼は一介のアマチュアにすぎなかった。ところが、2009年に自らのブログで連載を始めると、予想以上の人気を博すことになる。熱心な読者がつき、彼らの後押しもあって2011年に電子出版したところ、いきなりSF部門で売上第5位を記録したのだ。2014年には日本でも発売され、第46回星雲賞海外部門を受賞する。そして極めつきは、リドリー・スコット監督、マット・デイモン主演による映画化だ(映画タイトルは『オデッセイ』)。全くの無名だった彼の作品が、なぜ、こんなにもとんとん拍子で評判を広めることができたのか? その秘密は、作品自身にあった。
本作のプロットは、「火星に取り残された男が救援を待ちながら生き抜く」という、突き詰めればそれだけの話にすぎない。しかし、シンプルであるが故に、面白さは一点に凝縮され、作品の味わいはきわめて濃厚だ。そして、その強烈な味の根源となっているのが、作者の無尽蔵な科学知識である。火星で暮らす主人公には、幾度となく絶体絶命の危機が訪れるが、それを持てる知識を駆使して乗り越えていく。この危機と回避のプロセスがアイディアに満ちていてめっぽう面白い。つまり、この作品は、何を楽しめばよいのかひと目で分かる単純明快さとサプライズに満ちた内容の濃さを両立させることで、読者の数を増やし、熱烈なファンを生み出していったのである。
物語は、アメリカの第3次調査隊が火星からの離脱を決定したところから始まる。1カ月の滞在予定が、猛烈な砂嵐に襲われ、わずか6日で撤回を余儀なくされたのだ。とこらが、離脱直前に植物学者のマーク・ワトニーが飛来してきたアンテナの直撃を受け、砂嵐の中に消えてしまう。船長以下5人のクルーは彼が死んだものと判断し、忸怩たる思いで火星を後にする。しかし、マークは奇跡的に生きていた。とはいうものの、状況は絶望的だ。地球に自身の生存を知らせるすべはなく、次の調査隊が火星を訪れるのは4年後である。しかも、火星基地の備蓄は1カ月の滞在を想定して用意されたものなので、水も酸素も食料も圧倒的に不足していた。しかし、マークはそこであきらめることなく、生存確率を高める方法を模索し始める。
火星にひとり取り残され、独力で生き延びる道を探さなくてはならない。下手をすれば、息苦しい展開の連続になりかねないこの作品を肩の凝らない娯楽作品にしているのが、主人公のユーモア精神だ。話の半ば以上は、主人公が書いている日誌を通して語られるが、これが実に軽い。死ぬか生きるかの瀬戸際でも決して必要以上に深刻ぶらず、くだらないギャグを言い続けることにこだわり続けるのだ。しかし、不真面目ともいえる彼の態度には、人間的なタフさが感じられる。これが生真面目な人間であったならば、きっと途中で心が折れていただろう。この作品を読むと、苦難の連続である人生を強く生きていくためには、ユーモア精神は必要不可欠であることが実感できる。
一方、主人公のサバイバル生活の裏側で描かれるのが、地球サイドの物語だ。マークが火星で生きていることが判明し、NASAは救出作戦を進めていくが、こちらでもさまざまな問題が発生する。このパートも力強いドラマに仕上がっており、なんとしてもマークを救いたいという想いがひしひしと伝わってくるのが感動的だ。
しかし、それでも、より魅力的なのは火星パートなのである。地球パートがあくまでも、セオリー通りのドラマであるのに対して、火星パートは、夾雑物を極限まで削ぎ落したシンプルなプロットの中に面白さが凝縮して詰まっているのだ。この濃厚さは、他作品ではなかなか味わえるものではない。SF好きにはもちろんのこと、SF小説初心者の方にもぜひ読んでもらいたい1冊である。
文=HM