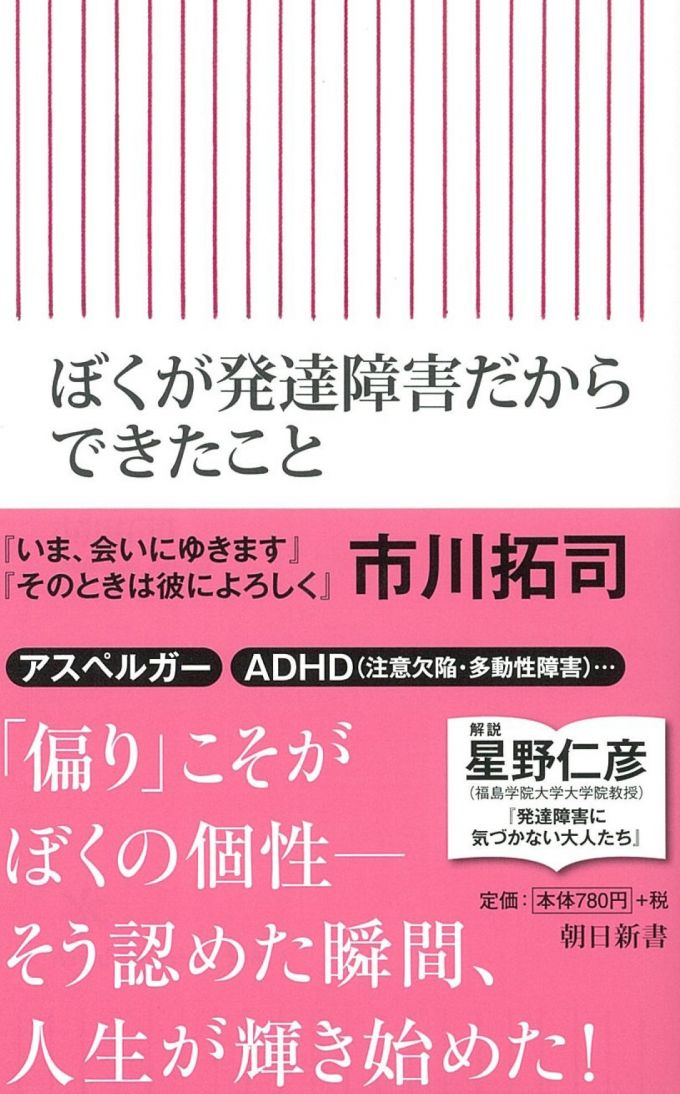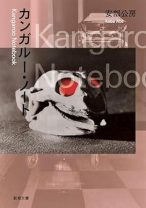障害がわかったとき、いっそすがすがしかった!『ぼくが発達障害だからできたこと』市川拓司インタビュー【前編】
更新日:2016/8/10
「発達障害者のサンプルを見せたい。僕がこの本を書いた最大の理由はそこにあります。レッテルやキャプションをつけるだけでは、ダメなんです。実際に生きて、動いて、しゃべっている、僕という発達障害者のサンプルのひとつを見せることによって、一般の人たちにビビッドなイメージを喚起してもらいたかった」
作家・市川拓司さんは『ぼくが発達障害だからできたこと』(朝日新聞出版)を著した理由をこう語る。映画化もされた『いま、会いにゆきます』『そのときは彼によろしく』(ともに小学館)などで知られるベストセラー作家と障害とは、すぐに結びつかないかもしれない。が、巻末に収録された福島学院大学大学院教授・星野仁彦医師による市川さんの精神医学的診断は、「注意欠陥・多動性障害(ADHD)とアスペルガーにほとんど該当」するというもの。
市川さん自身が、自身のパーソナリティが“障害”といわれるレベルに傾いていることを知ったのは、いまから10年ほど前のこと。そのときの感想は「なあんだ」だった。ずっと「困った子ども」で「間違っている生徒」で、作家になる以前に勤めていた会社でも問題行動ばかり起こし、同僚から「勘弁してよ」といわれるのが常だった。その根っこに障害があるとわかったとき、市川さんは「いっそすがすがしい」と感じたという。市川さんが自身を冷静に観察し、奇妙な行動の理由を探り、小説を書くようにその意味を想像(もしくは創造)して書き下ろした1冊は、“障害カミングアウト本”特有の重さがなく、全篇通して穏やかで、あたたかい。
自分が特殊だという意識はなかった
市川拓司さん(以下、市川)「社会は発達障害に対して、どこか悲壮感みたいなものを求めていますよね。本書にはそうしたネガティブ要素がないので、違和感を覚える方も多いと思いますが、僕にとっての現実はこんなモンなんです(笑)。子どものころ、教師から『私の教師生活30年で一番手がかかる子』といわれましたが、毎日がアメリカのおバカ番組『ジャッカス』みたいで、ケタ外れのことをする僕をクラスのみんなは『面白い、面白い』といってくれました。唯一、世間でいわれる発達障害っぽいエピソードが集中しているのは、中学時代ですね。引っ越して小学校とは違う地域の学校に通うことになったせいもあって、クラブになじめず、村八分に遭って、抑圧されていました。でも高校に行ったら、僕と同じような生徒がたくさんいて、それ以降は自分が特殊だという意識を持たずにこられました」
市川さんの話は終始、よどみなく、そして途切れない。幼少期から多弁だったのも、発達障害ゆえ。授業中でも、相槌を打たれなくても、とにかくしゃべるしゃべる。おかげで、市川さんのいるクラスは学級崩壊状態だった。
市川「当時はまだ発達障害が知られていなかったし、自分にも親にも障害という意識がなかったから一般学級に通っていましたが、いまだったら特殊学級に振り分けられていたでしょうね。そしたら、運命が変わっていたかもしれません。知らなかったからこそ、しれっと、するっと大人になれた。当時は大らかな時代で、僕みたいな子どもに『バカ』というあだ名をつけても許される雰囲気がありました。差別はもちろんあってはならないことですが、差別に対して過剰反応するのも何か違う気がします。差別が排斥になり、社会そのものがやせ細っていく。いまのように腫れ物に触るような感じで扱われるほうが傷つく子どももいるでしょう」
発達障害だからこその、市川ワールド
本書で市川さんは、自身の特性を「障害と考えずに、個性とみなしたらどうなんだろう?」と考察している。障害を障害たらしめているのは環境で、別の環境においてはそれが障害どころか生きていくための武器になる。
市川「発達障害は、つまるところ適応障害です。これは作家的想像なのですが、僕らは農耕がはじまる以前の人間の原型みたいなもので、もともとはみんなこうだったんです。たとえば僕は、直感だけは人一倍あります。データベース能力はニワトリ並みで、買い物リストを三つ以上覚えられない。四つめが出てきた瞬間、一つめを忘れちゃう。その一方で、世の中の森羅万象を目にしたときにそれをパターン化する能力は突出しています。それは古くは、風の音とにおいをキャッチして、『あ、この方角に虎がいるな。逃げなきゃ』と判断するときに使われていた直感力なんです。もっというと、僕は自分のことを人間以前のサル、しかもテナガザルではないかと思っています。だからこんなにも自然が好きだし、家族を大切にするし、争いを好まないんです」
それは、市川さんが書く小説の世界観にもつながる。
市川「そもそも、僕が作家になったのも発達障害だから。つらい時期が続いていたときに、自己治癒のために執筆をはじめました。センチメンタリズムとロマンチシズム全開の小説は、弱り切っていた当時の僕によく効きました。それがちょうど時代の流れとマッチしたんです。『いま、会いにゆきます』を書いた当時は、韓流ドラマブームがあり、『世界の中心で、愛をさけぶ』(片山恭一/小学館)がヒットし、ロマン主義の流れがありました」
いまや、神話的でロマン主義に彩られた市川ワールドは世界中で愛されている。取材当日も、『VOICE』(アルファポリス)がベトナムで発売され、市川さんのSNSは多くのファンからの祝福コメントで賑わっていた。
見えている世界を自動書記している
市川「発達障害を持った作家は少なくないといわれますが、たいていはSFやミステリーのジャンルで活躍されています。対人関係を苦手とする発達障害者が、恋愛小説を書くなんて異例中の異例だそうです。僕は発達障害者としてもアウトサイダーだけど、作家としてもアウトサイダー。僕みたいにとっちらかった人間が作家になるのはめずらしいと、作家デビューしてから知りました」
本書では作家にかぎらず、歴史に名を残す「アスペルガーの芸術家」に共通して見られる傾向についても、独自の論が展開されている。
市川「僕らのような人間は、視覚に偏る傾向があります。女性の服ひとつ描写するにしてもフレアスカートのふくらみから、そこに施されたレース、レースひとつひとつの網、さらにはその繊維まで見えている。そこまで見えてはじめて書くんですよ。それをディテールまでとことん書き込むか省略するかは、作家次第。僕はせっかちだからストーリーを先に進ませたいし、情緒をより重視したいのであまり書き込みません。作曲家も映画監督も漫画家も、見えている人が作ったものとそうでない人が作ったものとはすぐに区別がつきますよ」
本書のタイトルどおり、市川さんには「発達障害だからできたこと」が多くある。しかし世の中には発達障害であることで生きづらさを抱えている人のほうが、むしろ多い。生きづらさから「擬似発達障害」になる若者も増えていると市川さんは指摘する。なぜそんな現象が起こっているのか? 後篇に続く。
取材・文=三浦ゆえ
【後編】につづく/8月10日(水)11:00更新予定