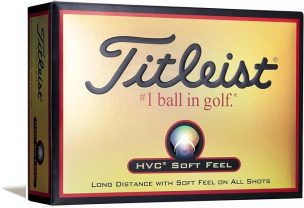人類の発展の裏には人体実験あり。医学や化学のために体を張った笑いと涙の人体実験エピソード集
公開日:2016/12/26
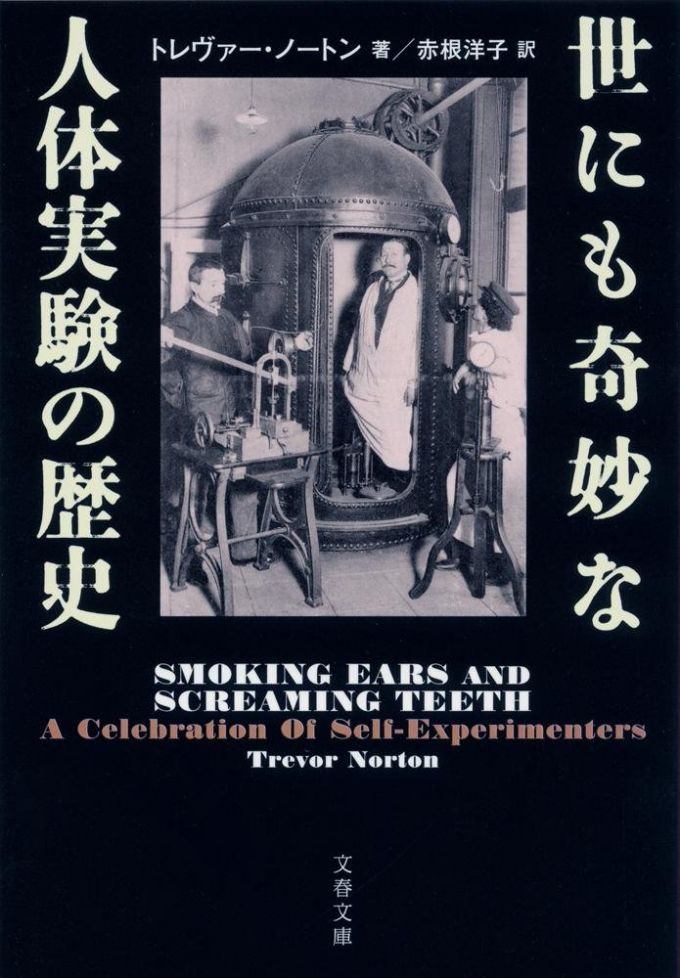
ウニやナマコのような見た目がグロテスクな生き物を最初に食べたのは誰だったのだろう? 今では知る由もないが、おかげで我々は今日もお寿司屋さんで美味しく軍艦巻きを食べることができる。食べ物に限らず、体を張って未知の領域に挑んだ偉大な先人がいたからこそ、文明が発達を遂げることができたのは間違いない。
しかし、それは言い換えれば紛れもなく「人体実験」である。つまり人間社会は人体実験によって支えられてきたし、今もその風習は続いているのだ。晴れて文庫化された『世にも奇妙な人体実験の歴史』(文藝春秋)を読めば、笑いあり涙ありの人体実験の歴史から目が離せなくなるだろう。
著者のトレヴァー・ノートンはリヴァプール大学名誉教授という堂々たる肩書きを持っていながら、過去の科学者たちが行ってきた人体実験を自らも実践してきた型破りな人物である。異常なまでに人体実験に関心を抱くノートン名誉教授は、長年にわたって幅広い分野の人体実験の歴史を研究してきた。本書はそれらをまとめた一冊だ。
しかし、昔の学者とはこんなにも無謀かつ大胆だったのかと驚かされる。たとえば、十八世紀のイギリスではハンター兄弟が医学のために過激な人体実験を繰り返していた。中でも衝撃的なのが「淋病と梅毒は進行段階が異なる同一疾患である」という学説を証明するために、自らの性器に淋病患者の膿をなすりつけた実験である。実験結果としてハンターは梅毒に感染するが、「淋病患者が梅毒にも感染している」という可能性もあったため、この実験は最初から無意味だった。ハンターはならなくてもいい梅毒に苦しめられることとなる。
外科手術では欠かせない麻酔もまた、大勢の犠牲のうえに安全が証明された代物である。人間の意識を奪うクロロホルムは麻酔に使われるようになってからも適量が見極められずに、しばらくは手術ではなくクロロホルム中毒で死亡する患者が続出した。精神医学界の権威、フロイトは興奮剤と媚薬としての効果を試すため、自らコカインを使用しているうちにコカイン中毒へと陥った。1886年、コカインを脊髄注射して痛覚を麻痺させる実験がドイツ人外科医アウグスト・ビールによって行われたが、助手に対する数々の行為は読むだけで痛々しい。
(前略)足の裏を羽でくすぐり、皮膚をピンセットでつまみ、ランセット(穿刺器具)を太股に骨まで突き刺し、陰毛をむしりとり、火のついた煙草を皮膚の上でもみ消し、向こうずねを重いハンマーで思い切り殴り、最後は睾丸を激しく押しつぶしたり引っ張ったりした。
もはや助手に個人的な恨みでもあるかのような暴れぶりである。
グルメについての章も興味深い。日本人読者からすると面白いのは、昆虫や毒キノコなどのエピソードに紛れてフグが取り上げられていることだ。体に致死量の毒を持つフグを食べる日本人は、欧米人の観点からいえば人体実験を行っているようなものなのだろう。
ノートン名誉教授の文章はときどき先人を茶化している部分もあるが、むしろ誇らしく紹介しているような姿勢のほうが強く感じられる。同じ学問の徒として、人体実験に身を捧げた人々への敬意を忘れていないからだ。特にワクチンや医薬品は実用化に当たって臨床試験が不可欠である。そして、現代でもごく稀に臨床試験の失敗により、被験者が生命の危険に晒される事故が起こっている。放射能を発見したマリーとピエールのキュリー夫妻は世界中から賞賛を受けノーベル賞も受賞したが、放射能の影響で健康に大きく支障をきたした。ピエールはラジウムが放射線源であると証明するために自らの腕に貼り付けさえしていた。
ノートン名誉教授はあとがきの最後をこう締める。
この利己的な世界の中で、社会はこのような人々を必要としている。彼らを誉め称えようではないか。
時にはマッド・サイエンティストと蔑まれようと、学者たちの挑戦と多くの犠牲が我々の平和を築いている。彼らに複雑な感謝を贈りたくなる本だ。
文=石塚就一