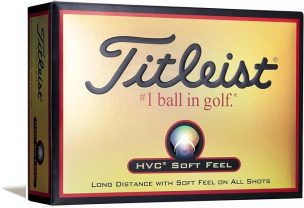突然の余命宣告、あなたはどうしますか?『最後の秘境 東京藝大』の著者が送る渾身の医療ドラマ
更新日:2017/11/12

人はいつ死ぬかわからない。もし突然、自分が不治の病に冒され、「あなたの余命は半年です」と医師から宣告されたら? 「完治する奇跡を信じて、病魔と闘う」か、それとも、「死を受け入れ、残された時間を大切に生きようとする」か。
昨年、その徹底した取材で話題となった『最後の秘境 東京藝大―天才たちのカオスな日常―』。その著者が送る書き下ろし小説『最後の医者は桜を見上げて君を想う』(二宮敦人/TOブックス)は、対立する2人の若き医師を通し、死に対して人はどうあるべきかを問う医療ドラマだ。
地域の基幹病院として機能する〈武蔵野七十字病院〉。若くしてその副院長となり、「天才」との呼び声も高い外科の医師、福原雅和。彼は患者と共に常に全力で病魔に立ち向かうことこそが医師の役割だと信じている。患者に寄り添うためならば、忙しいさなか千羽鶴を折ってやることさえいとわない。徹底的に死と闘う。
〈「人はどうしてこんなものに頼るのかな」〉―千羽鶴を前にして冷たくこう言い放つのは、武蔵野七十字病院皮膚科の医師、桐子修司だ。桐子は福原と違い、“患者には死を選ぶ権利がある”が信念。がんで余命半年の患者とその家族を前にして、〈「どう死にたいですか?」〉などとのたまう。おかげで、付いたあだ名は〈「死神」〉。冷静に死を迎え入れようとする。
熱血漢の福原と、クールな〈「死神」〉桐子。2人の医師の対立を、「いかなる神業で不治の病に罹患した患者を救うか」ではなく、「避けられない死を前にし、医師としてどうあるべきか」で描いているところがこの作品の魅力だ。そもそも各章のタイトルが「とある会社員の死」「とある大学生の死」とあるように、登場人物が死ぬことは読者にあらかじめ提示されている。
ある日突然、白血病と診断された会社員。3ヶ月も前から念入りに準備してきたプレゼンの機会を奪われたどころか、退職までさせられてしまう。入院を余儀なくされ、強力な抗がん剤を投与され、止まらない吐き気と下痢、脱毛、口内炎に苦しめられる。
筋萎縮性側索硬化(通称ALS)に冒された大学1年生。3浪の末に念願の医学部に合格を果たしたにもかかわらず、退学を余儀なくされる。全身の筋力が次第に低下していく難病のせいで、希望に満ち溢れた未来をすべて奪われる。
どんなに辛く苦しい思いをして治療を頑張っても、死は避けられない。ただ〈生きる〉という、これまで簡単に出来ていたことを奪われ絶望する患者を前に、自分たちの主義主張をめぐって対立する福原と桐子。
フィクションであるとわかっていても、自分と重ね合わせて読まずにはいられない。病室の様子、医療スタッフとの会話、治療の苦しみ。大好物のバニラアイスを食べても、油の塊にしか思えない感覚。こういったリアルな描写を読むうちに、いつの間にか読者自身も“死”と対峙している。自分や家族や大切な人たちがもし、同じような状態になったら? 福原vs.桐子、どちらを正しいと思うだろうか。
いや、これは単純な勝負の問題ではないし、正解もない。患者が死の淵からよみがえるような奇跡は起こらないけれど、作者は最後に小さな救いを二人の医師に残す。それは読者にとっての希望でもあるのだ。
文=林亮子