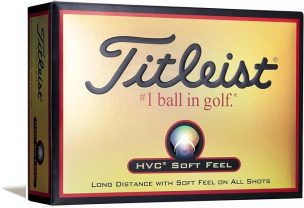憧れだけど、近くて遠い…なぜ日本人はきものを着なくなったのか?
公開日:2017/3/18

今この国で、日常的にきものを着ている人はどれくらいいるのだろう。かつてきものは、今のファストファッション感覚で着られる普段着だった。少なくとも第二次世界大戦前までは、ほとんどの庶民がきもので生活していたのだ。しかし現在は? 茶道や日本舞踊など伝統文化や伝統芸能に関わっている人でもない限り、毎日のようにきものを着る人なんてほとんどいないのではないだろうか。
多分それは、私たちの多くが「きものを面倒くさいものだ」と考えているからだろう。着付けを覚えるも大変だし、着用ルールも細かすぎる。しかも1枚1枚の値段が洋服に比べてずっと高い(ことが多い)。ほんの数十年前までは、多くの日本人にとってきものは身近な存在だったはずなのに。いつのまにこんな、ハードルの高いものになってしまったのだろうか。
その謎を解いてくれるであろう1冊が本書、『きもの文化と日本(日経プレミアシリーズ)』(伊藤元重、矢嶋孝敏/日本経済新聞出版社)である。経済学者・伊藤元重と、きもの販売会社の社長・矢嶋孝敏。異分野のプロフェッショナル同士がきものの過去・現在・未来について語り合う。自由で、伸びやかな語り口が魅力の対談集だ。
2人に共通しているのは、既存のきもの業界への危機感だ。洋服が普段着として普及し始めた頃、きものはフォーマル化を図ることで生き延びようとしてしまった。数が売れなくなる分、一着売れたときの儲けを多くしようとしたのだ。こうして1枚のきものに多額のマージンがのることに。実際の原価に比べて、相当高い値段で売られるようになったのだ。
さらにフォーマルな場で着る服には、それなりの着用ルールが必要になる。こうして、帯はこれを選ばないとダメなど、きもののルールはどんどん複雑になっていった。ルールが難解になればなるほど、我々消費者は呉服屋さんの知識をあてにするしかなくなる。いくら高い商品だと思っても、「それが伝統だから」とか、「決まりごとだから」と言われてしまえば仕方がない。我々には呉服屋さんの言うなりに、結婚式などに着ていくために高級なきものを買わされ、――そして結局、着なくなってしまう。
値段が高すぎる、着方のルールが難しい。一度きものについてしまった負のイメージは簡単には消えない。その結果きものを着る人口は減り続け、きもの業界全体が縮んでいってしまった。
ただ著者のうち、矢嶋氏は当の業界人、きもの販売会社「やまと」の社長である。当然このままでいいとは考えてはいない。若者でも購入しやすい価格帯の商品の開発、生産者の保護など、革新的な取り組みを行ってきた。ちなみに花火大会の服装として浴衣が定番化したのも彼の功績が大きいらしい。
「きものはアパレル化するべきだ」と矢嶋氏は言う。糸から手作りするような高級品がある一方で、カジュアルに楽しめるものがあってもいい。きものの在り方が多様化すれば、その分多くの消費者が着物を手に取れるようになる。それが結局は「きもの」という文化の担い手を増やし、その伝統を次世代に伝えていくことにつながるのだ。
きものは洋服のようにはなれない。機能性はないし、生産過程で職人の手仕事が必要になるのでどうしてもファストファッションより高価なものになってしまう。しかしその代わり、きものには物語がある。それは四季を味わう心や洋服にはない非日常感だったり、あるいは生産者側のストーリー、きものそのものが持つ伝統の魅力というものだったりする。価格帯と分かりにくさ、この2つのハードルを下げることができれば、きものにはまだ未来がある。そういった確信があるからこそ、著者たちはきもの復活への希望を捨てないのだ。
文=遠野莉子