かつて中2だったすべての人に。あの頃が甦る痛みの物語
公開日:2013/9/7
オーダーメイド殺人クラブ
| ハード : Windows/Mac/iPhone/iPad/Android/Reader | 発売元 : 集英社 |
| ジャンル:小説・エッセイ | 購入元:紀伊國屋書店Kinoppy |
| 著者名:辻村深月 | 価格:1,337円 |
※最新の価格はストアでご確認ください。 |
自我と自意識に雁字搦めになっている思春期まっただ中の中学2年生。まるでそんな年頃のような言動を、いい年してやってしまうようなことが<中二病>と言われるようになったのはいつ頃だったか。けれど大人になってからやるから痛々しいのであって、まごうかたなき中2なら、それは普通のこと。けれどそれが普通だったことを、私たちは忘れている。いや、なかったことにしている。自分にとってそんなものは、なかったと。
主人公の小林アンは中学2年生。クラスで仲のいいのは芹香と倖。けれどある日突然に、このふたりから無視されるようになってしまう。ちょっと前までは芹香とふたりで倖を無視していたのに──。クラスの中のヒエラルキーに辟易し、家庭では少女趣味な母親にうんざりしていたアンは、ある日、母親と決定的なケンカをして家を飛び出す。そこで偶然出会ったクラスメート・徳川勝利にこう頼むのだ。「あたしを殺してくれない?」
ふたりはクラスでこそまったく交流を持たない(属するカーストが違うのだという)が、実は近い趣味を持っていた。死、あるいは死体への憧憬。ふたりは「人々の記憶に残り、いつまでも語り継がれるような死」を小林アンの体を使って演出することに情熱を燃やす。その過程でほとばしるアンの思いが痛い。「誰もみんな、センスがない。私を理解しない。誰も、誰も、誰も。」「世間に溢れる、死ぬつもりのないリストカッターの一人のように自分がなるのは嫌だ。あの人たちと、私は違う。あんな、自分の病や意識に溺れるようなこと、しない」「どうしようもなく、くだらないリアル。それが私の現実なら、そんなものいらない。つぶれてしまえ」
学校と家庭。それが人生のすべてだったあの頃。私たちは一段高いところからアンを見下ろしながら思う。「痛いなあ、自意識の固まりだなあ、自分が特別な存在だって思いたがるよねこの年頃って」──けれど自分もそうだったのだ。蓋をしてそんなものはなかったふりをしているけど、肥大した自我を持て余すことのない中2なんていない。クラスの上位にいようと目立たない子だろうと、クラスという名のカーストで自分の立ち位置を意識しない子なんていない。
アンの痛さは自分の痛さだ。徳川の背伸びは自分の痛さだ。芹香の策略は自分の痛さだ。そんなもの自分にはなかったふりをしながら、でも心に刻まれている記憶は彼らの痛さを自分の痛みとして受け止める。読んでいて、ときおり恥ずかしくなる。そこには自分がいるから。自分の足掻きが見えるから。同時に応援したくなる。我慢しろ、生きろ、大丈夫になる日が来るから、と。
私たちは何歳になっても、心の中に中2を住まわせている。それがあぶり出される。馬鹿で、痛々しくて、自分のことで頭がいっぱいで、思い出すと恥ずかしいばかりの中2。けれどその時期を通り過ぎたからこそ今の自分があるのだと、自分の中の中2が(苦笑しつつも)愛おしく思えてきた。残酷で痛々しいモチーフにして、読後感は驚くほど清々しい。
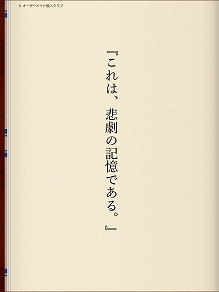
印象的な一言で始まる
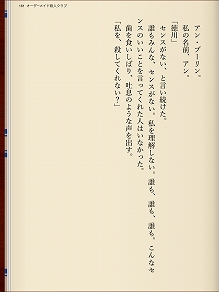
アンが徳川に「私を、殺してくれない?」と頼む場面とそこに至る過程は前半のクライマックス























