作中作が現実に次第に浸透する風味を味あわせるミステリー
更新日:2014/6/3
忌館 ― ホラー作家の棲む家
| ハード : Windows/Mac/iPhone/iPad/Android/Reader | 発売元 : 講談社 |
| ジャンル:小説・エッセイ | 購入元:紀伊國屋書店Kinoppy |
| 著者名:三津田信三 | 価格:648円 |
※最新の価格はストアでご確認ください。 |
ミステリーのさまざまなえり分けの中に、「館もの」というのがあることはファンなら誰でも知っている。
日本の風土には似合わぬ、石と鋼で構築された古色蒼然たる広壮な館の中で、閉じこもったように生活する一族が、次々と凄惨な連続殺人に見舞われるのがこの手のミステリのならわしだ。
「館もの」の最大傑作は、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』をして国内外の最高位を疑えまいが、ただしアンチ・ミステリを前提として読んだ場合に限るのであって、丸腰のまま本格ミステリとして取りかかったならばこれほどばかげた最低推理小説もないところが、ますますおもしろいわけであり、そう考えると「館もの」なんてしょせんは大人のからくり遊びの一種なのではないかなんて興ざめなことすら思ってしまう。
だからといって「館もの」が決してつまらないわけではない。むしろ、論理ゲームとしてこれほどおもしろいものはない。それは、西洋趣味の屋敷というのが密室性の極めて高い緊迫感のある構造を持っているからという理由もあるが、小説の中では惨劇の場となるこれらの建物が必ず鬱蒼たる林野のただ中、あるいは樹木に囲まれた庭園に位置されているからだ。あまり戸越銀座のコロッケ屋の隣という場合はない。つまりそれが東洋であろうと西洋であろうと、市井の生活の息吹から逃れた、「雰囲気」だけの空間において怪しい見立て殺人や絶対不可能な密室事件がきびすを接するごとくに勃発する。その雰囲気が無限に濃縮してみせるエキゾチシズムと殺人者の忌まわしい呪詛は、いってしまえば「知的アトラクション」なのだ。浦安の某テーマパークにあるたとえば「ホーンテッドマンション」、あれの小説版だ。
ということで、「館ものミステリー」のステップを見事に踏み仰せてくれる「忌館」も、大変楽しい。
小説の組み立ては少し複雑にできている。まず主人公の名前が作者と同じ三津田信三だ。私小説的な、作者の身の回りに起きた実際の事件めいた書きぶりをまず読者に味あわせる。編集者をしながら小説も書き進める「私」だが、ある日、自分をいつわって文学賞に応募したものがいることを知らされる。一方ミステリーの同人誌から連載を依頼されだ「私」は、東京郊外に廃屋のようになった西洋館を見つけて移り住み、連載小説の執筆に取りかかる。以後「私」の生活と、書き進める作品とが交互に並べられていくのだが、館にまつわるむごたらしい一家惨殺事件の風聞が浮かび上がってくるにつれて、現実と作品が次第に連携してゆき、うつつと虚構の混交が始まる。三津田信三の日常は次第に非日常的な様相を呈してくる。
たぶん試みられているのは、ホラーとミステリの融合のようなことだろう。過去の殺人者が100年ほどを経て現代の「私」に迫ってくるあたりは、スティーヴン・キングの書きぶりを換骨しようとしているとみられる。それはある程度成功しているのではないか。理由なき殺人者のスピリットが一人の青年に具体化して「私」と「私」の作品に描かれる少年に迫ってくるプロットは怖い。
ただ、犯人が犯人だけに、犯行の動機やプロセスが現実の中に取り出されて、断罪されることがない。幽霊は捕まえられないからだ。このあたりのうまさがキングとちょっと違うのだけが残念なところではある。
乱歩の偽作「梔子姫」を作中作に仕込みながら、だんだんと幻想の世界に現実が侵されていく久世光彦の「一九三四年冬―乱歩」を合わせて読みたい。
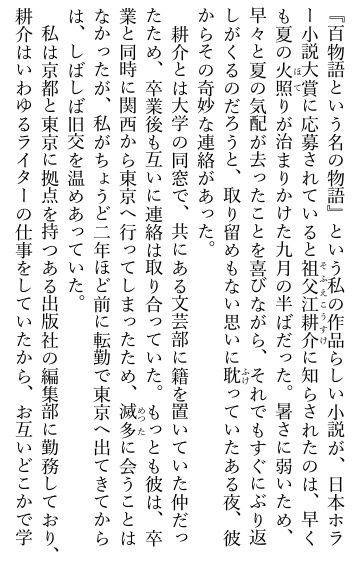
書き出しから一気に物語の中心へ入る
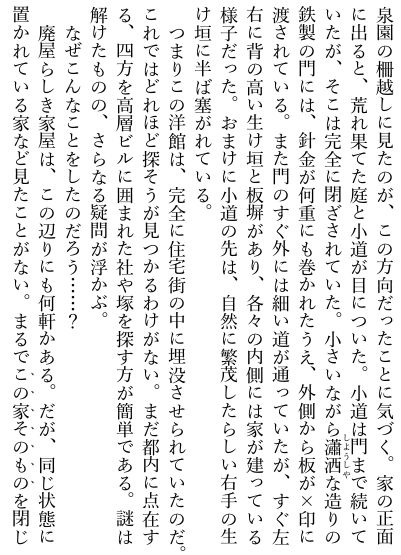
書き出しから一気に物語の中心へ入る
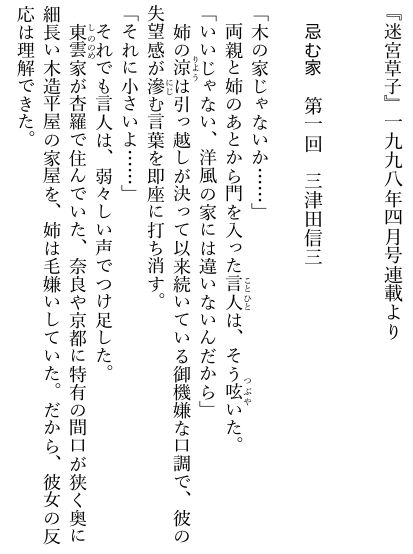
作中作と「私」の生活が交互に描かれていく


























