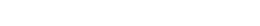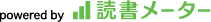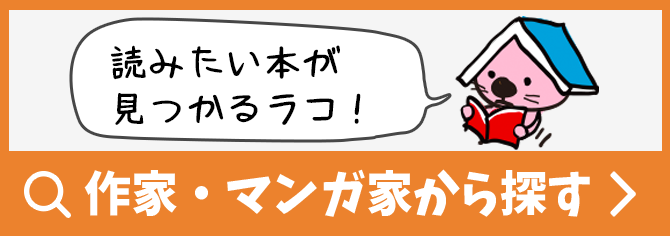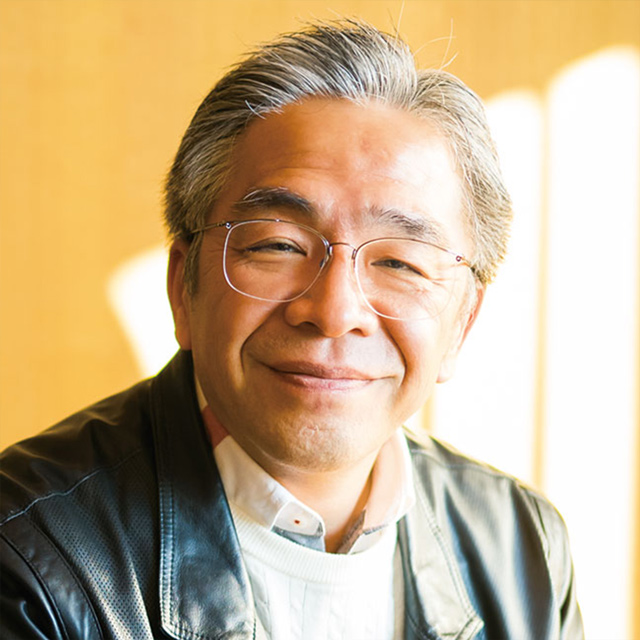とどめの一撃 (岩波文庫 赤 598-1)
とどめの一撃 (岩波文庫 赤 598-1) / 感想・レビュー
U
好きになった男性に、身を捧げようとするソフィー。そのソフィーの愛を、かたくなに拒むエリック。物語は、エリックひとり語りの回想で進みます。エリックの、ソフィーに対する辛辣極まりない思いに、彼の人間性を疑いそうになるも、静かに受け入れるわたしがいました。彼女へのとどめの一撃は、彼にとってもとどめの一撃。いや、それ以上ではなかったか。最終的には、形勢が逆転したように感じました。この作品、今のタイミングでよめてよかったかも。序文、素晴らしいです。後ろの解説を先によんでから本編をよむと、入り込めたのでおすすめです。
2016/02/04
藤月はな(灯れ松明の火)
自尊心の高い女は得てして自分に興味がなく、思想に凝り固まり、真っ向から自尊心と敵対する男に興味を持つ。そしてこの物語ではソフィーの弟であり、エリックの唯一、愛する人でもあったがために二人を結びつけたコンラートの存在感は全くないと言っても等しい。なぜならば、この物語は自尊心が互いに高かったために孤独にならざるを得なかった男女の一方通行の激情が棘のように抜けない執着へと変わる愛の復讐でもあるからだ。気高くも自分を貶めざるを得なかった自分を恥じながら執着するソフィーの姿は一旦、眼を背けたくなる女の性を描き出す。
2013/09/11
harass
ユルスナールの小説。愛憎劇を振り返る生き残った者の告白。回想として主人公のローモンが語る。癖があり読みにくいのだが、この独特の距離感のある文体は非常に面白い。語り手の猛烈な自責の念を端々ににじませている。解説にあるが表現などにリルケの影響があるのだという。「私のまえにあるのはもはや、筋肉を張りつめ、震えを抑えようとしてひきつっている顔にすぎなかった。彼女は一挙に軽業師の、あるいは、殉教者の美しさを見せた。少女は腰をひとひねりして、希望もなければ留保も問題もない愛という、ごく狭い舞台に跳び乗ったのだった。」
2014/10/28
みつ
初めてのユルスナール。なかなか頭にはいらない一冊。舞台はロシア帝国の領土であったバルト海沿岸の国ラトビア。第一次世界大戦の時代。ロシア革命が重なりボリュシェビキと反対派の戦争状態が状況を複雑に。主な登場人物は3人に限られる、と解説にあるが、「冷淡さと拒否という」(p51)特質を持った語り手の眼を通したソフィーの振る舞いが他を圧倒する。「男に生まれ損なったこの娘は、悲劇の女主人公のように」(p72)戦争と混乱と狂熱の時代に自らの運命を選びとる。衝撃的であるはずの終結部は、語り手の回想の中に静かに沈んでゆく。
2022/10/10
kthyk
エリックとソフィーの恋、これは二人が共に四つか五つ、様々のことばを使っての恋愛劇だったのだろうか。著者は序で「作者による解説を排除し、主人公の口から語られる手法を採用」したとある。二人は共に各々の生を直視し、エリックは誠実に説明しようとし続ける。それはある種の高貴さ、一人の人間の持つ、どうにもならない人間そのものを呈示する。ポリシェビキ革命時のバルト海沿岸ラトビアの首都リビア近郊、四カ月間の古い城館を舞台とした灰色の日々の悲劇。中篇だが一気読みの短篇。しかし、何処かが絶えずヒリヒリする読み応えがある作品。
2022/11/15
感想・レビューをもっと見る