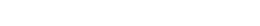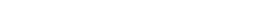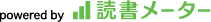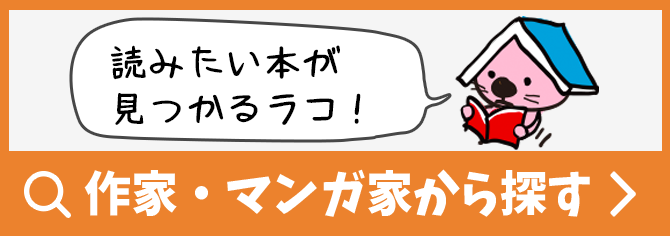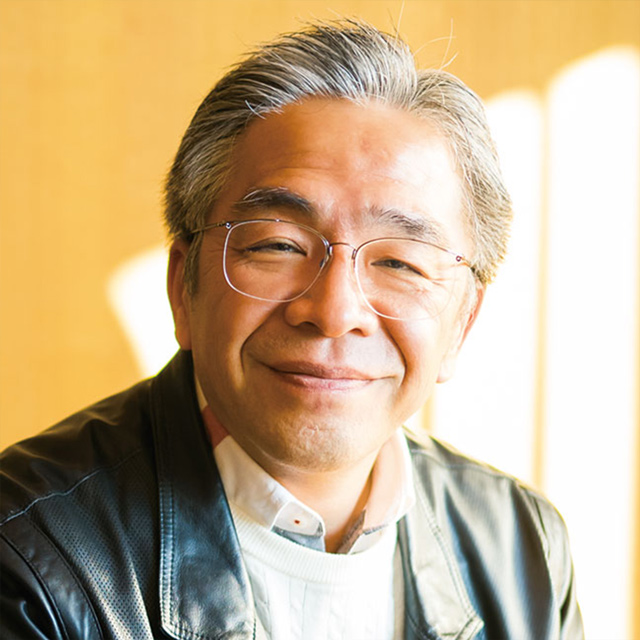死の講義
死の講義 / 感想・レビュー
trazom
「死の講義」と言うより、西洋の一神教、インドの宗教(バラモン、ヒンドゥー、仏教)、中国の思想(儒教、道教)、日本の死生観(神話、神道、念仏宗、禅宗、法華宗、江戸儒学、国学)を、「死」を切り口に解説したという一冊。各思想を余りにも単純化しすぎという懸念はあるが、「中学生でも読めるように、わかりやすく書く」という宣言通りの丁寧な記述である。死に無頓着な儒教、地獄を意識する道教、黄泉の国の国学、永遠の命の一神教、輪廻のヒンドゥー教など、選り取り見取りの死生観を紹介した上で、橋爪先生の結論は「自分で決めなさい」。
2020/11/26
禿童子
「死」に対する見解の分類を介して、無神論、一神教、多神教、儒教、仏教、神道など、各宗教の死後の見方を明快に説明する。中学生にもわかる平易な説明を心がけたというが、人生経験のある人でないと読みこなせないのでは。とはいえ、合理主義の穴である「偶然」を宗教が対象にしているという論の立て方はうまい。国学を、儒学の方法論による神道の再構成とするのは橋爪ならではの卓見。忠孝一如、生死の超越など日本独特の観念も取り上げている。ただ、パターン分けしたことで各派の宗教感情がやや平板に見えるのが気になる。
2023/11/29
こまり
いつだったか、新聞で紹介されていて面白そうと思い読んでみた。他者の死は経験できるが、自分自身は死を経験することは出来ない。経験した途端に存在しなくなるのだから。「死は必ず生きている途中でやってくる。でもそれが、終わりである。途中なのに終わり。……これに立ち向かうには、いつ終わってもいいように生きる、これしかない。」本当にそう思う。でも、そんな覚悟もないまま日々を生きているなぁ。そして急に終わりになるのかなぁ。命って何だろう。宇宙の不思議を感じる。
2023/03/06
テツ
人は絶対に死というイベントを体験することはできない。かろうじて触れられるのは他者の死であり、他者が死んだ後にも変わりなく続いていくこの世界だけだ。だからこそ世界各国の宗教は死について様々に説明しようとしてきた。死について説くこと。それにより苦しみと不安を和らげることは、かけがえのない生を見つめ直し、考え直し、より良く生きることに繋がる。しっかりと自分なりに考え抜いて、死と向き合い続けてきた先人たちの発明の中から好きなものを選ぶといい。それがあなたにとっての死の在り方だ。そしてそこから生の在り方も見つかる。
2021/01/13
ま
死とは何かについての考え方のカタログ。昔、「自分の死は自分で認識できないのであるから自分が死ぬことはない」って考え方を聞いて感心した記憶がある。人間は、死とは何かを本能より高い次元で認識できる(できてしまう)生き物。それゆえに、死とは何かについて古代より思考をめぐらし、その恐怖から逃れんとしてきたのだろう。逆に、自分の死を自分で認識できない以上、副題のように死とは何かを自分で自由に決められるということでもある。シンプルな文体でわかりやすいが、多分もう一回読まないと理解できないな。
2021/11/21
感想・レビューをもっと見る