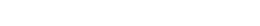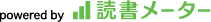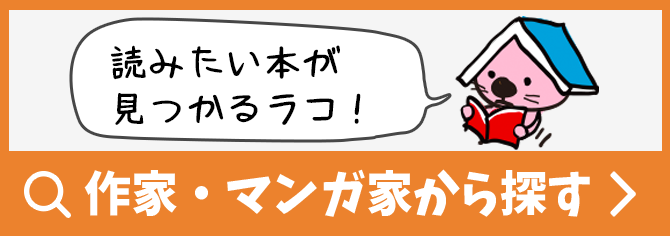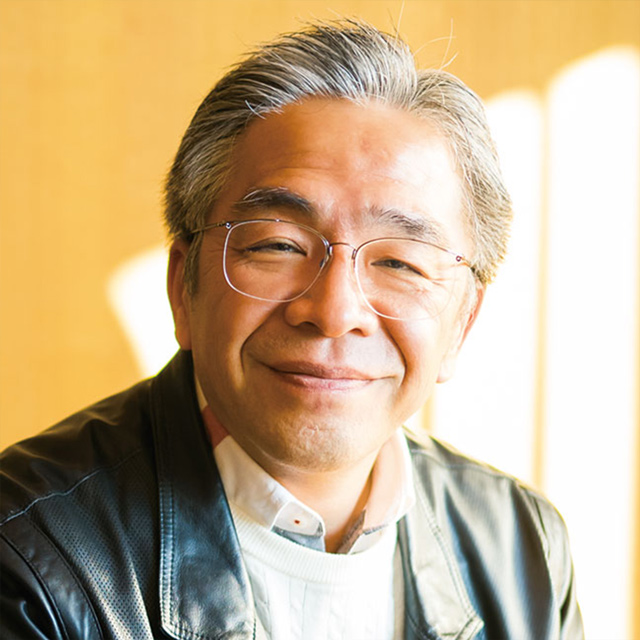母性という神話 (ちくま学芸文庫 ハ 11-1)
母性という神話 (ちくま学芸文庫 ハ 11-1) / 感想・レビュー
松本直哉
母性愛の概念が生きていたのはルソーとフロイトの間だけだった。全体の半分を占めるルソー以前の、特に旧制度下の捨て子や里子の多さ、乳児死亡率の高さの記述が驚き。育児への無関心。子どもの死を悲しまないこと。母性愛の賞揚は近代フランスの国力増強つまり人口増加(乳児死亡率の減少)への要請と軌を一にしていた。母性愛が常にうさんくさいのはそこに国家の影がちらつくからなのだ。フロイトの賞味期限の切れた今、この言葉はまだ死語になっていないにしても、子どもを育てるという喜びを母親に独占させるのはもったいないと思う主夫である。
2018/03/05
Narr
いわゆる「母性」とは、本能など本質的または自然的な特性ではなく母と子による偶発的な感情に過ぎず、近代社会のイデオロギーから産み落とされた歴史的・文化的な神話であると喝破した歴史書。母性それ自体は存在するし、母性に対して否定的な価値判断をする必要はない点に注意したい。問題は母性を女性の本質的な特性であると規定するばかりか、母性が(ないとされる)女性に対して排除を行うことで、女性が自身の地位獲得のための手段として「母性」をもった母となるよう差し向けられることであった。この研究にはマジで価値観変えられました。
2019/09/23
まりお
母親が持つ母性について、17世紀から1970年代までの女性の地位、役割、意識などの移り変わり、子供の地位と扱い、父親の役割などから探る。作中には女性の役割について、当時の人々の考えが書かれている。多くは母親はこうするべきだ、と生き方を決めつけた文である。女性についてありとあらゆる事を、外部が何故ここまで考えなければならないのか。女性をコントロールしなければ、という考えを感じた。
2016/11/04
魔魔男爵
人間には母性本能なんてない(チンパンジーにもない)のに、何故、そんなおかしな概念が定着したのかを、考察した本。18世紀末の仏政府の陰謀だったのでR!17~18世紀の二百年間、仏では子供は生まれてすぐ里子に出して乳母に育てさせるのが常識であった。貴族もブルジョアも商人も下層階級も全て里子に出す習慣であった。自分の子供を自分で授乳して育てるのは、出産した母全体のたった5%の極貧の乳母を雇う金のない人のみ。自宅に乳母を同居させたのは5%の上流階級のみ。90%の赤子は生まれてすぐ乳母の居る田舎へ旅することになり、
2018/06/14
nranjen
そもそももってこの本は何を訴えたいのかを考えると、第3部は本当に痛快。何を根拠にどう論理を組み立ててきたかを考えると、アナール派にカウントされる人たちの仕事はやっぱり面白いと感慨にふけっていた。こういう学問の質はすごい。1980年に出版された時の衝撃はどれほどだったのだろう。この本に描かれているように、時代のドクサというものの力と人の人生に与える影響力はすさまじい。それを明らかにしていく視点はいつの世の中にもあらまほしきことだ。
2018/11/24
感想・レビューをもっと見る