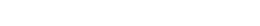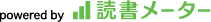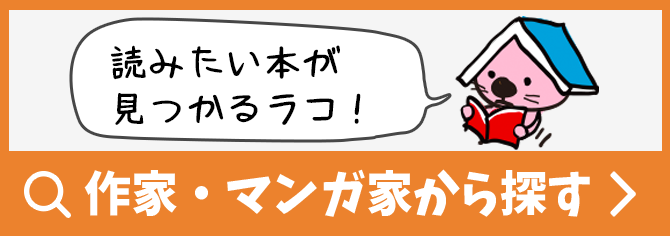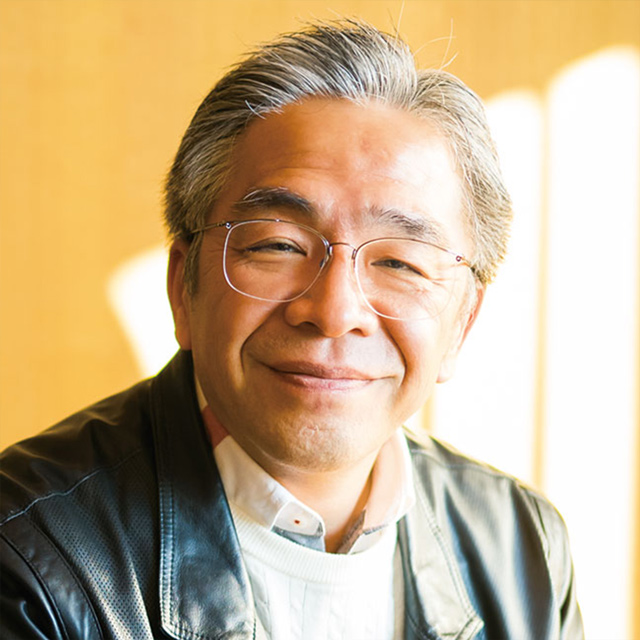動物の食に学ぶ
ジャンル
動物の食に学ぶ / 感想・レビュー
やすらぎ🍀
動物たちは何を食べ、人は何を食べるのか。主にヒトとサルの食を比べている。なぜ甘みと塩味に惹かれるのか。土を食べる謎。魚を食べる猿。ヒトとチンパンジーを分けた食とは何か…。食べる知恵を忘れつつあるヒトが生き方を見直すため、他の種と共存する動物たちを見習う必要がある。日本はいつからグルメ大国になったのか。世界に依存し生物多様性を破壊している食料輸入大国である。金で集めた食料を残し、食べ過ぎて健康を害する。誰しも食べることは楽しみである。生命の流れを絶やさぬため、ヒトは多様な生物とともに生きていかねばならない。
2020/01/21
姉勤
動物がなぜ、教えらせずとも食べられるものがわかるのか。それを知りたかったが本書にはなく。人の食のルーツをサルに辿る。昆虫と果実食が主体で、肉食は稀な事とと、人間が美味しいと感じるものは過去に必需食として摂っていたからという矛盾する謎。その他の動物の、通説を覆す事例や、食に適さないものを「薬」として色々な動物が口にしている事など面白い。最後は、日本人の豊かすぎる食文化の弊害は、世界の環境破壊に直結していると、セレンディーピティ。
2017/07/25
Humbaba
植物にとって、どのような方法を選択すれば趣旨を運んでもらえるかを考えることは重要である。この戦略を間違えてしまえばいくら種子を作ったとしても意味がなくなってしまう。媒介者を惹きつけるためには甘い餌が必要だが、それを作るためにはコストがかかるので可能な限り少なくしたい。
2013/12/14
貧家ピー
ヒトと主に霊長類の食を比較。種子散布を目的として食べてもらう果実を作った植物の戦略、甘い味に魅かれる理由、味覚、昆虫食についてなど。魚を食べる霊長類 人は珍しいことがわかった。
2023/10/31
Humbaba
動物の行動には意味があるはずである。しかし、ある行動が観測されたとしてもその意味をつかむことは難しい事も珍しくはない。植物は自分たちが生き延びるために様々な戦略をとっており、そこには意味が込められている。しかし、それも環境が変われば無意味になってしまう事もある。
2015/01/31
感想・レビューをもっと見る