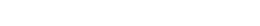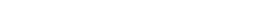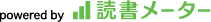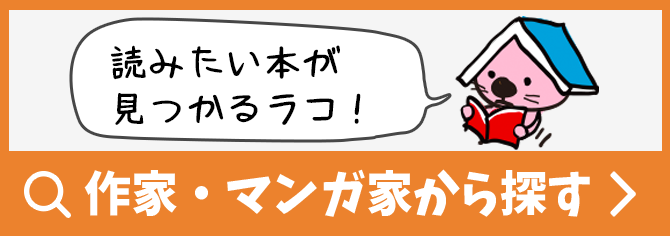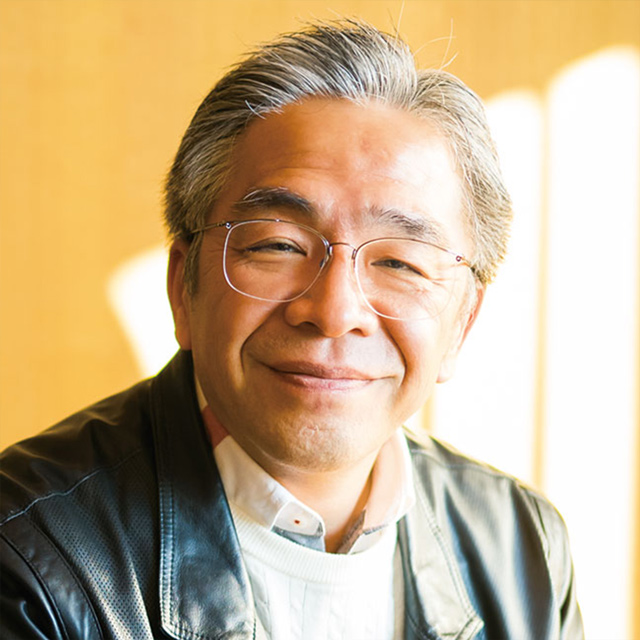SQ “かかわり”の知能指数
ジャンル
SQ “かかわり”の知能指数 / 感想・レビュー
Bartleby
SQを高めてみんなが密な関係になろうと主張している本ではない。むしろ、その人なりの「適切な範囲」でのかかわりを模索していくことや、顔だけは知っている他人を増やしていくことなど、「多生の縁」の重要性が強調されている。そして、中規模地方都市やライフスタイルセンターなどをヴィジョンとして提示しながら、コミュニケーションの生じやすい環境をいかに作っていくかが考えられている。個人のコミュニケーション能力を問題にするのではなく、誰もが緩やかなかかわりをもちやすくなる環境を考えようとする姿勢には共感できた。
2012/05/27
Roy。
【幸せに生きるためには】 社会貢献という言葉には方に力の入ったイメージがあるが日常生活の延長で自分にできることをやっていくことも十分に社会貢献である。また、遠すぎない未来を考え、モノより心を大事に、自分の生活圏の中で他人を思いやることが幸福度を高め人生を幸せにできる。 高度経済成長期での地域との関わり、都市への進出からその後の変遷をたどり、地域社会家族との関わりの変化を追える1冊。 コロナ禍で加速した面もあるが職住分離からテレワーク的住宅への変化することを当てていたのも興味深い。
2021/01/03
とろこ
特に目新しいことは書かれていなかったけど、「familiar stranger」はいい言葉だと思った。電車で毎朝一緒になる人とか、行きつけのお店の店員さんとか、「よく知らないけど顔見知り」レベルの人の存在にいざというときに救われるのかも。 アイデアまではおもしろいのに肝心なところで「何らかのかたちで」と逃げちゃうのがもったいない。ぶっとんでてもいいからそこを聞きたかった。
2012/12/15
ころこ
1章の幸福論の構想が、2章以降どこかへ忘れててきてしまっている、と感じます。好意的にみれば、本書は1章と、2章以降の異なる内容をたまたま1冊に纏めたという事になるでしょう。客観的な基準であるというSQは、経済的幸福のルサンチマン形態ではないか、他人の内心である幸福をなぜ道徳的に押し付けられなければならないか、という基本的な疑問に、鈴木さんは答えなければならないでしょう。
2016/11/07
ポコポッコ
関わりの知能指数「SQ」についてが主題。全4章構成で1章にて、人は「身近な他者に対して手助けをすること」で幸福度が上がると論じられ、先の章でさらにSQについて深掘りされると思っていたら主題のSQはほとんど論じられず、人の関わりの歴史や背景で4章まで終わってしまった・・・。うーむ・・・これは当時「絆」という言葉が強調された流れに便乗しようとしただけの本では?とゲスな勘ぐりをしてしまった。私が期待した内容では無かったが、こういった社会学を知りたくて購入する本でも無い気がする。うーん。。。
2019/04/26
感想・レビューをもっと見る