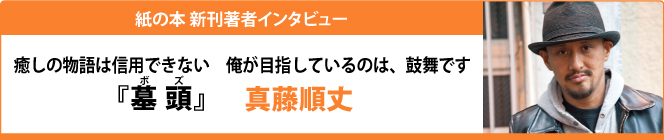癒しの物語は信用できない 俺が目指しているのは、鼓舞です
更新日:2013/12/4
墓の頭と書いて、ボズ(墓頭)。大理石でできた墓標のように黒く輝く、重厚な本のカバーに刻まれた二文字が、興趣をそそる。ページをめくると、飛び込んでくるのは次の一文だ。
〈生まれながらに彼は墓だった──/彼の人生をたどる旅に出るまで、僕が聞かされていたのはその一節だけだった。〉
2008年度エンタメ小説新人賞4冠を達成。連作中編集『畦と銃』が本誌イチオシ「プラチナ本」に選ばれるなど、着々とキャリアを築いてきた小説家・真藤順丈。待望の書き下ろし長編『墓頭』は、構想期間を含め執筆に3年もの月日をかけた、著者渾身にして勝負の一作だ。
「村上龍に『コインロッカー・ベイビーズ』があり、村上春樹に『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』があるように。今後も作家を続けていけると自信を持てるようなマスターピースを、30代のうちになんとか打ち立てたい。そう思いながら書きました」
しんどう・じゅんじょう●1977年東京都生まれ。『地図男』で第3回ダ・ヴィンチ文学賞大賞、『庵堂三兄弟の聖職』で第15回日本ホラー小説大賞大賞、『RANK』で第3回ポプラ社小説大賞特別賞、『東京ヴァンパイア・ファイナンス』で第15回電撃小説大賞銀賞と、2008年度エンタメ小説新人賞4冠を達成。近著に『バイブルDX』『畦と銃』など。
真藤によれば本作は、第15回日本ホラー小説大賞を受賞した『庵堂三兄弟の聖職』のラインを継ぐ、ホラー作品として構想された。
「ホラーをやるぞとなった時に、ホラーの対象、恐怖の対象をまず設定しなきゃいけないと思うんですね。貞子であるとか、ジェイソンであるとか。お化け系にするかスラッシャー系にするのかといろいろ考えていた時に、『頭のこぶの中に、双子の片割れの死体が詰まってる男』という主人公像が浮かんだんです。恐怖が外圧として襲ってくるのではなく、こぶの中、自分の中に内在しているって状態は、ある意味めちゃくちゃおっかないんじゃないかなと思っちゃったんですよ。それと同時に、そいつ自身の人生を描いたら面白いんじゃないかなと思っちゃったんです」
「思っちゃった」という口ぶりに、苦労の様子がうかがえる。「ボズの存在があまりに強烈すぎて、何度も挫折しかけました」と、苦笑い。他の作品を書いている時も、自ら生み出した稀代のモンスターの存在が、重くのしかかってきたそうだ。
「自分で自分の首を絞めたところもあります(笑)。“モンスターの一代記”ってところからどんどん欲をかいて、いろいろとお鍋にぶち込んでいったんです。一代記であり、歴史小説でもあり、伝奇小説であり、黙示録的な感じもあって、スリラーでもある。改稿ごとに、どんどん風呂敷を広げていったんですよね。それを畳むのが大変なんだってことを忘れちゃったんですよ」
だが、その大風呂敷こそが、本作の魅力なのだ。
「俺に書けるのか?」その感覚を大事にする
〈生まれながらに彼は墓だった──〉
その先へ、ページをめくろう。
小説家の「僕」が、失踪した父を探す旅路の果てに辿り着いたのは、インド洋の孤島。そこに暮らす養蚕家の老人から、「彼」に関する語りを聞くことになる。すべての始まりは、1955年11月、山梨県。
〈この世界に産まれ落ちるなり、ボズはまず母親を殺したよ〉
母親はボズの命と入れ違うようにして、出血多量で死んだ。「右額から頭のてっぺんにかけて、仔象の踝ほどに」ふくらんだこぶを持つ赤子を恐れ、家族は命名さえもせず蔵に閉じ込めた。手術を試みるも、中身が判明しただけで失敗。「あれはお頭にばらばら死体がつまった〈墓〉だ」。ボズの少年期は、差別と侮蔑の時を刻む。蔵のほこりの匂い、暗がりの悪意が濃厚に漂う、幻惑の文章体験だ。
やがて少年は、外の世界へ踏み出す。その途端、新たな死者が出る。医師、友人、実父……。自らが、呪われた存在であると彼は思う。
〈この頭のなかに死体があるかぎり、ぼくに関わった人間はみんな死ぬ──〉
「第1部は、『ジョーズ』でたとえるなら“サメを倒さなきゃいけない”っていう、物語のゴールの設定ですね」と、真藤は言う。
「『墓頭』のゴールは、“頭の中の死体を出す”です。わけが分からないですよね(笑)。最初にメディカルな方法は無理だってことを言ってるわけですよ。手術では取り出せない。じゃあ加持祈祷的なものなのか、もっと哲学的なロジックでケリをつけるのか。これは50年という長い長い時間をかけて、ボズがそういったトライ&エラーを繰り返すっていう物語なんです」
物語は、第2部から加速する。1969年、ボズ14歳。アウトサイダーばかりが集まる伊豆半島の福祉施設「白鳥塾」で、ボズは仲間を得る。おしゃべりのヒョウゴ。シロウとユウジン兄弟。聖少女アンジュ。彼らのキャラクター設定について、作家の語る言葉が面白かった。
「最初にイメージしたのは、悪いやつらってことですね。いいやつらではない。そいつらに出会ったことで、ボズが救われてしまうようなことはありえない。むしろ、出会ったことで余計、運命が翻弄されてしまう」
だが、最初は違ったはずなのだ。白鳥塾は指導官ホウヤのもと、独特の結束を得た。ボズにも居場所ができた、そう感じ始めた矢先、中国への団体旅行で、驚愕のサプライズが勃発する。
「ある歴史上の人物が関わってくるんですが、その展開を思いついた時はさすがに自分でも“大丈夫かな?”とひるみました(笑)。“こんなでかい話、俺に書けるのかな?”と。でも、その感覚が大事だと思ってるんですよ。自分の限界を広げるために、大風呂敷を広げる。そうすることで、作家として成長してきたつもりなんです」
第3部では高度成長期の日本、第4部ではポル・ポト政権が覇権を握るカンボジア、そして最終第5部ではインドネシア──。ボズの一代記が、現代史へと繋がり、物語は拡張する。そもそも。この物語は、誰が誰に語っているのか? 「語り」のミステリーも、読者を興奮に誘う。
「書きながら“なんか足りないな”っていうのはあったんですよ。なんか足りないって時って、答えは自分が書いた文章の中にあるんですよ。自分の無意識が書いているものを、拾えてないってことだと思うんです。それを拾っていったら……こういう語りのスタイルになりました」