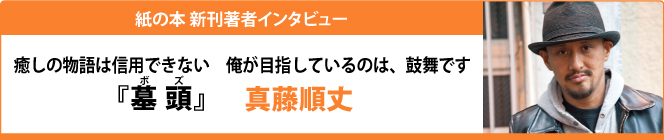癒しの物語は信用できない 俺が目指しているのは、鼓舞です
更新日:2013/12/4
“過去の物語と読者のために全部やる。死ぬ気でやる
かくしてこの物語は、章が進むごとに狂熱を高めながら、ゴールへと辿り着く。その頃にはもう、読者はボズと己の人生をシンクロさせていることだろう。思い返そう。ゴールは「頭の中の死体を出す」。もはやボズだけの問題ではない。
「ボズのこぶは、人それぞれが抱えている、自分で自分にかけている呪いの象徴とも捉えることができるのかな、と。その問題の活路を、ボズが50年の年月をかけて探していくのが、この物語なんです。あまっちょろい解決を提示して、安易にカタルシスを得ようとすることだけは絶対やめようと決めていましたね。癒し、というのはちょっと信用できないところがあります。僕が物語を作るうえで目指しているのは、どんなにしんどくても“でも、やるんだよ!”っていう、鼓舞ですね」
真藤の話を聞きながら、『墓頭』を読んでいる最中に沸き上がった特別な興奮が、理由のないものではない、と確信した。『カラマーゾフの兄弟』や『ユリシーズ』のことを、人は「総合小説」「全体小説」と呼ぶ。ジャンルの細分化が進んだ現在、あらゆるジャンルを横断し総合しようとする文学者の試みは途絶えつつある。だが、真藤順丈という作家はおもいきり手を伸ばすのだ。おもいきり風呂敷を広げるのだ。その勇姿にもきっと、読者は鼓舞される。
「そればっかりをやろうと思ってるわけではないんですよ。例えば『地図男』や『畦と銃』みたいに、読者の懐にしゅっと潜り込めるものも大事だと思っています。だけど、こういう“柄のでかいもの”、限界に挑戦するようなラインもやってかなきゃいけないなと思っている。柄のでかいものをやるって時に、自分の中で作った条件は“全部やる”ってことなんですよ。自分のできること、できないかもしれないけれどやりたいことを、全部やるんです」
「俺の人生にとって小説を書くことは、特別なことなんです」と、作家は決意を語る。
「このご時世に、小説を書いて本を出してもらえるという時点で、死ぬ気でやらないとウソだろってのがあります。そうしないと、小説ってものに失礼になるんじゃないかって。小説を書く時って、これまで自分がいたく感銘を受けたものとか人生を変えられたようなものを、常に頭のどこかで意識してるんですよね。そういうものに少しでもタッチできた瞬間が、幻想かもしれないけれど、訪れる時がある。その瞬間のために書いてるんですよ。『墓頭』でも、何度かありました。この小説が、読んでくれた人の想像力のともしびのようなものになったなら、書いた甲斐がありますね。リアクション、待ってます!(笑)」
取材・文=吉田大助 写真=野村佐紀子
『墓頭』
真藤順丈 角川書店 1995円
インド洋の孤島に住む養蚕家が、「僕」に語る。「彼」──ボズ(墓頭)の波乱に満ちたライフストーリーの始まりは1955年、山梨。顔の右側に巨大なこぶを抱えて生まれた少年は忌み嫌われ、やがて謎めいた福祉施設「白鳥塾」に収容される。70年代の香港九龍城、80年代のカンボジア内戦を経て、現代へ。ボズの存在が、世界を動かす。