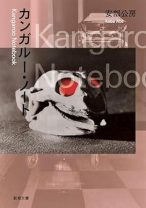「農耕」の始まりは弥生時代ではなく縄文時代だ! 『タネをまく縄文人 最新科学が覆す農耕の起源』 古代歴史文化賞大賞受賞記念・著者インタビュー
公開日:2017/12/12

縄文時代は狩猟・採集、弥生時代になって稲作が始まった――そう教えられてきた私たち日本人。だが最新の考古学の世界では、その常識を覆す「縄文時代から農耕が始まっていた」という新事実が発見されたという。このたび、その新事実をつきとめた『タネをまく縄文人 最新科学が覆す農耕の起源』(吉川弘文館)が第5回古代歴史文化賞大賞を受賞。すべては著者の小畑弘己先生が「レプリカ法(土器に残る植物の圧痕などからシリコーン樹脂を用いたレプリカを作り観察する方法)」という研究方法で、縄文土器から一粒の「ダイズ」を発見したのがはじまりだったという…。

■はじまりは一粒の「ダイズ」
小畑 私はもともと遺跡の土を洗って種を探すということをやってきたんです。遺跡の土壌の中には当時の家が焼けて炭になったり、米がこげてそのまま土の中にはいっていたりして、昔の食べ物や種が残っているんですよ。つまり土を調べれば当時の暮らし方が見えてくる。でも誰もが「当然お米を食べているのだろう」で思考が止まっていて研究しない。だったらやろう、と始めたんです。
今回の発見につながった「圧痕法」自体は80年代から始まった調査法ですが、2003年くらいから仲間がその方法で縄文土器を調べ始めていろいろ発見していて、興味は持っていたんです。で、たまたま卒論に悩んでいた学生に「こんなのあるよ」って紹介したら食いついてきた。それで一緒に島原半島を調査したら、最初に出てきたのが「ダイズ」だったんですね。実はそれまで縄文時代には「ダイズ」はない、弥生時代に伝わってきた作物だと言われていましたから、自分もそれを信じていました。それが目の前の縄文土器から出てきたわけです。
――すごい「運命のダイズ」ですね!
小畑 実はそれまで枝豆がダイズだと知らないくらい、ダイズのことなんて知りませんでした。もともと「形を見る」のは得意だったので、遺跡の土を洗っていたときも出土した種の形をわけて、あとは植物学者に何か同定してもらおうと考えていたくらいで。今回は自力で(注:穀物屋からありったけのマメを購入し観察)「縄文時代から大豆はあった。しかも大きさからいっても栽培していた」との発見にいたりましたが、最初に出会った圧痕がダイズであったというのは非常にラッキーでしたし、おかげで人生も変わりました(笑)。
――すごい新発見ですが、周囲はすぐに納得するんですか?
小畑 本物であることをきちんと証明する必要があります。もちろん不安はありましたが、今回は豆の形を調べて水につけたら同じ形になったので証明できたんですね。土器の中から出てくるということは「当時のモノそのもの」なんです。たとえば土の中のものというのは、新しいものをアリが運んだりすることもありますが、土器の中は製作時に練り込まれるので疑いようがないんです。証明ができれば「モノ自体」を疑うことはありません。本にも書きましたが資料というのは「見ようとしないと見えない」。みんな土器にあいた穴をたくさん見てきたはずで、そこにはきっとダイズもアズキもあったでしょう。でもそれを「ダイズやアズキ」と誰も思わなかったし、証明できなかったわけです。
――最近の考古学では科学的な分析方法も進んでいるようですね。
小畑 そうですね。出てきたものに科学的な裏付けがあれば認めざるをえないですし、その意味では考古学は自然科学に近い面があるかもしれません。もちろん今回は「これが本当に栽培なのか」と資料を基に社会を語っていくときには異論が出るでしょう。私としては今回、仮説を投げかけたつもりなので、これを波紋にいろんな議論がおこればいいし、客観的な証拠も集まればいい。
よく科学捜査で昆虫組成から死亡推定時刻を割り出すというのがありますが、私は古墳や甕棺などのお墓の土を洗って昆虫を調べたいんですよ。人骨の上にハエがたかったかもしれないし、甲虫がいたかもしれないし、それを探れば埋葬までの期間がわかる。まあ、私自身が楽しんでやっていることですが、考古学の世界はまだまだいろんなやり方があるというのを訴えたいですね。
――先生は「考古学科捜研の男」なわけですね!
小畑 そうかもしれません(笑)。ちなみに『CIS』っていうアメリカのドラマがありますが、あれは大人買いしています。科学捜査は面白いですよ。殺人の現場は、考古学でいう埋葬址と同じですから。いろんな小さな痕跡から探っていこうとするあの姿勢と技術力をどこまで応用できるかわかりませんが、昆虫だけはできるので。今はハエとかゴキブリの虜になっています(笑)。
■私たちの陥りやすい罠はひとつのイメージに
つい押しこめてしまうこと
――これから先生の学説で教科書が変わるかもしれませんね。
小畑 たしかに縄文人というのは植物や動物をかなり育てていたと思います。ただ私はひとつのステレオタイプにそれを刷り込みたくないんですね。大きく考えると西日本より東日本のほうが栽培植物への依存度が高いんですが、それは寒い冬を越すために食料を生産でまかなう比重が高くなるから。現在のような化学農法はありませんから、どこでもうまく栽培できるわけがありませんし、必要のないところでは栽培はしなかったでしょう。一口に縄文といってもひとつの文化や生活様式ということではなく多様性があるんです。おそらく「どこでもできるわけではない。必要なければしない」というのが縄文の農だったと思います。
私たちの陥りやすい罠は「弥生=稲」のように、ひとつのイメージについ押しこめてしまうこと。実際には弥生時代の土を洗っても出てくるのは麦とかアワとかキビなんですよ。教科書には「弥生=稲」と大きく書いてあるけれど、そうじゃない地域と時代があるんです。私はそういうステレオタイプの歴史観ががらがら崩れていくのが面白いし、興味があるんです。
――そういう考古学の視点は私たちの暮らしを考えるヒントにもなりそうです。
小畑 私自身はなるべく過去のことを現代におきかえて説明したいと思っているんです。自分の生活の中にアレがあるならきっと昔はこうだろうとか、そういう思考を持つと遠くの物が近くに見えるし、新しい発見もありますからね。
たとえば縄文人はカラスザンショウを貯蔵していたクリやドングリなどのコクゾウムシ除けに使ったりしていたようなんですが、それは今の生活と同じ発想ですよね。ただし今のように薬品で徹底的に排除なんてできませんし、「コクゾウムシさん、もうこないで」くらいの意識だったんだと。実は近代に「害虫」という概念は作られたようで、その前はイナゴがきても札をたてておくとかいう程度。殺せると思っていないし、ましてや壊滅させようなんて思考はなかったわけですよね。
私たちは科学の力で押さえつけて排除していこうという流れを強めてきて、共存ではないですが、一緒にどうにかするという姿勢を、もしかすると考古学が教えてくれるのかもしれません。一見、幸せそうに思えても長い人類史の中では耐性のできた虫との闘いを続けているわけで。最近は全部は殺さないソフトな農薬散布も出てきていますが、そうした発想の転換は大事でしょう。なんでも力で押さえつけてしまうとその裏に負の部分は必ずできます。そうであれば、もっと調和した無理をしない、ちょっとぐらい我慢する暮らしをする。それはたしかに縄文人が教えてくれるのかもしれません。
取材・文=荒井理恵