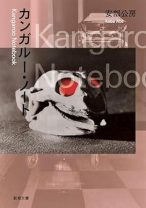累計40万部突破の大人気シリーズ『コンビニたそがれ堂 猫たちの星座』最新刊は“猫特集”! 猫との別れ、そして出会い―― 村山早紀インタビュー(前編)
更新日:2019/3/8

「風早駅前商店街の 駅前商店街のはずれに 夕暮れどきに行くと
古い路地の 赤い鳥居が並んでいるあたりで
不思議なコンビニを見つけることがあるといいます」
この一文から温かく、ほんのり切ない物語の扉はいつも開く。やさしい狐の神様と化け猫の看板娘が働く、「たそがれ堂」は、本当にほしいものがある人だけが辿りつける、この世で売っているすべてのもの、そしてこの世には売っていないはずのものまで何でも揃っている不思議なお店。そこでは大切な探しものが必ず見つかる――。
シリーズ累計40万部突破の大人気シリーズ最新刊『コンビニたそがれ堂 猫たちの星座』(ポプラ社)は刊行するなり今、読者の間に感動の輪を広げ続けている。第8弾である本作は、各話に猫が登場する“猫特集”。大の猫好きで知られる著者・村山早紀さんの真骨頂とも言える連作集となった。けれど、その誕生のきっかけには、20年近く共に暮らした猫との別れがあったという。

「なかなか大変な日々でした」と、穏やかに語る村山さんが、その日々のなかで繰り返していたのは、あとがきにも記されている“猫という形のうつわに入った、ひとつの魂、概念との対話”だったという。
物語は、てのひらに載るほど、小さく痩せた子猫・千春が、たそがれ堂にやってくる「しっぽの短い麦わら猫は その1」から幕を開ける。化け猫になるための薬を求めて――。
■猫に仮託し、人生の総決算的な想いを書いたところがあります
――しっぽの短い猫は長生きしても猫又になれない、ならば化け猫になりたいという“千春”には、モデルがいるそうですね。
今、千花ちゃんという子猫がうちにいまして。この子が千春のモデルです。新たに猫を迎えるのはもうやめようと思っていたのですが、ご縁があって、長崎県動物管理所からいただくことになったんです。小さな小さな麦わら猫で、しっぽの長さが中途半端な猫を。生後2ヶ月でうちに迎えたその子を育てていたとき、たまたま観ていたテレビ番組で、“猫又になれるのはしっぽの長い猫だけ”という話をしているのを耳にして。そのとき急に千花ちゃんがすごく可哀想に思えてしまったんですね。いらない猫として保健所に持ち込まれたうえに、この子は猫又にもなれないのかと。その思いがこの物語の発想のもとになっています。
――千春の切実な想いが響いてきます。“化け猫”になりたいという、物語で明かされていくその理由も。そこには村山さんご自身の、猫との出会いと別れ、そして猫への想いが投影されているようです。
1991年からこれまで4匹の猫と暮らしてきたのですが、そのなかで気付いたのが、猫は人間がすごく好きだということなんです。家族に溶け込み、人間の傍にいることを何より切望しているところがあるんですね。殊にそれを思い知らされるのが、猫が死ぬとき。本当に傍にいたがるんです、最後まで。“生きていきたい”という猫の生存本能は、人間の傍にいたい、というところに集約されてくるのではないかと思ってしまうほどに。そういう生き物である猫を、ちゃんと書いておきたかったということがありました。逝ってしまった猫と迎えた猫への想いも。
――千春をたそがれ堂で待っていてくれるのは、化け猫のねここ。このシリーズでは、店主の風早三郎と看板娘のねここ、どちらが待っているのかな?と毎回、楽しみですね。
8巻は猫特集なので、ねここです(笑)。2巻で登場してきた、ねここは、不幸なひとりぼっちのあやかしという感じだったけれど、お客様と出会い、語らうことで自分自身も癒されてきていますね。いろんな人の傷を癒していくことで、自分も救われていっているところがあるのだと思います。
――ねここは村山さんのなかでどんな存在なのですか。
猫の象徴というか、私の考える猫ですね。発想のベースにあるのが、佐賀の鍋島猫騒動など、語り継がれてきた怪談や民話。怪談に登場する猫って、主人のことが大好きで、自分自身に力がないがゆえ、化け猫になって仇をとるみたいなところがあるでしょう。そのイメージから派生している存在です。ちょっと怪しくて、ちょっと怖くて。だけど人間のことが大好きな。
――そんなねここは、千春を諭すように、たそがれ堂に来た2人のお客様の話を語っていきます。このシリーズには死や別れというものが物語の川底をいつも流れていますが、この2つの話は今までにないほど、それが色濃く表れていますね。
これほど死の色が濃厚な作品を書いていいのかなと、正直、躊躇しました。ただ私自身が昨年の猫の死で、かなりダメージを受けていたんですね。たそがれ堂8巻の締切が迫って、何か書かなくてはいけないと考えたとき、このテーマなら書けると。逆に言うと、それしか書けなかったのです。いつもはあらすじの段階で編集担当さんに読んでいただくのですが、今回はそれもしませんでした。
――そのときの気持ちがダイレクトに物語へと流れ込んでいるのですね。

猫を看取るのと同時進行で書いていた『星をつなぐ手』(PHP研究所より昨年刊行)もそうですが、猫へのレクイエムみたいなところがあります。この作品は、死んだ後の猫に対する想いですね。そして私自身も、年齢を重ねてきたので、猫に仮託し、人生の総決算的なことを書いたところがあります。
――ゆえに「サンタクロースの昇天」と「勇者のメロディ」という2つの話は、主人公の年齢がいつもより上なのですね。
いつも自分のなかにある感情しか書けないんです。執筆時、興味があったのは、命の生き死に。絶対に答えが出ないじゃないですか、生きることの意味というものは。それでも人は日々を生きていく。そのなかでたくさんの人やものを見送り、自分自身もやがて同じ道を行く。命だけではなく、身の回りの世の中、社会の変化、思い入れのある日本や世界の情景もみんな変わっていく。それもある意味、ひとつの死なわけで。そのことの意味も考えつつ、自分自身の思うところをそのまま書いた話になりました。
――人生の終焉に差し掛かった周太郎さんが、街の人たちに幸せを贈る物語「サンタクロースの昇天」。そのなかで口にする、「こんな素敵な世界に生まれてよかった、こんなに長く生きられてよかった」という想いは、ご自身の実感に近いのですね。
死ぬことを失われることだと捉えると、つらいと思うんです。そうではなく、ここに生まれ合わせて、今の時代に生きたということを僥倖だと思えば、生きることは素晴らしいことであると、そういう風に考えるようになってきたんです。何かこう、にぎやかな祝祭。生きることは多分、祝祭なんですよね。お祭りはいつか終わりが来る。でも祭りが続いている間は楽しまないと損じゃないですか。あとちょっとで終わってしまうと思って生きるより、楽しいなぁと思って生きたり、見ず知らずの人と同じ空間を楽しんだり。それが“生きる”ことなんじゃないかなと思うんです。その上で、何か自分が“楽しい”と思った良きことを誰かに譲り、残していけば、消滅にはつながらない。ずっと循環して世の中に残っていくんじゃないかなと思っていて。
――それが物語のなかで、周太郎さんのひそやかで素敵な活動に投影されて……。
そうなんです。そして周太郎さんのやっていることって、実はたそがれ堂とイコールなんです。たそがれ堂は神様が魔法によって、いろんな人を幸せにするけれど、周太郎さんは人の身の立場でそれを叶えようとする。だからねここは、周太郎さんに同業者的な気持ちを持ったのでしょうね。応援したくて、大盤振る舞いしていますね(笑)。
■幸せって、生きることの落しどころみたいなものかもしれませんね

――他者の幸せを願って生きる。もうすぐ取り壊される雑居ビルで占い師をしている、3話目の「勇者のメロディ」のユリエさんもそんな人ですね。
このシリーズ、実は友人、知人がモデルになっていることが多いんです。ユリエさんは、久しい友人である占い師の高橋桐矢さんがモデルです。彼女はいつも占いの最後に、“幸せを祈ってますから”って、にこっと微笑んでくれるんです。それがすごく気持ちに残っていて。祈る気持ちというのかな。それが発想の軸になっているところがあります。
――猫のおはぎさんと暮らすユリエさんは、〈この年まで独り身で、職業も安定していないもいいところ〉と言いつつも、日々にある幸せをしみじみと感じていますね。
ユリエさんと私は同世代くらいなのですが、この年になると“幸せってなんだろう”って考えてしまう。この話には、そうした気持ちも反映されています。「サンタクロースの昇天」の周太郎さんは、社会的に成功した人でもあるし、家族とも友人とも仲良しで、と、絵に描いたような幸せな人。かたやユリエさんは、ずっと独身で小さな古い雑居ビルで占いをして、いろんな人の幸せを祈ってきた人。真逆みたいな人生だけど、どっちも幸せなんですよね。そうしたいろんな人生の、いろんな幸せを書きたかったのかなぁと思います。幸せって、生きることの落しどころみたいなものなのかもしれませんね。
取材・文=河村道子 撮影=内海裕之
村山早紀
むらやま・さき●1963年、長崎県生まれ。『ちいさいえりちゃん』で毎日童話新人賞最優秀賞、第4回椋鳩十児童文学賞を受賞。著作に、風早の街を舞台にした『桜風堂ものがたり』(2017年本屋大賞ノミネート)、『百貨の魔法』(2018年本屋大賞ノミネート)、『カフェかもめ亭』『海馬亭通信』、このほど愛蔵版が刊行された『シェーラ姫の冒険』など多数。