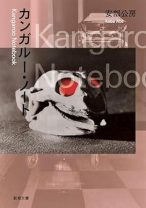どんな人にも訪れる「最期」を明るく迎えるには?『それでも病院で死にますか』出版記念トークイベント<前編>
公開日:2019/12/26

この世に生まれてきたからには、必ず誰もが迎える最期の日。その日を病院で迎えるのか、それとも住み慣れた場所で迎えるのか、それぞれどういった違いがあるのでしょう。京都で訪問診療医として活躍されている尾崎容子さんが、ご自身の母親や、訪問診療でのさまざまな看取りの経験をもとに「穏やかで明るい看取りの道」を探る初の著書『それでも病院で死にますか』(尾崎容子/セブン&アイ出版)を上梓。同書の出版記念トークイベントが大垣書店京都本店にて行われました。
今回のトークイベントでは、尾崎容子さんの実の妹であり、作家の尾﨑英子さんがゲストとして登壇。「姉妹漫才ではございませんが(笑)」と姉の尾崎さんが最初に語った通り、姉妹での軽妙な掛け合いに思わず笑いが起きる和やかなイベントとなりました。

母が乳がんに! しかも化学療法をやめてしまって……!?
イベント当日、大垣書店京都本店の「イベントスペース―催―」には多くの来場者が詰めかけ、用意された椅子は満席、立ち見も出るほどでした。その盛況ぶりは、終末期医療、とりわけ在宅医療に対する注目度の高さを伺わせました。対談テーマは「在宅で穏やかに明るく旅立つために」。おふたりが実際に経験した母親の看取りの経験からトークが展開していきます。

尾崎容子さん(以下、容子):今回『それでも病院で死にますか』というタイトルの本を出版いたしました。タイトルにつきましては、恫喝的な「死にますか!?」ではなく「(在宅には)こんな良さ、あんな良さがございます。それでも、病院で死にますか?」という、ちょっと下から上目遣いのご提案で(笑)。人間の多様な生き方についての問いかけをともにしていこうという本です。
私たちは4人姉妹なんですが、2017年に母が亡くなりました。娘と母とはしばしば断絶があったり修復があったりを繰り返していたんですけれども、病気(乳がんステージⅣ)が見つかった頃はまた断絶のタイミングだったので、母はしばらく病気のことは黙っておりました。で、その母が……最初は姉に言ったんでしたっけ?
尾崎英子さん(以下、英子):私は末っ子なんですが、母は長女とは唯一関係性がまだましといいますか、よい方でして。
容子:次女のわたしが最悪でございます。うふふ。
英子:まず秋ごろに長女と父が知って、私たちはお正月に「あけましておめでとう」って電話くらいしようかな、と思っていたときにいきなり言われるという衝撃的な展開で。
容子:私が一番、知るのが遅かったんですけど「人間やねんから病気くらいなるなる」くらいの感じでみておりました(笑)。で、話を聞くと化学療法をやめたと聞いて、あらあらと思って。そこで「やめたらダメだよ、治療したほうがいいよ」って普通ならば説得するところなんですけれども、まああの人やしな…と。
ここで妹の英子さんが挙手しながら「母の簡単なキャラクター説明も必要なんじゃないでしょうか」と、かつて占い師もしていたというマイペースで個性的なお母さまの紹介コーナーに。
英子:母はものすごく変わった人で、病的なほど楽観的でポジティブ。しかも宇宙とかスピリチュアルとか、そういうものが大好き。そういう人なので、私たちの言うことはまず聞かないという大前提があって。そんな母がもう化学療法をやめたってなったら、ああもうわかった。(この人は何を言っても)聞かないなって。
容子:化学療法をやめて、すっごく良い乳酸菌だとか、何にでも効くヨードの液体とか飲み始めて。
英子:むしろ飲んだら死にそうな、ドス黒い色をしたドリンクを(笑)。
容子:どうしてこの得体の知れない液体のことをそんなに信頼できるのか、どうしてそんなに医療を否定的な目で見るのかもわからなかったですね。娘が医者なのに(笑)。

「準備は追々で」と言う母に「オイオイ、その追々は今だよ!」とツッコミ
容子:その後、当然ですけど(化学療法を)やめたらやっぱり病気は悪くなる。6月末頃に母は脳転移から強いめまいを訴えまして、症状緩和のためにも全脳照射(※)は受けたら? とさすがの私も提案してみたんですが、それもまあ拒否ということで。じゃあもう、この状態で何もしないとなると(最期の日までは)“週単位”やなあって。私の見積もりでは、10週ないくらいかなっていう。それはすごく悲しかったですね。
※脳全体に放射線を照射する治療法
英子:母の看取りの中でいえば、その頃が感情のピークでしたね。家族もまだ受け入れらないし、なのに母は、自分のやりたいようにやるって言っていて。そこでやっぱり思いはぶつかり合いますよね。でもそれはもうどこの家庭でも、そういう状況になったらきっと訪れることだと思います。
どんなに理性的だったり、知識があったりする人でも、やっぱりそういう経験は初めてなわけですから、本人も家族も、覚悟みたいなものはなかなか生まれないと思うんですよね。「いやいや余命1ヶ月と言われても1年くらい生きることだってあるでしょう」って。うちはの母は準備をしなきゃいけないって言っても「追々でいいよ」って祈祷ばっかりしていて。そんな母に対して姉(容子さん)は「オイオイ、今だよその“追々”は!」っていうツッコミをしていました(笑)。
容子:もう本人はまったく死ぬつもりはなかったみたいですね。実際、死にそうになっても生き返っていましたし。でも結局は、(脳転移が見つかって)3週間ほどで亡くなったので、やっぱり早かった。母はすごく極端な人だったんですが、がんの細胞も80%が増える細胞だったんです。ふつうは、20%でも早いっていわれるのですが、母はもう最後まで極端というか、さすがというか。主治医の先生も「この数字は初めてです、すごいね」って言っていました(笑)。
英子:あはは。笑い事じゃないですけどね。
尾崎姉妹のお母さまは2017年8月に永眠。おふたりのトークからは、母の死に対して「ああしてあげたらよかった、こうしてあげたらよかった」という後悔や悲壮感などのネガティブな感情がまったくなく、むしろちょっと変わった母との別れの時間をいとおしく思い出しているような様子が印象的でした。
『それでも病院で死にますか』には、病院間のやりとりや周囲との連携の様子など、尾崎家が経験した母の旅立ちまでの詳細な経過が記録されています。また、妹の英子さんはこの経験から着想を得た小説『有村家のその日まで』(尾﨑英子/光文社)を執筆されています。次回のレポートでは、気になる“お金”の問題や、話題の「人生会議」について語られたトークイベントの続きをお届けします!
プロフィール
尾崎容子(訪問診療医)
京都市の在宅療養支援診療所「おかやま在宅クリニック」院長。産経新聞大阪本社地域版にて「在宅善哉」を月2回連載中。
取材・文=本宮丈子
写真=佐藤佑樹