はやみねかおる「子どもにとっては大金だから、600円の値打ちのある小説にしなきゃあかん」
公開日:2021/9/24

デビューした当初からずっと書いた小説が値段にみあう内容かどうか自問自答しながら執筆してきたというはやみねかおるさん。インタビュー中編では、今夏映画化され話題となった『都会のトム&ソーヤ』以外の作品創作秘話をうかがった。
(取材・文=立花もも)
――『都会のトム&ソーヤ』で、主人公・内人と創也のライバルとなる、伝説のゲームクリエイター「栗井栄太」。彼らは実は、複数人のクリエイター集団だというのが、シリーズが進むにつれすごくいいなと感じるようになりました。内人と創也の関係もそうですが、足りないものを補いあうという、自立した協同関係もテーマのひとつなのかな、と。
はやみねかおる(以下、はやみねさん):無意識やと思うんですけど、あるかもしれませんね。ぼくは大学を出てすぐ教師になったんですが、そのとき実感したのが「学校の先生って、自分にできないことも教えていいんや」ってことだったんですよ。たとえばぼくは、泳ぎは得意なのにクロールができない。でも、クロールのやり方は完璧に知っているから、子どもらに教えてできるようにさせてあげることはできる。何もかもできるようになる必要はないし、できないならできないなりの教え方があるんだ、という身についた感覚が、常に頭の片隅にあるような気もします。
――依存するのではなく、自分にできるすべてを尽くしたうえで、誰かを信じて任せる、というのは“生き延びる”ためにすごく大事なことなんだな、とシリーズを読んでいると感じます。
はやみねさん:そうですねえ。内人はおばあちゃんからサバイバル能力を叩き込まれていますけど、ぼく自身「絶対に生きて帰ってこい」とばあちゃんから言われて育ったんですよ。ばあちゃんは、ぼくの親父以外の息子を全員、戦争で亡くしているもので、孫は絶対に家に帰ってくるよう願っていたんだろう、ということが今ならよくわかります。
――はやみねさんも、内人のようにおばあさまからサバイバル技術を教えてもらうことはあったんですか?
はやみねさん:サバイバルというほどじゃないですけど、田舎の不便なところに住んでいますから「困ったときは自分でなんとかする」という教えは叩き込まれています。何かがないからできない、ではなくて、ないものは自分でつくってどうにかする。だから今も、モノが捨てられないんですよ。ロープでも輪ゴムでも、これを置いておいたら何かをつくる役に立つんやないかって思っちゃうから。
――たしかに、内人も日常のありふれた道具をくみあわせて道具をつくり、危機を突破しますね。1巻で創也の仕掛けた罠を突破したときも「電池とクリップだけでそんなことが!?」と驚きました。
はやみねさん:ばあちゃんに叩き込まれたサバイバルの心得は、ひとつは「身のまわりにあるものだけで状況を切り抜ける」ということ。そしてもうひとつが「そういう知恵を使わずにいられる状況に、常に身を置いておけ」ということ。つまり、危険なほうへは絶対に行くなということです。
――無謀と勇気は違う、ってことですね。はやみねさんの小説には常に“近づいてはならないもの”のにおいも漂っています。発想を変えるだけで、世界のどんなことも楽しくワクワクしたものに変わる。だけど好奇心に憑りつかれて善悪の境目を失ってしまった人を描くことで、一線を越えてしまうことの恐怖もしっかり教えてくれる。“楽しい”からといって何をしてもいいわけじゃないんだと。
はやみねさん:そうですねえ。『都会のトム&ソーヤ』に限らず、ぼくはけっこう大人の……なんちゅうんですかね、昏い陰のような部分も書いているもんで、「子どもが読んでもこんなのわからんやろ」と言われることもあるんですよ。でも今わからなくてもいいじゃないか、いつか読み返してくれたらそのときにわかるかもしれないし、何もかもわかってしまったらそれで終わりだ、っていう気持ちがぼくにはある。それから、デビューした当初からずっと、ぼくの書いた小説が値段にみあう内容かどうか、っていう不安があるんですよね。青い鳥文庫は600円くらいですけど、子どもにとっては大金だから、支払うだけの値打ちのあるものにしなきゃあかん、と思い続けている。だからどうにかして、1冊を豪華な弁当みたいに仕立てあげなきゃ、と苦心しているわけです。
――豪華な弁当?
はやみねさん:ただののり弁だと思って食べて、なかにおかずが敷いてあると嬉しいじゃないですか(笑)。おかずが二層になっていればなおさら嬉しいし、場所によって味が違うとワクワクする。食べれば食べるほど楽しみが増える、みたいな本にしておきたいんです。そのための仕掛けのひとつが「大人になって読み返すとまた違う感じ方ができる」ってことですよね。
――前編でもお話しいただいた、道徳を説くより、まず子どもたちが「楽しい!」と心躍るほうが先ということにも通じますね。
はやみねさん:はい。ただ、これもお伝えしましたが、ぼく自身がやっぱり、道徳的なことが苦手なんです。楽しければ何をしてもいいというわけじゃない、けれど、どこまでがよくてどこからがだめなのか? ということの判断を正確にくだすことができるとはいえない。ともすると、そっち側に行ってもいいんじゃないか、と思わせてしまう書き方をする危険性がある。
――『都会のトム&ソーヤ』には、組織の命令を守るためなら他者の命が奪われたとしてもかまわない、という美少女が登場しますが、彼女もかなり魅力的ではありますしね。
はやみねさん:そうですね。だからこそ、“近づいてはならないもの”との境目は、かなり気をつけながら書いています。
――はやみねさんの座右の銘に“赤い夢へようこそ”というものがありますが、一度捕まってしまうと抜け出せない楽しさの檻みたいなものが、“赤い夢”なのかなあと思ったりもします。夢なのか現実なのかわからないまま、ふわふわと、自分だけの喜びのなかを生きてしまう。それはとても幸せだけど、怖いことでもあるなあと。
はやみねさん:ぼく自身、いまだに赤い夢のなかで遊んでいるような感覚なんですよ。ただ「赤い夢ってなに?」と聞かれると、うまく説明できない。本格ミステリーの世界を味わっているときの純粋なドキドキや、くらーいところに引きずり込まれそうになるような感覚、そういうのを全部ひっくるめて“赤い夢”って言ってるのかなあ、と思いますけどね。まあでもそれは、読んでくださった方一人ひとりにそれぞれの夢の形があるんじゃないか、と逃げています(笑)。
――“ようこそ”とおっしゃっているように、近づいてはならないと警鐘を鳴らしながらも、はやみねさんは赤い夢にとらわれてしまった人を否定していないですよね。主人公たちを踏みとどまらせることで、そちら側に行ってはいけない、と示唆してはいますが……。
はやみねさん:ぼく自身がとらわれてしまった側の人間ですからねえ。だから本当に、難しいんですよ。赤い夢のなかにはたぶん、“やっていいこと”と“いけないこと”ではなく、“やっていいこと”と“やって楽しいこと”があるんです。その“楽しいこと”がもたらす結果とかを、子どもたちがうまいこと物語を通じて咀嚼し、自分なりの理解を深めてくれたらいいなあとは思いながら書いています。
――書くうえで、気をつけていることはありますか?
はやみねさん:罪を犯してしまったとして、その行為が美しいか美しくないか、というのは常に意識しています。法に触れていても美しい奴はいるし、逆にまっとうに生きているように見えて、ちっとも美しくない連中はごまんといる。そのへんは子どもらにも読みとってもらえると嬉しいです。
――法に触れているけど美しい奴、の筆頭が怪盗クイーンじゃないですか。
はやみねさん:たしかに(笑)。あれは、美意識のかたまりですからね。怪盗という存在じたいが、美しさを貫いている人たちですし。

――もともとは夢水清志郎(教授)の好敵手として登場した彼もまた、来年、スクリーンに登場します(※『怪盗クイーンはサーカスがお好き』は2022年夏、劇場版OVA化予定)。
はやみねさん:いやあ、本当に楽しみです。ぼくは絵を描く人間ではないので、カット割りとか見せていただいてもよくわからないけれど、一生懸命いいものにしようとしてくださっているのは感じるので、ストーリーの構成に多少口を挟みつつ、イラストを描いてくださっているK2商会さんに基本はお任せしています。『都会トム』のにしけいこさんもそうですが、シリーズはイラストに引っ張られてぐんぐん育ったところがありますので。
――シリーズを追うごとにイラストもどんどん生き生きと育っていますよね。『怪盗クイーンはサーカスがお好き』のころは、今に比べると全体的にシリアスというかハードボイルドな雰囲気でしたが……。
はやみねさん:最初は、江戸川乱歩が描くサーカス小屋みたいな怪しさ満点の小説を書こうとしていたので、その名残でしょうね。いつのまにか、ニースだろうとエジプトの砂漠だろうと気分ひとつでどこへでも行くし、暗殺者とも陰陽師とも対決する。ときにファンタジーな展開さえ起きる作品になっていきました。ただまあ、クイーンはぼくがつくろうと思ってつくったキャラクターではないですから。20歳のとき、勝手に夢のなかに登場して育っていった教授と同じように、あるときいきなりふわっと生まれてしまった。そのときから性別不明で、年齢不明。正体も不明。大きな飛行船に乗って、世界中どこへでも好きなように飛びまわって好きなように生きる。設定として決まっていたのはそれくらいです。仕事上のパートナーであるジョーカーや人工知能のRD、探偵卿などとの関わりを描くうちにだんだん、ぼく自身も彼の背景を知っていった、という感じです。
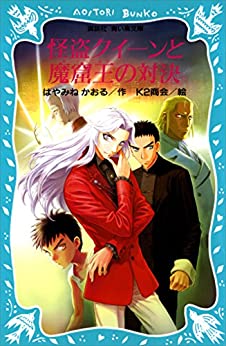
――最初にファンタジー要素がくわわったのは3巻『怪盗クイーンと魔窟王の対決』でした。
はやみねさん:あれを書いても読者がついてきてくれたのは、ホッとしました。普通にモノを盗むだけの怪盗だったら、それ以上は書き続けられなかったと思います。とはいえ、むやみやたらにファンタジーな展開をOKにしているわけではないですけどね。3巻の「半月石(ハーフムーン)」のように、不思議なことが起きかねない獲物をクイーンが狙ったときだけ。そうして、獲物を現実的なものに限定しなかったことで、世界観がぐっと広がってくれました。
――初期の作品は論理的に事件をひもといていくものがほとんどでしたが、いつからかほかの作品でもファンタジー要素が入り混じるようになりましたよね。『都会トム』やほかの作品にも「時見」という未来を見ることのできる存在が登場しますし、『令夢の世界はスリップする 赤い夢へようこそ 前奏曲』では世界を“スリップ”することができる少女が主人公。さらにそこには、内藤内人が登場するという……。

はやみねさん:ぼくの小説世界は全部つながっているんですけど、その総ざらいをそろそろ始めないとな、と。令夢シリーズをとっかかりに、あと8年ですべてをひとつにする作業を進めようと思っているんです。で、それを書き終えてから、ぼくは小説を書くことから引退します。
▶9/25(土)公開のインタビュー後編では、引退についての想いをうかがっています。






























