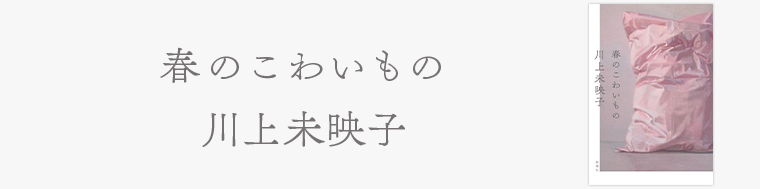「わたしたちは、いつも何かが起きる“前の日”にいる」コロナ禍の直前を描いた短編集『春のこわいもの』川上未映子インタビュー
更新日:2022/3/22

高級ホテルでギャラ飲みの面接を受ける女性たち、深夜の学校に忍び込む高校生、寝たきりのベッドで人生を振り返る老女……。感染症が蔓延する“直前”を描いた6編の短編集『春のこわいもの』(川上未映子/新潮社)が、このたび上梓された。ダ・ヴィンチWebでは、収録作「あなたの鼻がもう少し高ければ」を公開中。整形手術やパパ活をテーマにした衝撃作は、早くも話題を呼んでいる。
パンデミックの“直前”にフォーカスした理由、「あなたの鼻がもう少し高ければ」に込めた思い、そしてご自身の死生観について、川上未映子さんに語っていただいた。
(取材・文=野本由起)
起きてしまったあとではなく、その“直前”を書くことで本質を掴みたい

――『春のこわいもの』は、もともと「Amazon オーディオブックAudible」から音声で楽しむ作品として先行配信されていました。このたび紙の本として刊行されますが、そもそもこの短編集はどのようにして生まれたのでしょうか。
川上未映子さん(以下、川上):ご依頼をいただいたのは、2019年の暮れでした。「『オーディブル』で1冊作りましょう」「“オーディオファースト”作品として、皆さんに耳で聞いていただくことを前提にしましょう」というお話でした。その後、新型コロナウイルス感染症が広がる中、2020年11月頃から執筆を始め、年をまたいで書き終えました。
当時は、まだコロナが拡大してから1年経っていませんでしたが、感染症の第1波、第2波が来て、ワクチンの見通しもありませんでした。どうなっていくのかわからない状況で始まった執筆でした。
でも、パンデミック時に起きたあとの出来事を書くことにはならず、それが起きる“直前”を書くことになりました。たとえば、写真を見ながら「このときはみんな、こんなことが起きるなんて知らなかったんだな」というようなことを思うことが多いんです。良いことに対してはそうは思わないのですが、取り返しのつかないことが起きると「このときは、誰も知らなかったんだな」というように考えてしまうんです。明日起きることを知るすべもなく、起きる前にはもう戻れない。でも、物事は起きてしまうんですよね。
――もう取り戻せないからこそ、“直前”を書いておきたいということでしょうか。
川上:もう戻ってこない時間、失われた時間を記憶しておきたいという感じではないですね。
起きてしまったあとや、それとどう付きあっていくかを書くのではなく、それをまだ知らずにいられた瞬間を書くことが、なにか……時間とか、人のありかたの本質に関係するんじゃないかという直感があるという感じです。わたしたちは、何かが起きる“前の日”にいつもいます。その“前の日”を書くことが、今を書くことになると思うのかもしれません。
――作中で明示されているわけではありませんが、収録された6編はどれも2020年3月頃が舞台です。まさに、緊急事態宣言が出される“直前”ですね。
川上:そうですね。2020年の年明けに知り合いの家でホームパーティーをした時、「中国が大変らしい」みたいな話をしたことを覚えています。2月になるとダイヤモンドプリンセス号で集団感染が広がって、またたく間に世界各地でパンデミックが広がっていきました。そうした中、ニューヨーク・タイムズからコラムを依頼されたのですが、3月連休の上野公園の写真がとても印象的だったんです。世界中でパンデミックが起きているのに、日本人はマスクをつけて大勢の人たちとともに桜の下を歩いている。いっぽう、アメリカの知人や編集者からは、もうとんでもないことになってるという連絡が毎日のように来ているような状態で、日本はそれこそ、まだことが起きる直前にいて、どこかゆるやかな催眠状態にあるような感じがしました。結局、日本はニューヨークのような感染状況にはなりませんでしたが、あのときは──今もですけど、専門家のあいだでも意見がわかれ、確かなことはなにもありませんでした。あの時期の緊張感、得体の知れなさも含めて、短編を書いていきました。
今や整形手術は自己実現の手段。血を流し、サバイブした人への敬意がある
――6つの短編は、どのような順番で書いていったのでしょう。
川上:最初は「ブルー・インク」でした。記録を残したくないという強迫観念を持つ女の子と男の子の話です。それから「あなたの鼻がもう少し高ければ」「淋しくなったら電話をかけて」「花瓶」「娘について」を書き、最後に「青かける青」の順だったかな。「青かける青」は、最初に置きたいなと思いました。
――「青かける青」は、耳で聴くことを意識された作品ではないかと思いました。
川上:手紙の形式で、ひっそり語りかける感じですしね。
――「あなたの鼻がもう少し高ければ」は、ギャラ飲みを志願する大学生のお話です。ギャラ飲みやパパ活を斡旋する女性「モエシャン」にあこがれ、渋谷の高級ホテルで面接を受けるものの……という痛烈な展開が、胸にグサッと刺さりました。
川上:若い女性が視点人物なので、言葉遣いやテンションなど、いろいろと調整が必要でした。
――「まじ骨格ウェーブで優勝したい」「だいたいなんでわたしはブルベ冬として生まれてこなかった人生なのか」など、ワードも語り口もリアルです。
川上:でも、今はもう「ブルべ夏ナチュラルなんとかトーン」のように細分化されていて、そうした日々更新される情報は、書いた瞬間にどうしても古くなっていきますね。
――「あなたの鼻がもう少し高ければ」というタイトルも絶妙ですよね。
川上:この話はタイトルが最初にあって、作っていきました。
――主人公は美容や整形に執着し、パパ活をしたいと思っている女の子です。全肯定できるわけではありませんが、その生き方に不思議なすがすがしさを感じました。
川上:整形手術のありかたが、この十年くらいで大きく変わりましたよね。昔は隠すものでしたし、テレビ番組などもありましたが、他人が納得できるような理由が必要なことも多かったです。でも、今や整形手術は他者のいない自己実現の手段になっていますね。とはいえ、同じように容姿を変えるにしても、パーソナルトレーナーについて筋トレするの同じとはいえないところがあります。整形手術では血が流れますから。
かつてはビフォアアフターの間にどれくらい血が流れ、どれくらい痛みを伴うのかが可視化されていませんでした。でも今は、みんながSNSやYouTubeに経過も含めてアップしています。そして、その経過を見る側には、サバイブし、自己変革を成し遂げた人に対する敬意があります。過程がつらければつらいほどリスペクトは高まって、共感とともに称賛をおくる。わたしの世代にはないアーカイブだと思います。
――世間ではルッキズムを問題視していますが、彼女たちにはそうした考えはないようです。
川上:ボディポジティブやセルフラブといった価値観も知られてきましたし、たくさんの人と共有したいものですが、若い女性たちが思う「かわいくなりたい」とか「きれいになりたい」には、事実として多様性があります。自分で選んだものがあり、他人の目を気にしたものがあり、流行りのものがあり、どうしても憧れてしまうものがあり、その少しずつが混ざりあい、年齢とともに変化したり、しなかったりします。もともと満たされて幸せな人はいいですが、苦しくて、現状を変えたくて、必死に生きるしかない人は、容姿に限ったことではなく、なにかしらのオブセッションとともにあることは避けられないと思います。
――川上さんは『乳と卵』『夏物語』でも、豊胸手術について書いています。顔や身体を変えること、もしくは身体そのものへの関心があるのでしょうか。
川上:そうですね。身体は人間にとって大きいルールだと思います。身体って本当に大変なもの。痛みもそうですが、有限であるという事実は、人の思いを超えるものだと思います。本当にままならない他者を生きているという実感があります。その意味で、生きることは「失われ」のなかにいることにほかならないというか。
――それは、コロナと関係なくもともとあった感覚ですか?
川上:はい。よく覚えているのは、子どもの頃に電車に乗った時のこと。向かいの席に、わたしが育ってきたのとおなじような、ワーキングクラスふうのご家族がいて、お出かけにすごくうきうきしているのが伝わってきました。お父さんはジャンパーを着て、ご家族での外出を楽しんでいて。小さな男の子の靴紐を結んであげたり、窓の外をみながら、みんなが笑顔で。それを見つめながら、「わたしは今、この人たちの思い出を見ているんだな。記憶を見てるんだな」と思いました。「で、すべての瞬間がそうなんだな」って。昔からですけど、死ぬことについては本当に最近はよく考えます。
――どういうことを考えているのでしょう。
川上:最大に生きても、あと40年くらいですよね。これまで生きてきた時間だと考えると。十分に長いのですが、そうなると、今90歳の方は自分の今後をどういうスパンで捉えているんだろうと想像するんです。よくあるように「もう来年の桜は見られないな」と本当に思うのか、どうなのか、と。そんなことを考えていた時に、祖母が96歳で亡くなったんです。わたしはずっと祖母とやりとりしていましたが、亡くなる2週間前まで「人間はな、こうせなあかん」なんて志を語るわけです。もちろん夜中に不安になることはあったかもしれませんが、生が持続している、今が持続している感じがしました。
死にかんしては、出産でもいろんなことを感じました。今は医療もしっかりしているので、自分が出産で死ぬことはないだろうと思ってはいましたが、そうは言っても亡くなってしまわれる方もいます。病院からもそういう話をされましたし、今まで生きてきた中で、自覚的に、もっとも死に近づく瞬間ではありました。「このまま死ぬ可能性もあるわけか」と思い、それはどういうことなのか、なにを思うべきなのか、このときにしか考えられないはずのことを考えるべきだろうと思っても、出産が近づいてくるとそれ以上考えられなくなるんですね。ふかふかの布団に巻かれてベルトコンベアーに乗せられてるみたいにぼんやりして。「死ぬかもしれんのか──あ、お菓子食べよ」みたいな気持ちになって(笑)。
生きてる段階で考えられる死が、果たして本当の死なのかどうかもわからないんだけれど、でもその可能性が今までよりも濃く近づいてくるときには、あまり物事を考えられなくなるような“ふわふわアドレナリン”みたいなものが出るんだな、と思いました。その感覚を覚えているので、たとえば自分が80歳、90歳まで来たら、こんな感じになるのかもしれないな、と。ふわふわのなかでも、この短編集みたいに、なにかを書くことができたらいいな、とは思うんですけど。。
――でも、「整形をしたい」というパワーと、死を感じてふわふわする感覚は対局のようにも感じますが。
川上:一見そうですよね。でも、生をサバイブしてやろうと思う瞬間が、一番死に近づいている気がしませんか? 極限状態の時に笑っちゃうとか、本当に楽しい時にものすごく悲しくなるとか、極端なものを同時に生きている瞬間があると思うんですよね。「死にたい」と言う人の中に「生きたい」という声を聞くことはよくありますし、「生きたい」と言う人にも破滅的なところはある。「整形したい、綺麗になりたい」という人たちにも「綺麗になれたらもう死にたい」って言う人がいます。何かを強く思う時、その逆のことを常に求めてしまうことがある。人はそうやって引き裂かれる中で、バランスを取って生きているんです。だからこそ、強い何かを持っているというのは、それだけで大変な人生だと思いますね。
感染症は免れることができても、「あなたもいつか必ず死ぬ」
――他には、「淋しくなったら電話をかけて」も印象的でした。「あなた」という二人称で、ある女性の内面が描かれていきます。
川上:二人称の小説には独特の効果がありますよね。「私」という一人称とも、三人称とも違います。「おまえも例外ではないよ」と指をさされるような。この短編に関しては、最初から「あなた」でした。彼女は外側から見ると、普通に散歩して、喫茶店に行って、家に帰ってくるだけ。でも、内側ではこんなことが起きている。あなた自身にも気づかれない地獄があなたにもあるという話です。
オブセッショナルな状況に置かれたとき、それを見ないといけないのに、自分の中に封印していた別のオブセッションが内側から出てくるというのが、6編すべてに共通するものかもしれませんね。感染症下というある種の監禁状態、ある種の抑圧に対峙すればすむわけではなくて、絶対になくならないオブセッションが込みあげてくる。「感染症は免れたとしても、でも、あなたは必ず死ぬんだぞ」と。
――タイトルの『春のこわいもの』には、そういった意味も入っているんですね。
川上:そうですね。世界はこわいものだらけだと思います(笑)。