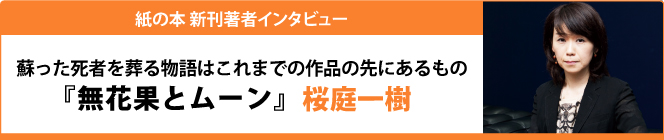蘇った死者を葬(おく)る物語はこれまでの作品の先にあるもの
更新日:2013/12/4
紫の目をした、もらいっ子。大好きなお兄ちゃんの死から始まる、18歳の少女・月夜のひと夏の成長・冒険譚─。冒頭から、真っ向ストレートでぐいぐい胸をしめつけてくる本書『無花果とムーン』はじつは、昨年完結した桜庭さんの代表作のひとつ「GOSICK」シリーズにもつながるものなのだという。
「少し前に、あるインタビュアーさんから言われて気づいたことがあるんです。私の書くものって、全然、別の作品であっても、どこかつながっている面がありませんか?と。たとえば『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』では少女が死んでしまう話を書いて。その少女をもう一回生き返らせてもう一回死んでもらうということで、『私の男』を書いた。そして、『私の男』のあとに、『ばらばら死体の夜』ではバラバラ死体にして、また死んでもらって。さらに、『傷痕』で大スターの死というかなり大きな死を書いて、ようやく死んでもらって─と。つまり、自分のなかに何か“核”になるものがあって、それを死なせる。でも、また蘇ってくる。だから、なんとかして死なせようとして、でもまた生き返ってきちゃって次の話を書いている。たしかに言われてみると、私はここ何年か、そういうふうにずっと小説を書いてきたんだなと、指摘されて初めて気がついたんですね。けれども、この『無花果とムーン』になると、もうそれが死んでいるところから始まっていて。だからこの話はこれまでとはたしかに核の部分でつながってはいるけれど、ある意味、その先に一歩進んだというか。いってみれば、ただ死なせるだけではなく、〈死者が蘇って、それをもう一度葬る〉という話になったと思います」
世阿弥の能を観ながら一気に思いついたプロット
さくらば・かずき●鳥取県出身。2000年デビュー。03年開始の「GOSICK」シリーズ、04年『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』が高い評価を受け、07年『赤朽葉家の伝説』で日本推理作家協会賞受賞。08年『私の男』で直木賞受賞。アニメ映画化された『伏 贋作・里見八犬伝』も10月20日より公開中。
蘇ってきた死者をしっかりと葬る─。無意識のなかでも自分の核を何度も追いつづけ、あらたな核=テーマに辿り着いたとき、桜庭さんはまた、それが古来より語り継がれてきた、ある種、普遍的な物語であることにも気づいたのだという。
「ちょうど『GOSICK』の完結編を書いているときに、内田樹さんの書評を読んでいて、非常におもしろい説を見つけたんです。その骨子をかいつまんで説明させていただくと、韓国ドラマの『冬のソナタ』は、村上春樹の『羊をめぐる冒険』から書かれている。なぜならどちらも死者を葬る話であるから、というものなんです。『冬の〜』は、高校生のときに初恋の男の子が死んじゃって、大人になったあと、その初恋の男の子にそっくりの人に出会う話ですよね? でも内田説によると、恋人はもう死んでいて、忘れられてしまったがために戻ってきて、もう一回生者に思い出してもらって、気がすんで死者の国に戻っていく話となる。そして、内田さんはさらに、『冬の〜』の脚本家は『羊を〜』に影響を受けているし、『羊を〜』はチャンドラーの『ロング・グッドバイ』に、さらに『ロング〜』はフィッツジェラルドの『華麗なるギャツビー』に影響を受けている。そういうふうに死者が蘇ってきて生者と関わるというのは昔からお話のパターンとしてずっとある。たとえば世阿弥が完成させた複式夢幻能も、死者がやってきて最後に舞いを踊って去っていく。そこまで考えると、『冬の〜』はじつは古来から繰り返し語られてきたお話をやっているのだとも言っているんですね(笑)。そして私は、その内田説を読んだときに、この『無花果とムーン』の話の概要を思いついたんです。『GOSICK』の完結編が終わった、その次に書くのは絶対それがいいな、と」
そして桜庭さんは『GOSICK』の完結編を書き終えてすぐに、複式夢幻能の「野守」を観に行った。さらに、蘇ってきた死者と生者の能=舞を観ながら、そのパンフレットの空欄に今回のプロットのすべてを走り書きしたのである。
「すごい不審な観客だったと思うんですけれども(笑)。でもほんとうにその能─旅人が昔ここに死者がいたんだよと告げ、そこで死者がやってきて最後は激しく美しく舞って去っていく─という話を観ているとき、自分のなかにわっと今回のイメージができたんですね。能のなかで死者の話を聞く“ワキ〟の役割をするのが、ヒロインの月夜。それから、ここに死者がいたんですよと教える“前シテ”の役が、旅人の密。そして、“後シテ”(=蘇ってきた死者)がお兄ちゃんの奈落というふうに、この3人のイメージがわーっと出てきたんですね」
まさにある種の奇跡のように一気に符合、成立した物語。また今回、桜庭さんは一気に書くことにもこだわったのだという。
「たとえば『私の男』や『傷痕』のような作品では、映画の『グラン・ブルー』のように、6章ぐらいに分けて1章ずつ、途中、息がつづかないから、インターバルを入れながら、徐々に深く潜行するように書くというやり方をしたんですが、今回は、ちょっとテンションを上げた状態で一気に書いたほうがいいな、と。ちょうど年末年始が空いていたので、思いついたまま3週間ぐらいで最後まで書き上げました。『赤朽葉家の伝説』や『砂糖菓子〜』もそうだったんですけれど、今回のように高めのテンションの人が一気に語っていく話は、こちらも一気に最後まで走るように書いた方がいいな、と。だから、その3週間は毎日、“これが終わったらお酒を飲みにいくんだ、具体的にはワインを、日本酒だったらあん肝を─”とか思いながら書いていました(笑)」
ただし、そのやり方は一歩間違えると、最初からすべてやり直しになることもある。たとえば、『青年のための読書クラブ』のときは、最初、女のコの一人称にするとまったくダメで、三人称にしてもまたダメで、1カ月紆余曲折して悩んだ末、誰かが書き遺した文章であるという文体にして、やっと上手くいったとか。でも今回は、書き出しから、すべてがかちっとはまった。そして、読む者の心を猛スピードでぐいぐい引きこんでいく物語はまた、ヒロインの月夜だけでなく、登場する人物それぞれが、非常に個性豊かで魅力的な作品にもなったのである。
「作品によって、毎回、リアリティをどこに置くかのバランスを、目盛りみたいに考えていて。たとえば『私の男』は人物にリアリティを置くので、あまり極端な人は出さないようにしました。でも今回は、テーマが重たいから、キャラクターはちょっと二次元寄りに、あるいは役者さんが演じているふうに、ひと目見て誰だかわかる、ちょっと極端にしたほうが読みやすいだろうな、と。それでヒロインの月夜も、ちょっと過剰で欠けた感じ、あるいは子供の頃、誰もが“自分もそうだったらいいな”と、ひそかに憧れたような特徴をもたせてみたんですね」