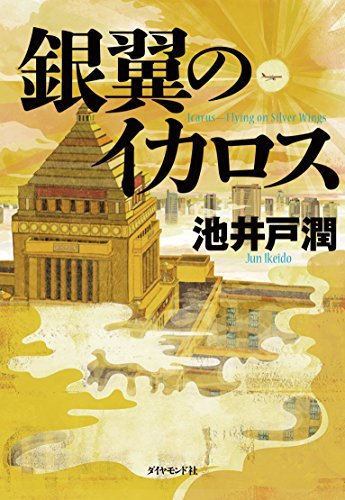半沢直樹の“新たな敵”を池井戸潤が語る ―シリーズ最新作『銀翼のイカロス』発売間近!
更新日:2017/11/21
2014年、春から夏にかけてのテレビ界は、池井戸潤が席巻した、といっても過言ではないだろう。6月、好評のうちに完結した連続ドラマ『花咲舞が黙ってない』と『ルーズヴェルト・ゲーム』。2作同時の映像化は、昨年の『半沢直樹』『七つの会議』に続いてのことだった。
『ダ・ヴィンチ』8月号ではそんな池井戸潤を大特集。ロングインタビューを掲載している。
「小説でもドラマでも今はコメディが難しい時代ですが、『花咲舞が黙ってない』は脚本がよくできていて、水曜夜10時に観るのにちょうどいい。杏さんも、自分なりの花咲舞をきちんと作っていらっしゃるようで、楽しく観ました。『ルーズヴェルト・ゲーム』の野球シーンも、とてもよかったじゃないですか。あの場面の説得力は、やっぱり断然、小説より映像だと思いましたね」
国民的物語ブランドとしてすっかり定着した“原作・池井戸潤”の看板。さあ、次は書店の棚が沸き立つときが来る。まもなく発表される小説の新作は、『オレたちバブル入行組』『オレたち花のバブル組』、そして2012年刊行の『ロスジェネの逆襲』に続く、待望の「半沢直樹」シリーズ第4弾『銀翼のイカロス』である。
出向先での活躍を経て東京中央銀行へ復帰した半沢直樹の次なるミッションは、経営破綻状態に陥った国内最大の航空会社・帝国航空の再建。近年、現実に起こった出来事を想起させる展開だ。
「実際の事件や社会現象を取り上げているわけではないんですが、やはりニュースは関心を持って見ていましたね。皆の憧れだった企業が実際には大変な赤字会社で、社員のエリート意識が世の顰蹙(ひんしゅく)を買ったり……。破綻前から報道を注意深く見ていて、これはなかなか興味深いと思ったので、半沢に担当させてみました(笑)。『ロスジェネの逆襲』では部下に大人しく応対していた半沢ですが、今回はまた子どもに戻っています。口は悪いしやることは汚いし、やりたい放題。でも、そういうスタンスこそが半沢の原点だと思うので。丁寧で礼儀正しい主人公なんて、面白くないですから」
実は池井戸さん、数年前にも航空会社の再建チームの奮闘を描いた小説を文芸誌に連載。「どうしても気に食わなくて」お蔵入りにしたその作品を換骨奪胎(かんこつだったい)し、まったく新しい一編に構築し直したのが『銀翼のイカロス』だという。
「ある程度皆が共通に知っている事実をモチーフにした小説には、いろいろな制限や独特の息苦しさがある。『銀翼のイカロス』でも、連載中は実験的に手探りで書いていた部分がありましたが、単行本ではその枠組みを壊しつつ、当初の目的から離れすぎないように、バランスを取りながら仕上げています」
銀行内部の派閥抗争や、取引先との駆け引き。これまで、いわば身内や身辺の敵との鍔迫(つばぜ)り合いを繰り広げてきた半沢は、今作では、政治勢力というあらたな相手に対峙。そこが、物語のスケールを拡大するポイントになっている。
「普通にいくと、航空会社のエリートたちの不遜や傲慢さと闘うという構図になるんですが、書いているうちに、どうもそれが違うような気がしてきて。たとえば、社員の待遇が多少手厚すぎたとして、“そんなことだから会社が潰れるんだよ”と言うのは簡単だけれど、本当にそうなのか? と。実際は、その程度のことでは会社は潰れない。原因はもっと構造的な、経営の失敗にあると思うんです。じゃあなぜその失敗が起こったのかを検証するという手もあるけれども、僕はそこにはあまり興味がなくて、むしろ進駐軍のように経営再建に乗り出してきたタスクフォース(再生のため、政府が設置した専門家集団)の人々を、航空会社側がどんなふうに見ていたのかが気になった。それで、半沢対帝国航空ではなく、対タスクフォースという構図にしたんです」
今、もっとも世の中から“物語”を求められる作家・池井戸潤。同誌では、自問の末に辿り着いた、究極のリアリティについて、今後の創作についても語っている。ほか、『花咲舞が黙ってない』花咲舞役を務めた杏、『半沢直樹』から片岡愛之助、『鉄の骨』で主演を務めた小池徹平も登場し、作品の魅力について語っている。
取材・文=大谷道子/ダ・ヴィンチ8月号「池井戸潤」特集