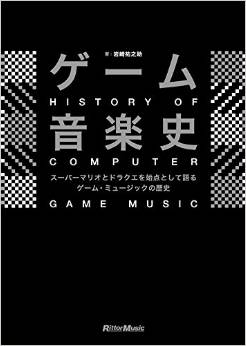【マリオ、ドラクエ…、知られざるゲーム音楽の歴史】スーパーマリオではノイズがドラム音代わり?
公開日:2014/8/8
何時間でも何十時間でもゲームに没頭してしまう。それは、ゲームそれ自体の面白さももちろんだが、我々がゲームの音楽に惹き込まれてしまっているからではないだろうか。なぜ、あんなにもゲーム音楽は私たちプレイヤーを魅了してやまないのだろう。音楽を聞くだけで、時に勇気が湧いたり、時に失望が深まったりする。そんなゲーム音楽はどのような工夫をもって制作させてきたのか。その原点には一体何があるのだろうか。
岩崎祐之助氏著『ゲーム音楽史 スーパーマリオとドラクエを始点とするゲーム・ミュージックの歴史』(リットーミュージック)では、ファミコン時代からスーパーファミコン、プレステ、Wiiに至るまで、ゲーム音楽がどのような変遷を経て進化していったのか、その特徴に触れている。コンピューター・ゲームの発展の途中、ゲームを盛り上げるための演出の1つとして音楽が使用させるようになったのは、1980年前後のこと。やがて、ゲームが場面展開やストーリー展開を持つようになると、それらに合わせて多くの楽曲が作り出され、ゲーム音楽という1つの音楽ジャンルが確立していったという。
ピコピコ音から始まったゲーム音楽はその製作者たちのアイディアの発展に支えられ、常に進化し続けてきた。近年では、豪華で高音質なゲーム音楽が当たり前になったが、コンピューター・ゲームの黎明期から発展途上の時代では、技術的な制約のために楽曲の構造を簡素化する必要があった。そのメロディを目立せるシンプルな構成、そして、音楽制作者たちがゲーム機ごとにこらした工夫がプレイヤー達の感動を大きいものにしたと岩崎氏は語る。
ゲームの音源には、多くの制限があったが、この音源でどこまでの音楽ができるのかという音楽制作者たちの強いチャレンジ精神が多くの優れた楽曲を生み出してきた。
たとえば、任天堂に音楽専門として初めて採用された近藤浩治氏が作曲した『スーパーマリオブラザーズ』のゲーム音楽には多くの工夫が見てとれる。『スーパーマリオ』が発売された1985年当時、ファミコンで出せる音は、矩形波2パート、三角波1パート、ノイズ1パートという4パートのみだった。矩形波とは音色は選択できるものの自然界の音とは程遠い「ピコピコ」と鳴る機械音であるし、三角波は「ポー」というような音、ノイズは名の通り「ザー」という雑音しか流れない。こんな限られた音の中で一体どうやって音楽を作り出していたかといえば、音楽制作者たちは、矩形波をメロディライン、三角波をベースライン、そして、ノイズをドラムパートとして活用したらしい。「ザー」となるだけの雑音をリズムを刻むハイハット代わりとして活用することで限られた音のみでも奥行きの出る音楽を実現しようとしたのだと岩崎氏はいう。そんな工夫は、半音進行の印象的なメロディラインとともに「スーパーマリオ」の世界を彩り、一度聞いたら忘れられない音楽を生み出した。
『亜麻色の髪の乙女』や『花の首飾り』といった歌謡曲でヒットを飛ばしていたすぎやまこういち氏がゲーム内音楽を作曲し、1986年から発売された「ドラゴンクエスト」シリーズ、特に1988年に発売された『ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…』にもさらに多くの工夫が見られる。ノイズを除く3パートしか同時発音できないファミコンは音の厚みが薄くなりがちだが、すぎやま氏は『ドラクエIII』内で32分音符を多用し、「ドミソドミソドミソ…」と素早く音階を鳴らすサブメロディパートを用いた。これは分散和音と呼ばれる手法で、1パートだけの消費でまるで和音が鳴っているかのような重厚感が出せるのだ。また、「ポー」という三角波を時にメロディラインとして用いることで独特の音色を時にはオカリナ、時にはホルンのように表現してみせた。そして、すぎやま氏は今までゲーム音楽ではさせていなかったプレイヤーの心情描写を行おうとした。それまでのゲーム音楽はゲームの場面や舞台、登場人物や敵を描写するものだったが、ゲームのラスボス、ゾーマとの戦闘曲「勇者の挑戦」では、勇者であるプレイヤーが勇敢に戦う心情を描いている。これにより、ゲーム音楽は人々の心に寄り添う音楽になりえたのだという。
その後、すぎやま氏に続くように、他分野で注目を浴びた音楽家がゲーム音楽を積極的に作曲し始める。『題名のない音楽会21』も務めていた羽田健太郎氏は「ウィザードリィ」シリーズを、サザンオールスターズのべーシストである関口和之氏は『桃太郎伝説』の楽曲を作曲する。さらにスーパーファミコンが誕生するとPCM音源が8パートという音の幅広さを手にすることができ、音楽の幅は広がっていったが、メモリの制限との戦いはまだ終わらなかった。
ゲーム音楽は技術的制約をいかに乗り越えるか、限られたパート数でいかに音に厚みを出すか、どうやってリアリティのあるサウンドを生み出すかという工夫によって発展してきた。これからはどのような新しい世界を生み出してくれるのだろうか。どんなに技術が発展しても、人の心に響く新しい音楽を作り続けようというパイオニア精神を持ち続けてほしいものである。
文=アサトーミナミ