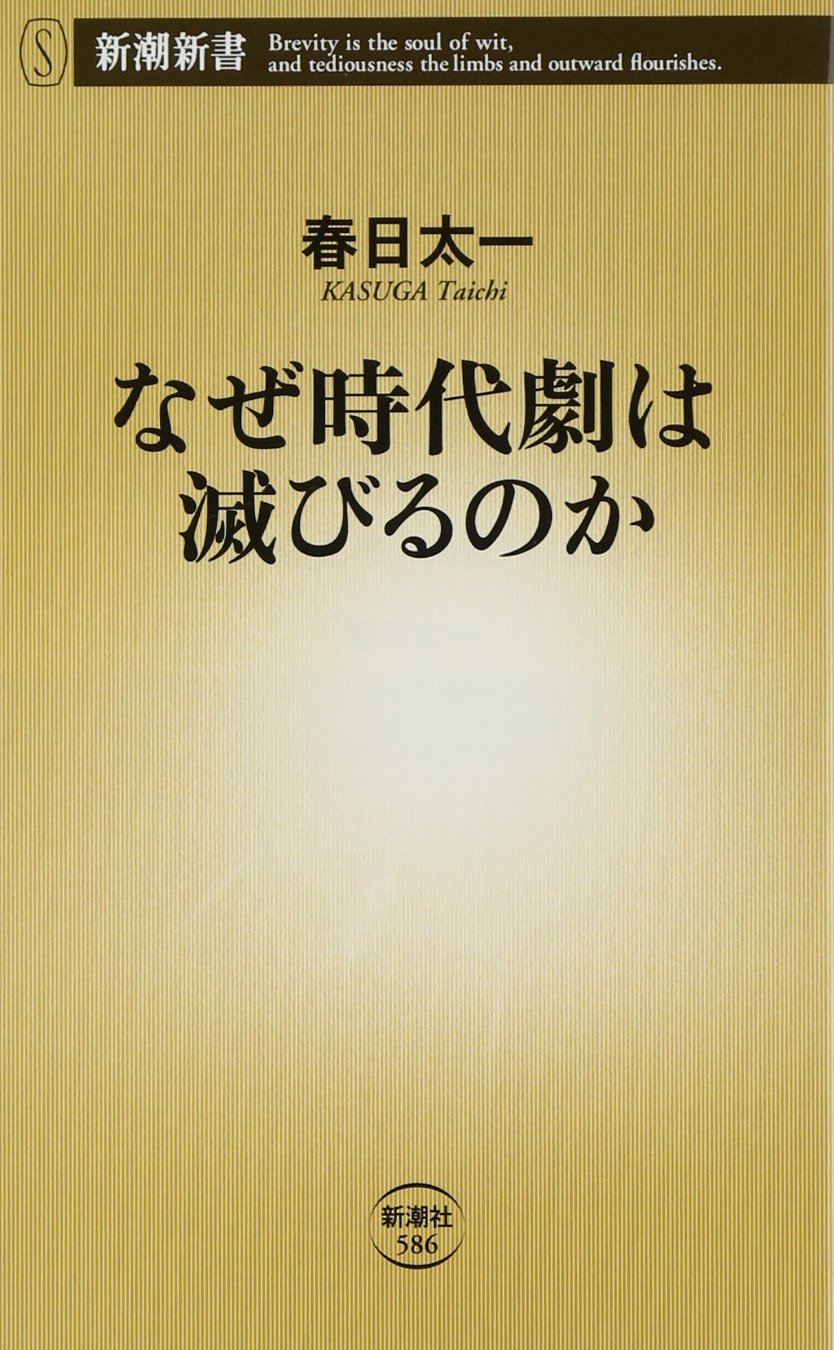民放地上波で時代劇枠が消滅してしまった理由とは
公開日:2014/10/19
先日、『闇の狩人』という時代劇を観た。池波正太郎原作のノワール色の濃い作品で、陰影のある画面作りが印象に残る質の高いドラマであった。
ところがこのドラマ、実は地上波では放送されていない。「時代劇専門チャンネル」というスカパー!・CSチャンネルが製作した、オリジナルの時代劇なのである。前・後編合わせて3時間の長編、しかも中村梅雀や津川雅彦といった第一線のキャストを揃えた大型企画が、なぜスカパー!・CSのみでの放送なのか。
そもそも考えてみると、現在地上波で時代劇をレギュラー放送する枠がNHKの大河ドラマ以外に全くないことに気が付く。一体なぜ、時代劇ドラマは地上波TVから姿を消してしまったのか。
そうした疑問に答えてくれるのが、春日太一『なぜ時代劇は滅びるのか』(新潮社)である。春日は『時代劇は死なず! 京都太秦の「職人」たち』(集英社)『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文藝春秋)といった著作で時代劇俳優・撮影所文化の研究者として注目を集めている。
タイトルの通り、本書はズバリ時代劇が衰退した要因を徹底的に検証した本である。
まず春日は1960年代の時代劇映画の不振から、2011年のドラマ「水戸黄門」の放送終了による地上波レギュラー枠の消滅に至るまで、時代劇凋落の歴史をまとめた上で、時代劇が観られなくなった原因を時代劇=〈高齢者向け〉という固定概念が出来上がってしまったことだと指摘する。
いやいや、時代劇なんて元々おじいちゃんおばあちゃんのために作られていたものでしょう、と突っ込まれる方もいるだろう。しかし、春日は第2章「時代劇は『つまらない』?」で以下のような意見を述べる。
「時代劇は古臭い“お決まり”劇ではなく、“現在進行形のエンターテインメント”だと筆者は考えている。(中略)時代劇の大きな魅力は、まずはなんといっても“ファンタジー”を描けることだ。(中略)そして、もう一つの魅力は、現代では描ききれないような大がかりなエンターテインメントの状況を作りやすいところにある。」
時代劇とは予定調和や型にはまった演出を楽しむものではなく、むしろ従来の常識にとらわれることのない、自由奔放な表現を可能にするジャンルである、という著者なりの定義を明確に打ち出した点が本書の良い所だ。このはっきりとした“ものさし”によって、春日は制作者・俳優など時代劇に関わる人間が抱える問題点に鋭く切り込んでいく。
例えば先述の時代劇=〈高齢向け〉というイメージが出来上がった問題について、春日はテレビ時代劇の生産効率を上げるための「物語のパターン化」が背景にあることを指摘する。映画興行が上手くいかない映画会社は安定した収入を得ようと、1970年代後半からテレビ時代劇の制作受注を増やしはじめる。その際求められたのは、脚本や演出のフォーマット化することで撮影の効率化を図ることであった。結果として「水戸黄門」式の勧善懲悪パターンばかりが時代劇にはびこり、マンネリを楽しむことの出来る高齢層のみが視聴者として残り続けた、というわけだ。
また、時代劇に向けた役の作りこみができない俳優たちに対しても、春日は辛辣な批判を向けている。春日は時代劇役者に必要な条件をこう言う。
「《遠い過去》という、現代とは違う異世界のキャラクターをリアルなものとして見せるためには、日常から逸脱した“作り込み”が必要になってくる。(中略)役者が現代とは異なる芝居をすることで初めて、時代劇の役柄はそれっぽく見えるし、だからこそカッコ良く映り、時代劇はファンタジーの世界として成り立つのだ」
ファンタジーとしての時代劇を作るためには、役者が「ウソを本当に見せるための技術」を身に付けなければいけない。ところが現代の俳優たちは役の作り込みを勉強しないどころか、作り込まれた芝居よりも自分の「自然体」を出すことに重きをおいて演技をしようとする者さえいる。だが「自然体」でリアルを出そうと思った演技プランは、却って衣装や舞台の“ウソ”を目立たせることにつながり、時代劇の芝居としては非常に拙いものに見えてしまうのである。春日は時代劇=ファンタジーと理解せず、「自然体」志向で役の作り込みをしない俳優たちを、きっぱり「下手である」と一刀両断しているのだ。
春日太一には俳優・勝新太郎を題材にしたノンフィクション『天才 勝新太郎』(文藝春秋)という著書がある。ここで春日が光を当てたのは、時代劇ドラマで次々と尖鋭的な映像を生み出そうと情熱を捧げる、演出家としての勝新太郎の姿であった。繰り返しになるが春日は時代劇を「自由に新しい映像表現を生み出すための実験の場」として捉えており、その自由な場を守ろうとする強い意志のもとに「なぜ時代劇は滅びるのか」を書いたことがひしひしと伝わってきた。ぜひとも「新しいエンターテインメント」として時代劇には生き残って欲しいという気持ちにさせてくれる本だ。
文=若林踏