キルラキルはわけのわからないもの? 脚本家中島かずき『キルラキル』トークイベントレポート
更新日:2014/11/26
去る2014年9月15日(月)大阪市宗右衛門町にあるロフトプラスワン・ウエストで、脚本家の中島かずきさんによるトークイベント「関西炉風斗賦羅素湾制圧イベント」が行われた。司会はライターの宮昌太朗さんとニュータイプ編集部の鳩岡桃子さんが務めた。
・中島かずき(なかしま・かずき)
劇団☆新感線の座付作家として活躍する脚本家。アニメーション作品では『Re:キューティーハニー』(2004)のシリーズ構成、脚本として参加してことがきっかけで今石洋之監督と出会い、同監督と組んだ『天元突破グレンラガン』(2007)で一躍アニメファンの間でも名前を知られる存在になった。2013年10月から2014年の3月まで放送された『キルラキル』では全25話の脚本を担当。その脚本を全て収めた「キルラキル脚本全集」(以下、脚本全集)を9月10日に上梓。

会場内に設置された販売ブースでは、参加者が次々と本を購入していた
「脚本全集」には本編25話だけでなく、ドラマCD4話分のシナリオ、サブタイトルに用いられ歌謡曲の元ネタ、定稿から制作の過程で改変された部分に関する中島さんの解説コメントも収録されている。まさに『キルラキル』の設計書といえる一冊だ。また、中島さんは本作の功績が広く認められ月刊ニュータイプが主催する「ニュータイプアニメアワード2014」において最優秀脚本賞を受賞された。
■アニメを文字で読み楽しむということ
「脚本全集」の刊行は中島さんから、ニュータイプ編集部に持ちかけた企画だという。中島さんは「『キルラキル』に関しては、ほぼ一人で書いているので、自分の作品としてやりきったという想いがありました。放送されたアニメとは違う、自分の脚本ではこうだったというのを見てもらいたかった」と刊行の経緯を語る。TVアニメのシナリオはこのように書籍として刊行されない限り、ファンが脚本を読むことは難しい。中島さんは「この本がこれから後に続くアニメシナリオライターの希望の星になればいい」と語った。本書の企画に携わった鳩岡さんは「“武滾流猛怒”(ぶったぎるもーど)など、この作品は文字で読む方が面白さが増すのではないか」と、中島さんの言葉のエッセンスを味わうためにも「脚本全集」が役立つことを指摘。ライターの宮さんは「サイクルの速いTVアニメ制作において、全話を一人の作家が担当するということは少ないので、このような「脚本全集」は大変貴重。アニメもハリウッドのようにどんどん脚本本を出して行くべき」とコメントした。アニメ作品を文字として読むことで鑑賞の楽しみもより広がるだろう。今後、一般の視聴者にもアニメの脚本に触れる機会が増えることを願いたい。
■『キルラキル』の面白さの底流にあるもの
ロフトプラスワン・ウエストでは、このイベントのために特別に考案されたオリジナルメニュー「お肉アーマー」や「なんだかよくわからないコロッケ」、「鮮血」と「純潔」をイメージしたドリンクが特別メニューとしてふるまわれた。登壇者もオリジナルドリンクで乾杯。会場いっぱいに集まった参加者は食事を楽しみながら、中島さんのトークに耳を傾ける。

会場内に設置された販売ブースでは、参加者が次々と本を購入していた
イベントの前半では、『キルラキル』の成立背景に『男組』(原作:雁屋哲/作画:池上遼一)や、意志を持つ衣服のアイデアに『カエアンの聖衣』(バリントン・J・ベイリー)の影響があったことが話された。司会の宮さんが「『キルラキル』は、1950年から60年代くらいの増村保造作品のようにロジカルでスピード感のある日本映画の印象に似ている」とい指摘すると、中島さんは「実は、ここ2年間くらい増村保造を追いかけていた」と明かした。ドライでテンポが良く、でも観た後に心に残るものがある。そんな日本の映像エンターテイメントの源流が『キルラキル』の根底に流れているという。中島さんは「人間ドラマってよく言うけど、どんなものにもドラマはあるわけで、わかりやすく主人公が悩んでいる姿を平べったくやるよりは、そんなこと分かっているから先に行こうよって思う」と語る。
そんな、意図がよく現れているのが第4話「とても不幸な朝が来た」のような人間の内面にこだわらず、テンポよくドラマが進んでゆくエピソードだろう。ひたすらハイテンションでアドレナリンが出ているキャラクターは、中島さんの生理的な快感原則に沿って作られているという。どんなに困難な状況に直面しても、くよくよ悩んだりせず前に突き進んでゆくキャラクター達は面白いだけでなく、見ていてとても気持ちがいい。

また、中島さんのエッセンスが凝縮されているのがネーミングだ。「着る(KILL)」、「裸(la)」、「斬る(KILL)」といった語呂合わせの言葉遊びから、物語の世界を押し広げてゆくのだと言う。特にキャラクターの名前は“名が体を表す”と同時に、音を耳にした時に印象に残る言葉選びになっている。例えば鬼龍院皐月の名前は、もともと「着る」を転じて「鬼龍(きりゅう)」にしようとしていた。だが、「きりゅう」だと音が流れてしまうため、音として印象に残りやすい「鬼龍院(きりゅういん)」にしたのだという。中島さんが生み出した言葉の持つ力が、画面いっぱいに強調された真っ赤な太字テロップの演出へ繋がっていったという。中島さんのインスピレーションによって生まれたアイデアが詰め込まれた結果、『キルラキル』は“なんだかよくわからない”けど面白い、魅力と勢いにあふれた作品になったのだろう。
■ファンから質問に中島さんが一問一答で回答

後半は、会場で集められた質問に中島さんが答えてゆく。「蟇郡(がまごおり)は皐月様を待っている2年間、毎日どのように生活していたのか?」や「伊織の一人称は?」など、キャラクターの細かなエピソードを知りたいと願う熱心なファンの質問に、中島さんはその場で次々と設定を考えだしては答えてゆく。「伊織の一人称はいおりんだよ」など、ジョークに富んだ返答で会場を大いに湧かせた。アニメの制作現場でもスタッフとのやりとりで新たな設定がどんどん追加されていったというから、まるでその様子を想像させるかのようだった。質問の多くは作品のキャラクターに関する内容で、本作におけるキャラクターの持つ魅力の大きさがうかがえる。
本作のキャラクターは、誰もが言い負けないことが特徴だ。その原則があるため、キャラクター同士が張り合う場面のセリフは自ずとハードルが上げられてしまう。第22話「唇よ、熱く君を語れ」で縫と流子が言い争う場面では、縫が「自分には友達がいるなんて、反吐が出るようなこといわないでね」と言う。それに対して流子は「そんなこと言うつもりはねえ。友達なんて言葉じゃおさまらねえ。もっと“わけのわかんねえもの”がいるんだよ。満艦飾マコとか鮮血とかっていう、な」と答える。この、流子が放った“わけのわからないもの”というセリフを書いた時に、中島さんは“わけのわからないもの”がこの世に満ちているからこそ、一枚布で包もうとするものに対して多様性を確保しようとする、という作品全体のテーマが見えてきたという。自分が書いたはずのキャラクターのセリフによって、表現したいと思っていたテーマが見つかるという執筆時の体験を語った。ロジックだけでは測りきれない創作時の不思議な出来事は、物語の世界をキャラクターが生きている証のように思われた。
イベントの冒頭では「皆さんの質問には真摯に答えますが、がっかりする答えしか返ってこないと思います」と宣言していた中島さんだが、軽妙なトークを繰り広げ、終始笑い声の絶えないトークショーとなった。
イベントの終了後、中島さんに本日の感想を伺った。
――まずは、イベントを終えられた感想をお聞かせ下さい。
「関西に来てくれて嬉しいです」というファンの言葉は、前日にMARUZEN&ジュンク堂書店で行ったサイン会の時にも、ずいぶん声をかけていただきました。それだけでも、こっちに来てよかったなと思いましたね。不安だったのは、どれだけの人が来てくれるのかなということだったのですが、トークイベントのチケットも完売して、サイン会の方も盛況だったので嬉しかったです。
――直接、ファンの方と対面されてどのように感じられましたか?
やはり『キルラキル』ファンの熱心さと、キャラクターを好きな人もたくさんいるけど、それと同時に、作品そのものを楽しんでくれている人がたくさんいる感じがします。それは嬉しいことですね。
――『キルラキル』の企画が立ち上げられてから、中島さん、今石監督ともに別のお仕事が入って作業が一時中断されてしまいます。その後で、作品を再開されて変化した部分はありますか?
途中で入った『仮面ライダーフォーゼ』が『キルラキル』で考えていた設定と同じ学園バトルものだったので、最初は「参ったなぁ」と思っていたんです。でも、『フォーゼ』は子ども向けの番組としての制約がありましたが、その分『キルラキル』の方では、より趣味性を強く出そうと思いました。ですので、『キルラキル』は『フォーゼ』があったことでより趣味性の反動が出た気がしますね。
――トークイベントでも話に挙がりましたが、脚本を書きながらキャラクターのセリフを思いついて、それをどのようにして脚本へと落とし込んで行かれるのでしょうか?
それはね、口で説明するのが難しいんですよねぇ。浮かぶんです、と言うしかないんです。おそらく、今まで書いてきた積み重ねも、訓練にはなっていたと思うんですけどね。舞台の劇団☆新感線の方でもそうなんですけど、まず人物のやりとりが浮かぶんです。物語を会話で描いていくのがシナリオだし、舞台では映像よりもセリフ頼みの部分が多いので、脚本をセリフで落としこんでゆくっていうことをずっとやっていたんですね。口では説明しにくいですが、そういう訓練があったからひらめいた事を作品全体につなげてゆく作業が、自然と出来るようになったんだと思います。
――舞台でもアニメでも制作現場とのコミュニケーションが重要だと思うのですが、どのような事に気をつけられましたか?
『グレンラガン』で一度やったチームですし、お互いの理解も速くてすごくコミュニケーションのキャッチボールはしやすかったです。それは、信頼できるとチームだったからっていうのはすごく大きいですね。例えば、絵の設定を作る方が出してきたデザインを見て「闘うために服を着ているのになんでこんな半裸みたいな恰好なんだ?」と思うこともありましたが、彼らがこれをカッコいいと思っているのであれば、それを作品世界の中で意味づけしてゆくのが僕の仕事だと思っています。「無理だからこっちにしましょう」ではなくて「多少無茶でも、こっちの方が面白いです」っていう作品の作り方が、劇団☆新感線でありTRIGGERだと思うんですね。そういう時は、脚本がどれだけ現場の要望に対応できるか、いい作品にしたいという想いやダイナミズムは大事にしたいと思っています。
――オリジナルで新しい企画を立ち上げる際に、今のアニメファンがどういうものを求めているか、という市場調査はされますか?
僕のチームの場合は、それをやってもあまり意味がないような気がしています。それは、最初に(『キルラキル』の)鳥羽洋典プロデューサーもおっしゃっていました。むしろ、僕と今石監督が面白いと思っていることを、どれだけの純度で出せるか。それは、間違いなくある一定の層には受け入れられるはずなので、それをどれだけ広げられるかということが重要でしたね。「観てもらえば絶対に面白い!」みたいな気持ちが僕らの中にあるので、それは思っていた以上にちゃんと伝わったんじゃないかな。今回のイベントも、男女や年齢もさまざまな方が集まってくれていたので、結果的にこの作品が幅広い層に受け入れられたのは嬉しいですね。
――書く技術は独学で学ばれたとのことですが、脚本家としてのスキルはどのようにして鍛えられたのでしょうか?
高校時代から演劇の脚本を書いていたので、書くこと自体はずっと続いているんです。会社員と同時並行だった時期は、土日や移動時間を使ったりして書いてました。常に劇団☆新感線の舞台脚本を書いていたので、勉強ではなく発表される事を目的に書いていたんですね。それで、現場に必要な技術が身について行ったのだと思います。
――アニメファンの中にも、中島さんのような脚本家に憧れる人は多いと思います。脚本家を目指している人へアドバイスはありますか?
やっぱり書き続けるしかないし、プロとしてやっていくのであれば、生活のために別の仕事をしていたとしても同時に書く気持ちをキープしていけるかが重要ですね。それは、書き続けられる意志があるかどうかだと思うし、それで仕事が忙しくなって書き続けられなくなったら、それまでだと思うんですね。そして、作品は最後まできちんと書き終わることです。最後まで書き終わらなければ書いたことになりませんので。
――総合文芸誌『ダ・ヴィンチ』のニュースサイトということで、最後に中島さんが最近読まれている本を教えて下さい。
今度半村良さんのトークイベントをやるので、彼の作品を再読しています。改めて『妖星伝』はとんでもない傑作だったとうちのめされています。最近、読んだ新しい本でいえば春日太一さんの「なぜ時代劇は滅びるのか」ですね。彼の著作はずっと気になっていたし、僕も劇団☆新感線で時代劇をやっているので読まなくてはいけないだろうなと思いました。
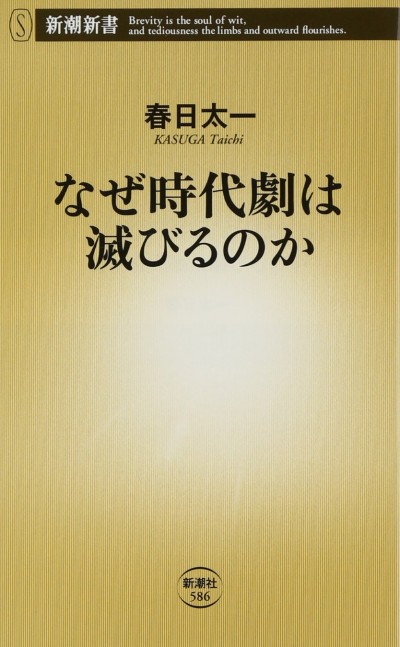
他は、川島雄三とか映画監督に関する本は好んで読んでいますね。物書きを目指している人にとっては、橋本忍さんの本が面白いと思います。いずれにせよ自分が書きたいものがあるならば、それをどうして自分が面白いと感じているのか、どこをどう面白がっているのかを考える客観的な視点はあった方がいいと思います。
『キルラキル』は中島さんと今石監督の作家性が色濃く反映されている純度の高い作品だ。どのようなアニメを作ればヒットするかを分析し、市場やニーズありきで作られる“カテゴライズされた”作品が多いなか、本作のように作り手側の趣味や主張が反映され、なおかつ多くのファンに受け入れられている作品は、オリジナルアニメでも数少ないのではないだろうか。
今回のようにTVアニメの放送終了後に地方でイベントを開催しても、作り手の新たな発言を求めて会場を満席にするほどのファンが集う。中島さんたちが100%の自信を持って生み出した作品は、その熱量を保ったまま全国のファンへ届き、放送が終了してからも深く心に残っていたようだ。中島さんいわく『キルラキル』の続編を作る予定はないとのことだが、いつかまた中島さんと今石監督のタッグによる興奮と熱気にあふれた新作に出会えることを期待したい。
取材・文=松田はる菜
【<中島さんが読んだ本>関連記事】
民放地上波で時代劇枠が消滅してしまった理由とは























