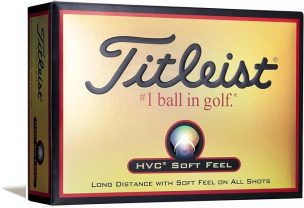戦争体験者たちの告白を、現代の10、20代が読んで考える『若者から若者への手紙』
公開日:2015/8/15
学徒看護隊として砲弾が飛び交うなか負傷兵のために駆けずり回った女性は、そのとき18歳。人体実験や細菌兵器の研究を行い〈悪魔の部隊〉と呼ばれた731部隊に志願した男性は、そのとき15歳。やがてその内実を知って苦悩することになる。派兵されたニューギニアで終戦を迎え、ジャングルを逃げまわるうちに次々と仲間を亡くして狂気の淵に立った男性は、そのとき23歳――。
戦争を知り、次世代に語り継いでくれる人たちがいなくなりつつあるといわれるいま、『若者から若者への手紙 1945←2015』(落合由利子、室田元美、北川直実/ころから)には、当時〈若者〉として国内外で戦争を体験した15人の証言が収められている。著者である写真家の落合由利子さん、ライターの室田元美さん、編集者の北川直実さんたちの試みは、10年ほど前からはじまった。
北川直実さん「戦争体験者の証言を聞いて形にして残そうと考えたきっかけは、三者三様です。私の場合は、亡き父が戦時中、航空機体学科の学生で、勤労動員令により軍の研究所に派遣され、航空機の研究開発の手伝いをしていたと聞きました。当時の若者がみなそうであったように、父もまた純粋な愛国青年として、その仕事に取り組んでいたのでしょう。戦後、父は大学で教鞭をとることになりますが、中国、韓国からの留学生を早くから積極的に受け入れ、“日本はアジアの人たちに大きな損害を与えた、これからは科学技術で交流していくことが大切だ”とくり返し話していたそうです。そこに戦争に対する反省の思いが強くこめられているのは明らかですが、一方で戦争中に何を見、何を感じてそう考えるようになったのかを父が子どもに話すことはありませんでした。聞いておけばよかった、という気持ちに後押しされて、この仕事をはじめました」
落合由利子さん「その時点で戦後60年、いまお話ししてもらわないと消えてしまう、なかったことになってしまうとわかっていながらも、それだけ重い体験を自分は受け止められるのだろうかという不安もありました。平和な時代には100人の人間に起きるような不幸が、戦争ではひとりの人間に襲いかかります。それを何人もの方から聞くとなると、自分が潰れてしまうのではないか……。でも、3人ならできるだろうと話し合って、証言者の方たちに会いにいきました。そして、重く苦しい体験ですが聞かなければよかったと思うことは一度もありませんでした。お会いできたことに感謝しながら真っ正面から向き合う形で、撮影させていただきました」
語り部として活動をしている人を訪ねたり、広島、長崎それぞれの平和記念式典に出かけていき参列している方に声をかけたりしながら、戦争体験者と出会い、証言を集めていく。そんな作業が10年の月日をかけて断続的に行われた。
室田元美さん「多い方では7、8回お話を聞きにうかがいました。聞く側が簡単にわかったような気になってしまうのは、いちばんよくないでしょうね。戦争の体験はひとりひとりみんな違うし、ひとりの人のなかでも複雑な思いが交錯していることが多いと思います」
空襲のなかを逃げまどう、長崎で被爆して4人のきょうだいを全員失う……非戦闘員として犠牲になった方たちの証言もある一方、本書には人を殺す訓練を受け、中国で一般人の殺りくに手を染めた経験もある男性(当時20歳)の告白もつづられている。
北川さん「日本人はこの戦争において被害者であったばかりでなく加害者でもあったことを伝えたいと思い、この本に加害の証言を入れることを大事にしました。こうした体験は思い出すこと自体がたいへんつらく、語られないままでいる場合がほとんどです。ほかにも、満州から引き揚げてくる際、現地の男性とのあいだに生まれた幼子を中国に残してきた女性(当時23歳)や、朝鮮半島出身で17歳のときタイの捕虜収容所で監視員の職に就き、そこで虐待をしたとして戦後、BC級戦犯となった男性の話から、加害と被害が入り混じる複雑さを感じました。それらは、そもそも歴史の表舞台に出てくることがまずないので、たいへん貴重な証言となりました」
証言者15人のうち7人の方が、本書の発売を待たずして鬼籍に入ってしまわれた。戦後70周年というタイミングもあり、「いまこそ1冊にまとめよう」と集まった落合さんたち3人の頭を悩ませたのは、「どうしたら、いまの若い人たちに届けられるのか」ということだった。
室田さん「どんな本だったら、若者たちが手に取ってくれるのか。彼らにとっては戦争自体が遠い昔の話になっていて、関心が薄いのではないか……何度も話し合いましたね。これまでにも証言集は多数出版されていますが、ただ証言を記録したものではなく、いまに〈つなげる〉1冊にして、若者たちに手渡したいと思っていました。若者というのを仮に20歳とするなら、1945年に20歳だった若者と、2015年のいま20歳になる若者との、ちょうど中間ぐらいに私たちの世代は位置しています。だから、両者の橋渡しをするのは自分たちの役目だと感じるようになりました。その方法として出てきたアイデアが若者から若者への〈手紙〉だったんですね
ひとりの戦争体験者が語った証言と、ひとりの若者がそれを読んで体験者その人に宛てて書いた手紙。本書はそのふたつの要素で構成されている。若者たちはバックグラウンドがさまざまなら、「博子ちゃん」と親しげに呼びかけたり、まるで正座して問答するように話しかけたり、手紙のスタイルもさまざまだ。
北川さん「いまの若者はメールに慣れていて手紙を書かないので、感想文を書いてもらおうという案もあったのですが、ひとりひとり証言者とじっくり向き合ってほしいと考え、それにはやはり手紙がいちばんだという結論になりました。おそらく自分に置き換え、言葉をつむぐなどの作業をそれぞれにされたんでしょうね。みなさんたった1000字の手紙のなかに、証言に対して感じたことや証言者への思いだけでなく、自分自身のこともたくさん書かれてきたので、私たちも驚きました。〈戦争〉という大きなキーワードから、平和について考えたり、不安に感じたり、それでも生きるという希望を読み取ったり、語りたいと思ったり……若者の〈いま〉を色濃く反映した本にもなったと感じています」
落合さん「撮影のため、手紙を書いた後の若者たちと会いました。おひとりにつき4時間もらって、その人の好きな場所や落ち着く場所を散歩しながら話をし、写真を撮ることで、若者の〈いま〉を受信したいと考えたんです。“手紙を書くのは大変だった”とみなさん言いました。そして自分の話もしてくれました。〈平和〉な現代であってもそれぞれがいろいろな状況を抱え、心を揺らしながら生きていることにあらためて驚かされました」
そしていま国の中枢では、若者が戦争を「遠い昔のこと」と思えなくなる動きが起きている。
北川さん「ある証言者のお孫さんは本書を手にして、“いままで漠然と〈戦争=悪〉と思っていたけれど、戦争になったら実際に何が起きるのか、なぜ〈戦争=悪〉なのかがよくわかった”とお話してくれました。一度戦争になれば、終戦になっても終わらない。その人のなかでは、生きているかぎり続くのだということを、私たちも証言者のみなさんから教えていただきました。いま国会前にたくさんの若者が集って“戦争はイヤだ!”と声をあげていますが、どうしてイヤなのかを考えるための〈生の声〉や〈生の記憶〉が、ここに詰まっています」
室田さん「みなさんあの苦しい時代を生き残ることができたから、こうして証言していただけるわけですが、実際には戦争でたくさんのものを失っています。家族、友人、恋人といったものもだけでなく、〈個〉というものが失われていくと話してくれたのは、20歳のときに召集されて戦地に赴いた男性です。それまで哲学を学び、自分はどう生きるかを追求していたのに、戦場では自分が意思を持った個人と認められなくなり、いくらでも代わりのきく道具のような存在であることがわかった、と。また、疎開先に生徒を引率していった女性教師(当時21歳)は、戦後、教育者として戦争に加担してしまったと思い至り、大きな喪失感に苛まれます。戦争は、命以外のたくさんのものを奪ってしまうものなのだということがよくわかります」
落合さん、北川さん、室田さんの3人は今後も〈手紙〉を募集するという。本書では、10~20代の若者からの手紙だったが、今後は世代を問わずに「1945年、戦争の時代を生きていた若者たちに、あなたも手紙を書いてみませんか?」と呼びかける。詳細は、特設HPをチェックしてほしい。
取材・文=三浦ゆえ