ネタの接続詞1つにもこだわる―南キャン山里が“天才”に近づくまでのストイック過ぎる道のり
公開日:2015/9/14
お笑いコンビ・南海キャンディーズ、山里亮太。かつては「キモい」「アイドルオタク」といったイメージが強かったが、いまや情報番組『スッキリ!!』『ヒルナンデス!』(日本テレビ系)から、『テラスハウス』『アウト×デラックス』(フジテレビ系)、『ナカイの窓』(日本テレビ系)まで、幅広い人気番組の進行に欠かせない存在だ。
豊富なボキャブラリーが特徴のツッコミで知られる。練りに練ったツッコミを1000パターン以上書いたメモを持ち歩き、現場の状況に合わせ、それら“テンプレート”の中から最適なツッコミを出すのだという。「実はテンプレートなど存在せず、全部アドリブ」という、“タモさんの弔辞”的都市伝説も囁かれるほど、山里のツッコミに対する評価は高い。
しかし、自らを「凡人」と称する。著書『天才になりたい』(朝日新聞出版)に、高校生のとき芸人を志してから、南海キャンディーズが世に出るまでの努力の日々を綴っている。“凡人”がいかにして天才に近づこうとしたか、そして着実に近づいたか。その道のりが記されている。
関東出身だが、お笑いの本場大阪を目指し、名門・関西大学へ進学する。大学3年になると同時に、NSC(吉本総合芸能学院)に入学。2度のコンビ結成と解散、ピン芸人を経て、“運命の女性”しずちゃんと出会う。しかし、難しいとされる男女コンビ。一筋縄ではいかなかった。紆余曲折の末、しずちゃんの面白いボケを伝えるのではなく、張り合おうとしていたのだと気づく。
忘れていた。自分がおもしろいと思うことをやる、それが変わってるというのが天才なんだ、全く天才ではない僕のような凡才でも、自分がおもしろいと思うことをやらなきゃおもしろくないんだ。その大前提を完全に見失っていた。
そこから南海キャンディーズのネタは変化していく。代表作ともいえる、「医者ネタ」の初期台本はこうだ。
山 僕ね、お医者さんになりたい
し (両手をあげおおげさに古い動きで驚く)ぷぷー
山 ……平成だよ
し じゃあちょっとやってみよう、山ちゃんお医者さんやって
山 わかった
し 私、火を怖がるサイやるから
山 メス
し(火を怖がるサイ)
山 メス
し(火を怖がるサイ)
山 だめだ、俺こんな状況生まれて初めてだ……
このネタが秀逸なのは、なんといっても、しずちゃんの「私、火を怖がるサイやるから」に対して、山里が突っ込まずに「メス」と進めるところである。意外にも、当初は「なぜ?」と突っ込んでいたという。しかし突っ込む前にお客さんが笑った。それでツッコミはいらないと考えた。
こうしたマイナーチェンジを重ね、ライブが終わるたびに取捨選択の作業をする。それをノートに書く。そこで思いついたボケを次の舞台に入れてみる。その反応を固定化していく。その繰り返し。
こういうノート、この前数えたら前のコンビからのものを入れて百冊近くあった。最終的に僕たちが初めて出たM-1のときの医者ネタは、十回以上書いてると思う。接続詞の一つまで気にするようになったのも、このノートのおかげだ。
テレビやラジオで明かされる、山里の努力家エピソードは枚挙に暇がない。自宅にカメラが潜入した際、壁に「小手先だけになってきている!」と書かれた張り紙が発見される…。長年、彼女をつくらずにいるのは、デートをしていても「他の芸人はいまごろお笑いの腕を磨いている」と考えてしまうから…。
なぜそこまでストイックになれるのか。天才になりたいから、だろうか。そもそもなぜ芸人になろうと思ったのか。「モテたいというのが最初のきっかけ」としながら、こう述べている。
入り口は明確じゃなかった。お笑い芸人になりたいという気持ちを口に出し、そのビジョンを何度か空想したことが、あいまいな夢に重みを与えてくれた。「お笑い芸人になってみようかな」は「どうしてもお笑い芸人になりたい」になっていた。
夢というと、とかく確固たるもの、というイメージがある。イチローは小学生のとき、「一流のプロ野球選手になりたい」と作文に書き、その通り実現した。夢とはそういうものだ、自分にはそんな夢なんてない、所詮は凡人なのだ…そうやって、私たちは夢を諦めてしまう。しかしそうではなく、空想や、小さな成功体験の積み重ねが“夢に重みを与えてくれた”という山里。多くの人にとって希望になる。
今年8月、格闘技の聖地・後楽園ホールでトークライブ「山里亮太の大140」を開催した。ゲストなし、休憩なしの2時間。昨今の安定したポジションからは、およそ捨て身ともいえる切り込んだトーク。一度も水を飲まず、リングの上で孤軍奮闘する様は圧巻だった。南海キャンディーズの元マネージャー片山勝三氏はこの日のライブについて、「『天才になりたい』 そう思い続ける芸人の姿が垣間見れた作品だったと思います」とツイートした。
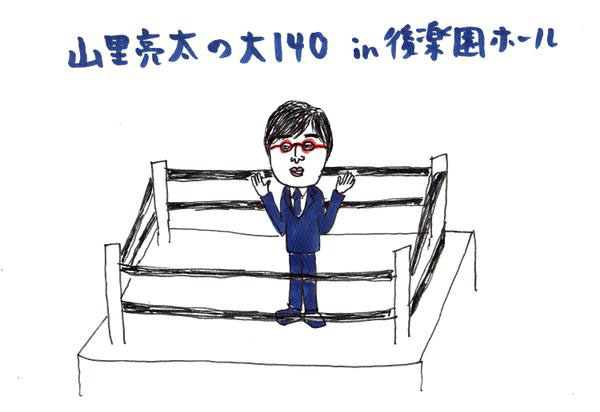
2006年。いまから9年前に出版された本書の最後は、こう締めくくられる。
この先、どのような展開が待っているかわかりませんが、辞めたいと思うことはないと思います。それは、一喜一憂の「喜」が僕にとってはいつも新鮮で、そして何よりも、今まで、また今も僕を助けてくれる人達がいるから。
文=尾崎ムギ子























