新聞社の裏側を生々しく描いた『小説 新聞社販売局』の著者・幸田泉さんインタビュー
更新日:2017/11/18
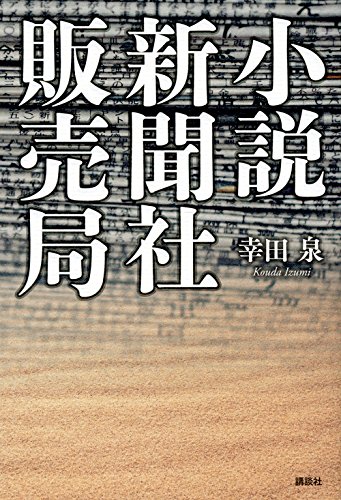
読者の目になかなかふれることはない、新聞社の裏側。いわば“暗部”ともいえる業界の内情が、創作ながら赤裸々に描かれた小説が刊行された。その名も『小説 新聞社販売局』(幸田泉/講談社)だ。主人公・神田亮一は、新聞社の花形ともいうべき編集局で記者を務めていたものの、左遷されて販売局へ異動。しかし、記者時代には目にすることのなかった新聞という業界の実態を、販売店を管轄する担当員として目の当たりにすることになる。
小説執筆の動機を綴ったエッセイで「発行部数という魔物に取り憑かれた」と新聞社を表現するのは、著者の幸田泉さんである。実は、著者自身も主人公に似た経歴を辿った方だ。1989年に全国紙へ入社して社会部の記者として活躍。その後、編集局で社会部のデスクなどを務め、2014年に退社。新聞社での最後の2年間は、販売局で勤務した。
小説では、新聞社から販売店へ一方的に送付される“押し紙”(※)の存在や、販売店を取り巻く社員の横領や裏金の存在などを、専門用語も交えてかなり生々しく描いている。小説というよりむしろ、ルポともいえるほどに迫真した物語には、どのような思いが秘められているのか。幸田さんにお話を伺った。
(※)“押し紙”とは、新聞社が、その新聞を配達する販売店に対して、必要部数を超えて押しつけているとされる新聞のことをいう。よって配達されなかった、いわゆる“残紙”が、サービス品や包み紙となっているというのだ。
部数から見えてくる新聞を取り巻く“押し紙”と“カネ”の問題
――まず、新聞という業界の実情をかなり生々しく描かれた印象を受けたのですが、正直、どこまで現実を反映されているのでしょうか。
「創作と実情が入り乱れてはいますが、例えば、根幹のテーマである“押し紙”や“残紙”という新聞販売の特殊性や、新聞社と販売店の関係性などは、できる限り詳細に描きましたし、直面している課題や問題点を網羅するようにしました」
――やはり、幸田さんが新聞社へ勤務されていた経験も反映されているんでしょうか?
「そうですね。主人公の神田と違い、実際には販売局内で後方支援の役割をする職場にいました。バブル期に入社してから、収益が右肩下がりで特にリーマンショック以降はひどくなり、疲弊し続ける現場を記者としても経験しましたが、販売局でも組織が縮小されているのを痛感しました。局内のいくつもの部署がだんだんとなくなって、私のいた職場に仕事がまとめられていました。だから、担当員の要望を聞いたり宣伝物を作るという本来の業務だけではなく、仕事の守備範囲が把握しきれないほど、いうなれば販売局の“何でも屋”のような状態でした。多岐にわたる仕事をする中で、後方支援の部署にいながらも、販売の実情が見えてきたのです」
――ご自身の「仕事の守備範囲が把握しきれないほど」とお話にありましたが、退社の理由もそこあったのですか?
「自分の仕事に対する不満というよりも、作品でも描いたような販売の実態を見て、とても疑問が膨らみました。だんだん気分が憂鬱になり、この憂鬱を抱えたまま定年まで働き続ける気にはとてもなりませんでした。早期退職する気持ちが固まりつつあった時に、上司から『編集局に戻る』という人事異動を打診されました。でも、新しい職場に異動してすぐに辞めるのもかえって会社に迷惑がかかると思い、その時点で退職の意思を伝えました」
――現場から見て、小説のテーマにもある新聞の“販売”の実態はどうなっていたのでしょうか?
「現場の後方支援をしながらも、担当員の声を聞く機会もあったんです。世間の新聞離れが進む中で担当員の仕事も様変わりし、かつてのような読者を増やすための『打って出る』仕事がなかなかできないと嘆いていました。作品でも描きましたが、販売店の積立金や会社の経費を流用したり個人の懐(ふところ)に入れるという“不祥事のデパート”のような担当員もいました。何度、注意しても繰り返すので販売局で抑えきれなくなり、会社が正式な調査に乗り出して結果的に懲戒免職となりました。当時、周りでは『小説になるよね』という冗談が飛び交っていたのも覚えています」
――部数に端を発するカネの問題が業界の“闇”として根幹に見えてきますが、読者も含めた新聞の実情をどうお考えでしょうか?
「販売にまつわる問題は一見、読者には関係ないように思えます。販売店に“押し紙”や“残紙”があったとしても、読者が困ることではない。ただ、だからこそ広く明らかにされず、放置された問題でもあったと思うんです。不良社員もいましたが、真面目に頑張っている担当員や販売店主の方もたくさん見ました。こうした人材を生かし、新聞を守るためには、新聞社の経営を支える根幹である『販売』の健全化は避けて通れないところに来ていると感じました」
――作中で「販売店にとって新聞は折り込み広告の包み紙」という言葉もありますが、購読者としては衝撃的なセリフでした。
「そのセリフは実際にベテランの販売担当社員から聞いた言葉です。販売店にとっては折り込みチラシを多く入れるほど収益の出る仕組みになっているんです。販売店が本社に支払う新聞原価代よりも、折り込みチラシの収入の方が多ければ、販売店は読者がいようがいまいが、どんどん部数を増やした方が儲かります。折り込みチラシがたくさん入った景気のいい時代に、“残紙”があまり問題視されなかったのは、こうした事情もあると思います。しかし、もはやそんな状況ではないし、やはり直近ではリーマンショックが折り込みチラシのガタッと減るきっかけでした。景気がいい時に販売店側が『部数を増やしてくれ』と本社に要望してしまい、折り込みチラシが減ったので部数を減らすよう頼んでも、新聞社は『そちらの要望で部数を増やしたんだ』となかなか応じないのが業界では一般的だと言われています。でも余分な部数を抱えて販売店の経営が悪化すれば、本社が補助金などの形で経費を使って支えるのですから、結局、本社の経営にも影響してくるのです」
――作中では販売店からの入金拒否による担当員の“立て替え”も描かれていますが、実際にあることなのでしょうか?
「販売店の入金拒否は、小説では大物販売店主が本社に警告を発する手段として登場させましたが、現実には入金拒否はそうそうあることではありません。担当員の立て替えは、販売店の経営状態が悪く本社に入金すべき金がそろわない場合に補うものなのですが、販売店が全額を入金できないという事態の背景には、新聞販売の抱える構造的な問題があります。立て替えのために何百万円も借金を作ったとか、驚くような話もありました。販売店からの集金は“入金率”というノルマがあるので、担当員は追い詰められて立て替えてしまうのだと思います。ただ同時に、それこそが担当員の金銭を巡る不祥事に繋がる温床になっています。自分のお金、会社のお金、販売店のお金の違いがだんだん分からなくなり、最悪の場合、横領のようなことにまで手を染めてしまう。『立て替えは絶対にダメ』と教育する勉強会も開かれていましたが、公称部数の水増しという問題の根幹が改善されなくてはならないと思います」
――お話を伺い、幸田さんご自身が見聞きされたものがだいぶ反映されているようにも思えますが、出版後の反響はいかがですか?
「新聞社の中では私が『暴露本を出版した』とうわさが広がっていると聞きます。でも、この小説が暴露本と言われること自体が、新聞社が闇を抱えている証拠です。そもそも新聞社で働いていても、新聞販売の仕組みを知らない人間は多いんです。事実、私も記者の頃は“作る”ことへ一心を傾けるばかりで、販売店が本社に支払う新聞の原価すら知らなかった。販売局で勤務していた当時、他局の社員から『販売のことなんて分からないから』という言葉をしばしば言われました。誰しも『販売には何かカラクリがある』ということは薄々分かっている。しかし、それを深く知りたくはないのだろうと思いました」
――作家としてデビューされる経緯はどういったものでしたか?
「小説を書きたいという気持ちはかなり以前から持っていました。記者をしていても、新聞記事には厳しい行数制限があるし、文章も一種の『型』のようなものがあるので、自分の独自の表現で好きなだけ書きまくることはできず、そのストレスもありました。退職を機に作家に転身を目指したのですが、会社を辞めたくなるぐらい強い問題意識を持った新聞販売現場を描き、処女作として仕上げたいと思いました」
――ご自身が憂うつさを抱えるほどのテーマを選ぶにあたり、葛藤はありましたか?
「本格的に執筆を始めたのは退社後でしたが、出身の新聞社や販売店の方々に『迷惑をかけないか』と考えて筆が進まない時期もありました。半年ぐらいは執筆したり、中断したりと葛藤が続いたのですが、やはりモヤモヤした気持ちは『作品にしないと晴れない』と気付きました。自分の手で書いた文章で世の中に問題提起したいし、作品として仕上げることでしか私自身がこのテーマを乗り越えて、作家として前に進む道はないんだという考えに至ったのです。心が決まってからは一気に仕上げた感じです」
――作品を通して、幸田さん自身が伝えたいと強く願った部分はどこでしょうか?
「作品の軸を担う“押し紙”や“残紙”の問題は、実は、以前から一部では指摘されていたんですね。書籍はもちろん、裁判になって公開されている話でもあるんです。ただ、これまでは鬼のような担当員が販売店をいじめるといった極端な事例が取り上げられていましたが、そもそもの発端は、新聞業界の構造的な問題であるという側面から伝えたかったという思いがあります」
――現実に、新聞の意義や未来を幸田さんご自身はどのようにお考えでしょうか?
「やはり“押し紙”や“残紙”を発端とする、発行部数水増しの問題を解決しなければ、新聞社ないし新聞業界は傾き続ける一方だと思います。でも、新聞は生き残ってほしい。なぜならば、多々あるメディアの中で、新聞は社会的弱者の声をていねいに拾い、届けるという役割を担っているからです。ややもすると弱肉強食の競争主義が支持される風潮の中で、弱者、少数派の存在を発信し続けるのが新聞の意義だと感じます」
――最後に、作品を読んで欲しい方々へのメッセージをお願いします。
「新聞に根ざす問題を身近に感じられる方々、それこそ新聞社や販売店などの関係者に読んで頂きたいです。また、新聞社を舞台にしているものの、もっと普遍的な『組織内で生きる人たちが働く意味とは何か』を訴えたくて、登場人物の心理描写などを詳細に描きました。組織で働く人の喜怒哀楽に寄り添い、応援する作品にしようと思いました。今後も現実にある問題を分かりやすく読者の方へ届けられるよう、ノンフィクションに迫る作品を描き続けたいと願います」
一般社団法人 日本新聞協会の調べによれば、新聞の発行部数はここ10年で約765万部も減ったという。2008年には1世帯あたりの配達部数も0.98部となり、今や、各家庭にとって必須のものだという価値観も薄れつつある。しかし、他者を批判しつつも「みずからの実情からは目を伏せる」という実態にも新聞の構造的な問題が潜むと幸田さんは伝えていたが、その意義を見つめ直すためにも、1人でも多くの人へ同作を手にして頂きたい。
取材・文・構成=カネコシュウヘイ
























