今も絶大な影響力を誇る「ドゥルーズ哲学」 その思想に寄り添った記念碑的名著がついに文庫化!
更新日:2017/11/16
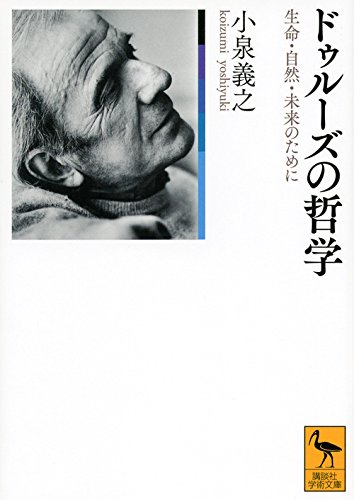
ドゥルーズの哲学に触れると、なんだか身体中の細胞たちが元気になってくるような気がする。
それが一体なんなのか明確に把握されるのを先取りして、情報をキャッチした脳が全身の細胞に何らかの朗報でも運んだのではないかと思われるような、そんな感覚になってくるのだ。『ドゥルーズの哲学 生命・自然・未来のために』(小泉義之/講談社)を読むと、どうしてそのような感覚に至るのか、その理由がわかってくる。
本書がはじめて書籍というかたちでこの世に生み出されたのは、今から約15年前の2000年。
著者によると、その頃の日本における哲学研究の現場では、ドゥルーズ哲学の魂の部分は消失しかけていたという。ドゥルーズは自らの全著作を「生命論」にまつわるものだとしているが、その重要なポイントが、日本のドゥルーズ研究には欠けていた。そのため、「私とは何か」「自己とは何か」という問いに拘泥し、自分が生物だという現実を取り逃がし、旧来の自然観や人間観を墨守し続けていたのだ。
そのような状況に対抗して書かれたのが本書ということになり、この「生命論」であるという前提が本書の言葉たちをまとめ、貫き、鳴り響いている。その理由は、来るべき「未来の哲学」は、そこからしか人間と世界のつながりを信じるという扉を開くことができないからだ。
ニューアカの時代、1980年代には浅田彰氏の紹介などによって、新しい時代にフィットした思想と倫理の源泉として人気を集めた20世紀フランスの哲学者、ジル・ドゥルーズ。
その残された業績の影響は現在でも波及し続けており、例えば日本では、本書の著者である小泉義之氏をはじめとして、多くのメディアなどで活動する気鋭の哲学者、國分功一郎氏や千葉雅也氏なども、その哲学の研究者として活躍している。
この巨大な情報の束、力の発源地ともいえるドゥルーズ哲学の最重要の問いは、「差異はどこからやってくるのか」というもの。そして彼は、何かと何かが違うという差異の生まれる「場と力」がつくる運動と、新しい姿の生命が生み出されていく運動を、同じ原理に基づくものとして捉えている。
その原理を肯定することによって、ドゥルーズは生命という存在やそこに潜在している「力」徹底的に肯定している。そして、「生命の進化を肯定することだけが、ニヒリズムを越えていくための倫理」だと喝破しているのだ。また、特定の秩序やシステムを維持するための倫理や道徳が、その生命の「力」を貶めてしまっているとまで展開している。
既存のシステムから逸脱し、新たな異なる存在、生物を生み出していく力の源泉のありかとその原理への「信」が、ドゥルーズ哲学の根幹には横たわっている。その地点から、全ての言葉は肯定の地平へと向かっていくのだ。
新しく生み出されたものをただ肯定していくこと。それらを殺めないこと。アニミズムとマテリアリズムの融合。その思想は、万物が仏性を宿している、という私たちにも馴染みぶかい思想にも重なりあい響きあい、来るべき「未来の哲学」へと開かれていく。
生成消滅する人間はすべて無垢でしかありえず、万物の生成消滅もまた、無垢でしかありえない。生命に潜在する力を加速し、新しいものを生み出すことを肯定していくこと。それは生命に対する信仰告白でもある、と本書では述べられている。
その先にあるのは、人間と世界の間にある絆を信じることだ。
ドゥルーズはその著作のなかで、自然哲学や生命哲学を通じて、その信仰を歌いあげた。生きることは実験であり、生物は解けない問いの中を命がけで生きる存在。潜在する「力」とその肯定が鳴り響いているこの場所で、ただそこに「ある」こと自体が、肯定と問いの地平の海を漂っていることでもあるのだ。
その海には新しい倫理、「未来の哲学」が顔を覗かせている。本書を読むことは、その顔と相対することに等しい。以前読んだことがある人でも、もしその顔を上手く思いだせないのなら、この文庫化という出来事をきっかけに、再び手にとってみてはいかがだろうか。
文=中川康雄
























