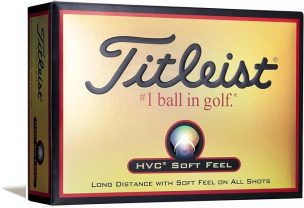全世界300万部の児童書『ワンダー』 ―“特別な顔”を持つ少年が教えてくれる世界の真実とは?
更新日:2017/11/16

昨年の終わり、電車内で、顔に障害がある女性を無断撮影し、SNSに投稿したとして、17歳の女子高生が書類送検されるというニュースが流れた。彼女は「笑い止まんない、死ぬ」とコメントを付けていたそうだが、本当に死んでしまえばいいと思うほどに、腹立たしく、そして、理解しがたいニュースだった。
清廉潔白な人生だとは言わないが、にらめっこのような遊びを除いて、私は人の顔を見ただけで、笑いがこみ上げたことなど一度もない。彼女は、なにがそんなに可笑しかったのだろう? 彼女の目に映った“笑える顔”とはどんなだろう? 児童小説『ワンダー』(R.J.パラシオ/ほるぷ出版)を手がかりに考えてみたい。
遺伝子疾患により“顔に重度の障害を持って生まれた少年”オーガストは、10歳にして初めて一般の小学校に通うことになる。その“特別な顔”のせいでいじめに遭ったり、奇異な目で見られたりする中で、家族や先生・親友たちと心から信頼関係を築き、いつしか学園一の愛されキャラに成長する――これが、『ワンダー』のあらすじ。
オーガストの顔は、生まれながらにして特別だ。顔の骨が正しく形成されないまま生まれたために、目は通常の位置より3センチも下にあり、左右の目の高さが違う。左目は飛び出し、眉毛もまつ毛もなく、耳のあるべき場所はへこみ、頬骨はなく、鼻から口にかけて口蓋裂を縫い合わせた跡があり……と、映画『エレファント・マン』をより過酷にしたような状況で、児童書にしてはかなり特殊な主人公設定だろう。
「一人の少年が、顔に対するコンプレックスを乗り越える話」であり、子供に障害のことを考えさせる「教科書」として良さそうな本だと感じるが、「障害を乗り越え自らの生き方を見つける人々」の物語は他にもある。それでも本書が全世界で300万部を超え、子供のみならず、多くの大人の心を打つ理由はどこにあるのだろうか?
それは、著者のパラシオ氏が、この物語を書くきっかけとなった「数年前の事件」にあった。詳細は、「MARUZEN&JUNKUDOネットストア」内の特設ページをご覧いただきたいが、パラシオ氏が子供たちと出かけたとき、本書の主人公・オーガストのように、頭部の骨格に障害のある少女と出くわした。3歳だった娘が少女を見て怯え、泣き出した。パラシオ氏は、少女を傷つけたくないと、娘の乗ったベビーカーを遠ざけた。すると、少女の母親は「そろそろ行かなくちゃね」と穏やかに告げ、去っていった。
パラシオ氏は、自分がどうすべきだったのかを考え、その親子がきっと繰り返し経験してきた日々を思い、母親として自分の子供たちに何をどう教えるべきだったのか……「ジロジロ見ちゃだめ」と教えることが正しいのか? その末に出した答えが「あの母親に話しかけるべきだった」「少女のことを怖がることなどひとつもないと教えてあげるべきだった」。そして、彼女は『ワンダー』を書き始めた。あの日、母親として自分の子供に教えてやれなかったことを伝えるために。
障害を持つ子と母親の気持ち、その親子を見て泣いた娘を持つ母親の立場、「見られる側」と「見る側」の2つの視点を抱いて、パラシオ氏は『ワンダー』を書いたのだろう。それは、この物語が、主人公のオーガストの視点だけではなく、姉、友人2人、姉の恋人と友人――オーガストを取り巻く人々の視点(一人称)で書かれていることからも明らかだ。そこには、時に残酷で、けれど正直な「障害を持つ少年」に抱く周囲の人々の感情がつづられていて、「ただの良かった話」に落ちていない。
たとえば、第2章では、オーガストの姉・ヴィアの「2つの思い」が描かれている。障害を持った弟の状況を理解し、自分に起こる不幸を「小さなこと」だとし、両親が弟にかかりきりになることもヴィアは姉として受け止めている。弟の顔を「気持ち悪い」と言う人がいれば怒鳴って追い払い、弟を守る。そんな“賢く優しい姉”である一方で、弟から離れて祖母の家で、思う存分に甘えられる4週間を過ごして帰宅した瞬間は、弟に「驚愕、嫌悪、恐怖」を抱いてしまう。祖母もまた、オーガストを愛していると前置きしながら、「秘密」をヴィアに打ち明ける。
「おばあちゃんにはヴィアが一番だってこと、忘れないでちょうだい」「おまえはわたしのすべてなんだよ。わかるかい。おまえはわたしのすべて」
祖母の告白を受けた孫娘のヴィアは、その裏にある悲しみを察する。
よくわかった。それに、なぜ秘密なのかもわかった。おばあちゃんがひいきするわけにはいかないもの。だれでもわかりきってることだ。でも、おばあちゃんが死んでから、わたしはその秘密にしがみついて、毛布みたいにくるまっている。
ここを読んで、私は本書が大人の読者の心を打つ理由がわかった。当事者にならないと見落としてしまいがちだが、障害を持つ人がいて、その人が苦しみや悲しみを抱いているのなら、取り巻く家族や友人たちだって、愛情や理性だけでは割り切れない複雑な想いを抱いて生きている。葛藤や戸惑いがあって当然だ。それを抉る作品は思いのほか少ない。
また、最後までオーガストを嫌悪し、認めないクラスメイトやその母親も描かれる。人の優しさや「差別は良くない」という理念では片付かない、残念な現実からも目をそらさない。
そのうえで「あなたはどうする?」と、パラシオ氏は問いかけてくる。障害を抱えるオーガストの気持ちも、その家族の思いも、第三者として関わるときの戸惑いも、すべての登場人物の立場に、読者自身が立ち、共感できる物語が『ワンダー』にはつづられている。だから、本書は人々の心を打つのだ。
“特別な顔を持つ少年”オーガストは、1年間の学園生活を経て、ひとつのハッピーエンドを迎える。はじめは「恐怖」や「差別」の対象であった“特別な顔”は、仲間たちに“当たり前の顔”として受け入れられるようになる――オーガストの顔は、物語のはじめから終わりまで同じなのに。まさに、Wonder。
そこに、私たちが見ている世界の真実があるのではないだろうか? 人が見ている世界は、その人の心が映し出された鏡なのだ。件の女子高生が笑った顔は、彼女自身の顔だった。
文=水陶マコト