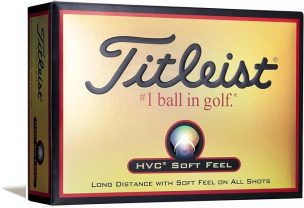死者が遺した「故人サイト」にある生々しさ―古田雄介さんインタビュー【前編】
更新日:2016/2/24

TwitterやFacebook、mixiなどに書いた日記やシェアした記事、日々の出来事や思いを綴ったブログの文章、InstagramやLINEに残している膨大なコメントや写真などが「自分の死後」にどうなるか、考えたことがあるだろうか? ネット上に死後も残る「遺物」について、死生や終活問題をライフワークとし、ネット上を漂い続けるサイトを集めた『故人サイト 亡くなった人が残していったホームページ達』(社会評論社)の著者である古田雄介さんにお話を伺った。

古田雄介
ふるた・ゆうすけ 1977年、愛知県名古屋市生まれ。ゼネコン、葬儀社、編集プロダクションを経てフリー記者となる。著書に『中の人 ネット界のトップスター26人の素顔』(KADOKAWA)、『ウィキペディアで何が起こっているのか 変わり始めるソーシャルメディア信仰』(山本まさき氏との共著/オーム社)など。現在、産経デジタル「終活WEBソナエ」で「死後のインターネット」を連載中。
日常や感情表現がそのままの形で残っている「故人サイト」
幼いころから「死」に興味を持ち、闘病記など死生観についての本をよく読んでいたという古田さんは、5年ほど前から亡くなった人が残したサイトを調べ始めたという。管理人の死後もネットを漂い続けるものには「特有の惹かれる要素がある」という。
「本として出版されるような闘病記には、闘病した本人が読者に読んでもらうという意識の他に、編集者や家族などいろんな目が入りますよね。それによって本の完成度は高まるんですが、インターネット上の闘病記にはプライベートな日記の延長線上のようなものもあって、出版するならカットするであろう日常の話やネガティブな感情表現がそのままの形で残っていたりします。だからこそリアリティがあり、距離感が非常に近い。生きているときに発した言葉がそのまま漫画の『吹き出し』みたいになって、その人が去った後もずっと残り続けているような感じがあるんです」
時に感情が揺れ動いて死を恐れることもあるが、諦観から死を受け入れようとする日もある。あるいは今までまったく誤字脱字のなかった人が、ある時を境に雑になったり、文章が短くなったりする…そうしたことが「本とは違う特有なこと」という古田さん。しかし死期が迫る中でも、こうした感情は親しい人へ出しにくいものだ。
「肉親だったり近い関係だからこそ、照れがあったりそれまでに培ってきた人間関係が邪魔をして、深い話ができないということもあるんですよね。本人がどう考えているのか聞いてみたい、でもショックを受けたり怒るかもしれない、と考えて聞くのをやめてしまうんです。しかしインターネット上の言葉は無遠慮に見ることができる。例えばある人がガン告知から1年後に『あの時の□□からの◯◯という言葉はショックだった』と書いていたら、それを読んで考えることができる。そういう意味で、ネットにはリアルとは別の有利さがあると思うんです」
故人サイトの平均寿命は約5年
本書は見開き2ページで、そのサイトがどんな内容を扱い、管理人はなぜ亡くなったのか、そして死後はどのような状態になっているのかを6つのタイプに分類して紹介している。死の予兆がまったくない「突然停止したサイト」、本人は気づいていない(または表に出していない)が死の匂いがする「死の予兆が隠れたサイト」、病気と死に向き合った「闘病を綴ったサイト」、余命幾ばくもないことを覚悟した「辞世を残したサイト」、自殺願望が感じられる「自ら死に向かったサイト」、遺族や近しい人が運営を続ける「引き継がれたサイト 追悼のサイト」があり、古田さんはこれらを見ることで「死はインターネットで学べる」という。
「見開き2ページではすべてを伝えきれないところがあるので、“この人、すごく思索したんだな”などと興味を持ったら、アクセスしてみてほしいですね。“死に様”があるということは、その人の“生き様”が残っていることの裏返しであり、その人の人生を真摯なスタンスで読み込むことは決して非礼なことではなく、文章に共感するのはいいことだと思うんです。ただその時、サイトに『感動しました』というようなコメントを安易に書かないようにしてもらいたいんです。故人が残していったサイトを見ることは遺構に立ち寄るようなもので、そこに落書きしちゃいけないのは最低限のマナーですよね。もし引き継いでやっている方がいるのであれば、ダイレクトメールなど公にならない場で連絡するようにして、心ないコメントが残ってしまう状況は避けてほしいと思います」
ネット上のサイトも現実の墓と同じく、きちんと手入れをして誰かが管理していかないと荒れてしまうという。『故人サイト』に掲載されているサイトも荒れ放題のもの、遺族が引き継いでいるものなど様々だ。
「2006年くらいにブログブームがあったのですが、当時は無料のレンタルスペースを使っていたものが多く、その後それを運営していた企業も潰れたり方向転換したりして、今はもう残っていないものが多いんです。平均的に見たら、サイトは数年から5年くらい残っているのが普通、10年後に残っていたらレアで、20年後はほとんどない、というのが現状だと思います。だからインターネット上って意外と半永久的じゃないんですよ。ブログブーム以降はmixi、Facebook、TwitterというSNSがたくさん出てきました。こうしたものは運営している側がなくならない限り、続いていくものです。しかしLINEが出てきてからクローズドな交流の場も増えているので、全公開のまま無防備に放置される事例は今後減っていくかもしれません」
死を「フラット」に紹介する意義
遺影タブレットが表紙の『故人サイト』にギョッとする人もいるだろう。それは「死」が触れてはいけない非日常のものである、と思っているからだ。
「亡くなった人の悪口を言わないとか死を深刻に受け止めたりするのって、日本人の美学としてあるじゃないですか。逆に死は怖くてよくわからないから下世話に楽しむ、という両極端な向き合い方もある。だけど私は、その真ん中で行きたかったんです。死んだら誰もが素晴らしい、二階級特進だというようなフィルターをかけて奉る感じにせず、一方で怖いとか心霊スポットに訪れるような下世話な興味からも追求しないスタンスを固めた視点は、大切な人を亡くしたらどうするか、どう死の恐怖と向き合ったのかという思索の妨げになってしまうところがある。なのでそのままの状態でネットに残っているものを、フラットに紹介するのが一番フェアであろうと考えているんです。その人が何を考え、どんな環境で、どんなプロセスを経たのかを深く追える材料がネット上に無料で全公開で存在している。そうした事実だけでも知ってもらって、あとは各自に判断してもらう。それが良いと考えました」
「今って普通に生きていると死は隠れているもので、もし誰かが死ぬところを見たらすごいものを見てしまったみたいなことになってしまう。かといって自分の肉親がちょっとずつ衰えていって、最後に眠るように息を引き取るという死のプロセスを学ぶ機会も少ない」という古田さんの言葉通り、厚生労働省の人口動態統計の「医療機関における死亡割合の年次推移」によると、1951年に亡くなった人の在宅死の割合は80%超、医療機関での死は10%を少し超えるくらいだった。それが1975~6年頃を境に入れ替わり、2000年代に入ると80%以上の人が医療機関で、10%を少し超えるほどの人が自宅で死を迎えるという完全な逆転現象が起きている。
「50年前に比べると、日本人と死の距離って広がっているんですよ。今、政府が『自宅で看取り』を進める方向で動いてますけど、核家族化が進み、病人が療養するための部屋が用意できない住宅事情など複合的な要素もあって、たぶん主流にはならないでしょう。でも机にいながらパソコンなどで検索するだけで『精神の死』には出合える。それを再認識してもらうことが『死はインターネットで学べる』という本書の目的なんです」
【後編】では、今年1月に起きた軽井沢スキーバス横転事故で亡くなった被害者の顔写真をFacebookなどから転載することがなぜ問題視されたのか、増え続けるネット上やデバイス上に残されるデジタル遺品とどう付き合っていくべきかについて考えていく。
⇒【後編はこちら】「隠しフォルダのエロ画像」よりも心配すべきこと ブログ、SNS…、死後あなたの書き込みはどうなる?―古田雄介さんインタビュー
取材・文=成田全(ナリタタモツ)