「認知症」の残薬、年間500億円以上! 患者をさらに蝕む不適切な処方への警鐘
公開日:2016/5/24
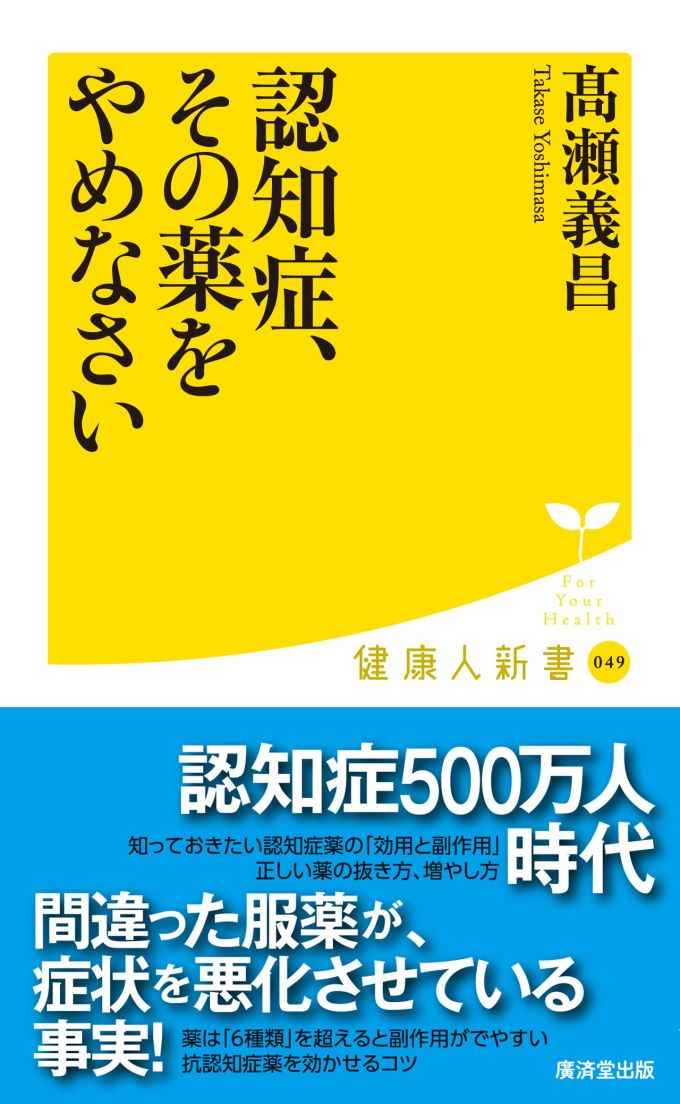
認知症は今や、誰にとっても身近な病気になった。2015年1月に発表された政府の国家戦略案、「認知症施策推進総合戦略」(新オレンジプラン)によると、今後、認知症患者数は2025年には700万人にも達すると言われている。だが、それ以前の厚生労働省研究班の発表によると、2012年の時点ですでに認知症患者数は462万人。認知症予備群ともいえる軽度認知障害(MCI)の人は約400万人と予測されている。つまり、2012年の時点で認知症とそれに準ずる人は800万人を超えているのだ。これは高齢者の約4人に1人の割合となる。
4分の1といえば、かなりの確率だ。当たり前だが、宝くじで一等が当たる確率よりもはるかに高い。それ以上に、6等の当たる確率が1/10なのだから、それよりも高いと考えれば、この数字がいかにとんでもないものかわかるというもの。認知症は身近な病気どころではない。認知症になって当たり前の時代がすでに迫ってきているのだ。
認知症を発症し、これまでの思い出や記憶がなくなっていくことの恐怖は、想像はできても体験した者にしかわかるまい。だが高齢者介護の現場で働いていれば、それよりも恐れることがあることを知っている。BPSD、もしくは周辺症状と呼ばれる、認知症に付随して現れる症状のことだ。
認知症によって、すべて の人に現れる症状がある。今したことを忘れてしまう記憶障害や、自分がどこにいるのかわからなくなる見当識障害。そして服の着方やご飯の食べ方がわからなくなる失行など。これらをまとめて、中核症状と呼ばれている。
一方、人によっては現れない、もしくは全く異なる様相を呈する症状もある。自分が財布をしまった場所を忘れて盗まれたと訴える物盗られ妄想、家から出て帰れなくなってしまう徘徊など。これら中核症状に付随して発生するものをBPSDと呼ぶ(以前は周辺症状と呼ばれていた)。家族や介護者を疲弊させ、家族の関係を崩してしまうのはこちらが原因だ。
『認知症、その薬をやめなさい』(高瀬義昌/廣済堂出版)は、そんなBPSDに薬の面から焦点を当てた一冊だ。著者の高瀬氏は長年高齢者介護の現場で、認知症を患う方々を見てきたスペシャリスト。2004年に開院以来、1500人近い患者を診ており、現在も300人どの認知症患者を抱えている。著者によると、「認知症の治療は薬1.5割、ケアが8.5割」だという。なんだ、薬の割合は少ないじゃないか、と言われるかもしれないが、そうではない。認知症患者のBPSDの中には、薬の飲み過ぎや不適切な処方によって悪化しているものが少なくない、と著者は指摘している。
本書の中では20種類以上の薬を飲んでいた患者が、整理して6種類ほどに減らすことで徘徊や暴力行為がなくなった例や、12種類の薬を、必要最低限にすることで幻覚や抑うつ状態が改善した例が挙げられている。それなのに、なぜ薬が1.5割でケアが8.5割なのだろう? 中核症状が認知症を患うすべて の人に現れるのに対し、BPSDは現れる人とそうでない人が存在する。その差は周囲の人のケアの差だ、と著者は言う。認知症になった人を疎んじるのではなく、ごく普通の人として扱うこと。そうすれば、多くの家族を悩ませているBPSDは、完全になくすことはできなくとも、和らげることができる。そして薬の調節をすることで、少しでも手助けをすることが、医者としての役割だと著者は考えているようだ。
また、現在の高齢者が陥りがちな、多剤併用の弊害がさまざまな角度から語られている。認知症患者に対する悪影響だけでなく、薬の飲み残しによる残薬が年間で500億円以上にも上るといった点まで。さらに、認知症治療の分野が未発達で、専門医の数がまだまだ少ないことなども指摘している。
本書で指摘されている問題点は、一朝一夕で解決するものではない。薬を処方している医師だけでなく、実際に薬を渡す薬剤師、本人や家族。そして私たち。多くの人が問題を直視し、解決しようと具体的な行動を起こして初めて、薬によって苦しむ認知症患者は減っていくだろう。そしてそうなった暁には、認知症患者の生活の質(QOL)を左右するのは、ケアであり、介護する人の知識や技術が、これまで以上に重要性を増すことだろう。
文=A.Nancy
























