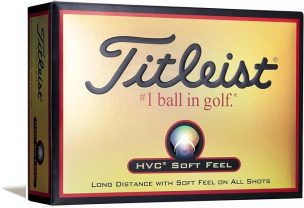時間を作るには寝なければいい!? 『君の名は。』プロデューサーで小説家、川村元気が寝る間も惜しんで小説を書く理由/[対談]川村元気×高山一実(乃木坂46)
公開日:2017/3/6

雑誌『ダ・ヴィンチ』の人気連載「乃木坂活字部!」のWEB出張版です。今回は現役アイドルで小説を連載中の乃木坂46・高山一実さんが、映画『君の名は。』など数々のヒット作を手掛ける映画プロデューサーで小説家の川村元気さんと対面。川村さんにとって初の恋愛小説『四月になれば彼女は』の執筆秘話を中心に、小説のテーマである恋愛論や、多忙な川村さんの創作術に迫ります。
「愛を終わらせない方法はひとつしかない。それは……」
高山一実さん(以下、高山):『四月になれば彼女は』は、本当に久しぶりに、周りに人がいない状況で最後まで読みたいと思う小説でした。
川村元気さん(以下、川村):そのこころは?
高山:そのこころは!?(笑) 「恋愛って何だろう?」ってことを登場人物たちが正直に悩んで悩んで、その思いの丈をぶつけている小説じゃないですか。読み終えた後で、ノートに感想文をメモしたのは初めてだったんですよ。これからもし自分が素敵な人に出会ったら、この本をあげたいなって思いました。
川村:高山さん、それ男サイドからしたら結構なプレッシャーですよ(笑)。
高山:本当ですか!? えっ、追い詰められちゃう?
川村:そうそう。わりと女性は素直にこの話を受け止める人が多いんですけど、男性の読者は身につまされたりとか、追い詰められがちなんですよ。というのも、女性のキャラクターが4人出てくるじゃないですか。あと、ゲイの男の子が1人。この5人はみんなそれぞれちゃんと恋愛に対して向き合っているんだけど、主人公の藤代という男だけが逃げ続けている。でも、あれが男子のマス(多数派)なんです。この本を渡された男子は、高山さんに「逃げるなよ」って間接的に言われた気がすると思いますよ。
高山:え~!! そっかぁ……。
川村:今ぱっと目に入ったんだけど、持ってきてくれた本にたくさん折り目がついてますよね。
高山:はい。気になった台詞だったり、素敵な表現だなと感じたページを折っていったら、いっぱいになりました。
川村:明らかに、後半に折り目がありますよね(笑)。
高山:前半は、フジ(藤代)が大学時代の甘酸っぱい初恋の思い出を振り返るじゃないですか。それがすごく楽しかったんです。でも、ぐさっと突き刺さってきたのはやっぱり後半でした。
川村:どんな台詞が気になりました? すっごい興味ある。22歳が何に引っかかっているか。
高山:いっぱいあるんですけど……一番突き刺さったのは、「愛を終わらせない方法はひとつしかない。それは手に入れないことだ」(196ページ)。これだ~って思ったのと同時に、本当につらかったです(笑)。
川村:この小説を読んでくれた周りの俳優に「一番好きなセリフは何でした?」って聞くと、たいていそれが挙がるんですよ。そっちの業界にいる人にとっては、何かグッとくるものがあるんでしょうね。基本、恋愛しちゃいけない世界だったりするじゃないですか、アイドルなんて特にそうで。現実よりも、ファンタジーのほうが強いんだよね、やっぱり。
みんなが思っているけれどまだ言葉にしていないもの
高山:この小説は、恋愛をすごく大切なものだと捉えてる方が書かれたのかなと思ったんですが、川村さんは恋愛についてどうお考えですか?
川村:僕自身は本来、すごく重い人間なはずなんですよ。学生時代は好きな人のために泣いたり、嫉妬心で夜眠れなかったりしていたんです。でも、社会人になってたったの10年でそういう気持ちがスコンと自分の中から抜け落ちて、昔の自分と比べたら別人みたいになっている。その現実に気づいた時に、気持ち悪いなって思ったんですよ。もしかして、僕と同じような人は結構いるんじゃないかなと思って100人くらい取材してみたら……。
高山:えっ、100人!!!!!
川村:いろんな人にコイバナを聞きまくりましたよ(笑)。そうしたら、みんな同じような気分を持っていたんです。「それはなぜなんだろう?」と疑問に思ったのが、この小説の出発点なんですよ。僕にとって小説を書くことは、卒論みたいなものなんですね。自分自身が切実に知りたいし悩んでいる問題を、取材したり仮説を組み立てたりしながら、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかって考えて形にしていく。自分が知りたいことを知るために書くっていう、そういう感じなんです。それをやっていくと、自分にしか書けないものが出てくるんじゃないかって思うんですよ。
高山:私も小説を書かせていただいているんですが……。
川村:読みましたよ、『トラペジウム』。「東西南北」でそれぞれ一番の美人を見つけてアイドルグループを作るっていうアイデアはキャッチーだし、話の運びも次が気になる感じでよく練られていて、良かったですよ。
高山:本当ですか!? でも、書いていると「これって誰しもが思ってることなんじゃないかな?」って自信がなくなってしまって。当たり前のことを当たり前に書いているだけで、川村さんのおっしゃる「自分にしか書けないもの」が私にはないなぁ、と思いながら書いているんです。
川村:誰も思いついてないことを書いたって面白くないんですよ。それを書いても「へぇ~そんな考え方があるんだ」って、「へぇ~」で終わっちゃう。むしろ、みんながおんなじことを思ってるのに、まだうまく表現されていないことを書かなければいけないと思うんですよ、我々は。
高山:なるほど……もっと具体的に教えていただけませんか!?
川村:例えば、さっき言った「大人になると恋愛感情がなくなっちゃってるな」って、みんなうっすら思ってるんだけど、はっきり言わないんですよね、不思議と。世の中って実はそういうことだらけで。自分が思ってることは、みんなもきっと思ってる。だけど、なぜか誰も書いてないよね、言葉にしてないよねってことを書くのが、僕たちの仕事だと思うんですよ。
高山:確かに、川村さんの小説で個人的に印象に残ったのは、『魔女の宅急便』のジジのエピソードだったんです。ジジがしゃべれなくなった時に寂しくなった気持ちって、なんとなくは思っていたけど誰にも言わずにいた気持ちで。それを彼女の言葉で書いてくれていて……。共感できたことがすごく嬉しくて、印象に残っています。
川村:そこを指摘してくれるのは嬉しいですね。僕もまったく同じで、初めて『魔女の宅急便』を観た時に、ジジがしゃべらなくなったことがものすごくショックで。でも、大人になって改めて観た時に、「あぁ、ジジは愛を手に入れたから言葉を失ったんだ」って思ったんですよ。みんなうっすら感じていたことだけど、言葉にされることで、初めてちゃんと自分の感情に形を与えることができた。そういう箇所をいくつ作れるのかが、勝負どころだと思うんです。
東京の人って、恋愛が終わる瞬間を見ながら生きている
川村:今回の小説を書いてまずいなと思ったのは、主人公のモデルが僕だと思われてるんですよね。ここまで薄情な奴じゃない(笑)。
高山:でも、フジっていろんな人から好かれてるじゃないですか。その理由はちょっと分かる気がします。自分の感情を隠して、ちょっと冷めてるふうに見える人がカッコよく見える世の中だからじゃないかなあって。大人になると、みんな感情を隠したいって思うんですかね? フジの婚約者の弥生さんは、以前は相手に尽くして尽くしてっていう感じだったけど、だんだん尽くさないほうがいいのかなって思って心を閉じてしまった。大人の恋愛ってそういう感じなのかな、だとしたらそれってすごく寂しいなと思ってしまいました。
川村:それって、面白くもなんともないよね。自分の感情を隠してる人ばっかりの世界なんて。
高山:……私事なんですけど、お正月に実家がある千葉へ帰った時に、昔からの友だちカップルに会ったんです。彼氏が最近買った新車の自慢をするんですけど、車のナンバーが記念日だったんですよ、二人が付き合った記念の。それを見て私、「えっ!?」と思っちゃったんです。
川村:その反応が普通ですよね。
高山:それはたぶん、私が東京に出てきたからで。東京の人って、恋愛が終わる瞬間を見ながら生きている感じがするんです。心配しちゃったんですよ、「別れた時どうするの?」って。でも、この小説を読ませていただいてからあのナンバープレートを振り返ったら、「あれは愛だ」と思い直しました。
川村:愛ですよ。だからジョニー・デップも、恋人の名前を入れ墨しちゃったんですよ。そういうのを馬鹿にする風潮ってあるじゃないですか。「ナンバーを記念日にしちゃってんの? カッコ悪い~」ってカフェかなんかで半笑いしてる人たちと、記念日のナンバーの車に乗ってディズニーランドに出掛けている人たちとで、どっちが幸せかっていったら答えは明らかじゃないですか。
高山:ディズニーランドのほう。
川村:絶対そっちのほうが幸せですよ。俺たちは幸せになるために生きてるんじゃないの、って思いますね。そこには、高山さんがおっしゃったように東京の問題、都市の問題がある。実は今回、海外からの翻訳出版のオファーがとてもたくさん来たんですよ。ソウルでも北京でもパリでも、「ラブレス」って呼ばれるような問題が起きているみたいなんですよね。そういう現実を、どう見るか。自分自身はどうしたいのか。
高山:男の人がカノジョのことを友達とかよりも大切にしていると、「一途」って言われるじゃないですか。でも女の人がカレシのことをすごく大切にしていると、「重い」って言われるのがおかしいなって思うんですよ。
川村:それも都市のせいかもね。 ていうか高山さんの話、とても面白いですね(笑)。
自分では思いつかないようなことが現実にはいっぱいある
川村:僕、昼間は映画をずっと作っているんです。
高山:もちろん知っています(笑)。川村さんがプロデュースされた映画は、どれも大ヒット作です。
川村:いや、それは『君の名は。』の印象に引っ張られてるかも(笑)。ただ忙しいことは確かで、去年は映画を4本作ったんです。そっちの仕事を終えてから、深夜2時から朝5時くらいまでで書くっていう生活だったんですね。
高山:いつ寝てるんですか!?
川村:えっと、それに関しては秋元康さんから言われたんですけど、「寝なくていい」って。
高山:えーーー!!
川村:「愛を終わらせない方法はひとつしかない。それは手に入れないことだ」よりもタフな、秋元康さんの名言ですね。「時間を増やす方法はひとつしかない。それは寝ないことだ」。高山さんも、アイドルの仕事が忙しいでしょう? 小説はいつ書いてるんですか。
高山:私は、次の日がゆったりめのスケジュールの時に、朝まで書いてます。毎日早朝から夜までっていう仕事が続く時は、空き時間にポメラを持っていって、現場で書いています。毎日それをやっちゃうとメンバーに「作家気取ってるな~」って思われるかもしれないので、ポメラを出すタイミングには気をつけています(笑)。
川村:僕も撮影の合間の休憩時とかに書きますね。大変なことも多いですけど、小説以外の世界と繋がっていることが、僕とか高山さんみたいな人の武器だと思うんですよ。専業作家じゃ書けないものが書けるはずです。こんなに世間にまみれながら書いている小説家って、なかなかいないですから。
高山:私は最初、専業ではない自分なんかが書くのは申し訳ないという気持ちがあったんです。でも、『ダ・ヴィンチ』さんの連載でいろいろな作家さんとお話しさせていただいたら、みなさんが応援してくださるんですよ。「兼業だからこそ書けることがあると思います」って。だから今は開き直って、私なりの小説を作り上げられるように頑張りたいと思っています。
川村:高山さんの小説の中に、ロボコンの試合が出てきますよね。取材はしたの?
高山:ロボコンは、担当さんの知り合いの方にやってらっしゃる方がいて、電話で取材させていただきました。
川村:その知り合いに頼んで、高専の部室とか行かせてもらった方がいいと思う。僕は『四月になれば彼女は』の取材で、慶應大学の写真部に行ったんですね。そうしたら「僕はペンタックスのカメラしか使いません」ってしゃべってる男がいて。「一線を画す名機。その紛れもない素晴らしさ」(ペンタックスのカメラのキャッチコピー)って英語で書いてあるTシャツ着てたんですよ。
高山:小説に出てくる「ペンタックス」そのまんまですね!
川村:そのまんま出したんです(笑)。そんなキャラって、思いつかないじゃないですか。自分では思いつかないようなことって、現実にいっぱいあるんだよね。取材って、欲しい情報を得られる以上の出会いが必ずあるから、絶対行ったほうがいいですよ。
高山:連載の一番新しい回(2017年3月号掲載の第6話)では、ボランティアのことを書いたんですね。もともと書きたかったんですけど、なかなか実態が分からないなと思っていたところで、大学に通っている友だちと久しぶりにごはんに行って。彼女に「そういえばサークルとか何入ってるんだっけ?」って聞いたら、「ボランティアサークルに入ってる」って言うからびっくりして、詳しい話を聞いたらすごく面白かったんですよ。私たちが普段想像しているボランティアとは、全然違ったりしたんですよね。
川村:いいですねぇ。どうせなら名前を隠して、ボランティアもやった方がいいと思う。
高山:やりたいと思っていました。想像だけでゼロから書こうとすると、書くのにも時間がかかるし、ちょっとやり方を変えてみたいなと思っていたんです。自分で実際に感じたり経験したものを出発点にして、そこを膨らませていくほうがずっと書いていられるなあって。
川村:どんどん取材して、出会った人をどんどんモデルにして書いて怒られちゃえばいいと思います。僕なんて、怒られまくりですよ(笑)。でも、小説を面白くするためには、怒られることなんてどうってことないですから。
次の作品のテーマは〈記憶〉
高山:次の作品は何を書くか、もう決まってらっしゃるんですか?
川村:『四月になれば彼女は』の後半のほうを書いているときに、恋愛って〈記憶〉だなと思ったんです。人間は何を体験したかで決まるとずっと思っていたんですけど、そうじゃなくて、何を覚えていて、何を忘れられないかで決まると思ったんですよね。そこのところは今回、書き切れなかった部分なので、次の作品で取り組んでみようかなと思っています。というわけで次の作品のテーマは、記憶です。
高山:楽しみです! 私は『ダ・ヴィンチ』さんで小説を連載させていただいてちょうど1年経って、お話的にもこれから大きく動き出すっていうタイミングだったんですね。映画のお仕事もしながらこんなに素晴らしい作品を書かれている川村さんとお会いできて、気合いを入れ直すことができた気がします。反省しました。自分は全然普通に寝てるしだめだぁ~と思って……。
川村:寝るのは別に悪いことじゃないよ!(笑)
高山:いえ。私はまだまだ、全然努力が足りてないなぁって思いました。だから……めちゃめちゃ頑張ります!
川村:じゃあ、小説家としてもアイドルとしてもめちゃめちゃ売れてください(笑)。
高山:はいっ。今日は本当にありがとうございました!!
かわむら・げんき●1979年、横浜生まれ。映画プロデューサーとして『告白』『モテキ』などを手がける。昨年は『君の名は。』『怒り』『何者』と手がけた3本の映画が連続公開。2012年、『世界から猫が消えたなら』で小説デビュー。同作は累計130万部突破の大ヒットに。小説第2作『億男』、第3作にして初の恋愛小説『四月になれば彼女は』もベストセラーに。
たかやま・かずみ●1994年2月8日、千葉県南房総市生まれ。女性アイドルグループ・乃木坂46所属。3月22日発売の最新17thシングル『インフルエンサー』まですべてのシングルで選抜入りの人気メンバーで、『しくじり先生』(テレビ朝日)などバラエティ番組ではソロでも活躍。『高山一実写真集 恋かもしれない』(学研プラス)発売中。
取材・文=吉田大助 写真=山口宏之
ニュースカテゴリーの最新記事
今月のダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ 2024年5月号 私の『名探偵コナン』履歴書/『ダ・ヴィンチ』創刊30周年
特集1 祝・連載30周年! 私の『名探偵コナン』履歴書/特集2 雑誌不況の“荒波”を乗り切れるか!? 『ダ・ヴィンチ』創刊30周年 他...
2024年4月6日発売 価格 850円
人気記事
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
人気記事をもっとみる
新着記事
今日のオススメ
-
![]()
インタビュー・対談
世界で2900万部売れた中国SF『三体』。女の子にベルトで殴り殺されるショッキングなシーンから始まる壮大なSF物語〈大森望さんインタビュー〉
-
![]()
インタビュー・対談
2歳から始めるオムケア!医師監修、男の子とお母さんのための性の絵本「ぞうちんとぱんつのくに」が発売
-
![]()
レビュー
この男モテすぎる…! 女たちが放っておかない、型破りでフリーダムなヒーロー誕生! お色気シーンもたっぷり
-
![]()
レビュー
青春×学園ミステリ「小市民シリーズ」がアニメ化。『氷菓』で有名な直木賞作家・米澤穂信が描く「謎解きの性」の話
-
![]()
レビュー
あたしのこと飼わせてあげる! 昼は美少女、夜はネコの奔放少女とネコ好きアラサー男性の同居生活を描いた『みーちゃんは飼われたい』
PR
電子書店コミック売上ランキング
-
Amazonコミック売上トップ3
Amazonランキングの続きはこちら -
楽天Koboコミック売上トップ3
楽天ランキングの続きはこちら